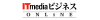管理職になりたくない人が増えていることは、多くの企業に共通しているお悩みです。とりわけエンジニア職や研究開発職、編集・記者職など、専門性の高い職種では昔からその傾向が強いようです。
これらの職種では、スペシャリストとしての技能や専門性を高めることを第一に考える人が多いことが背景にあると考えられます。ジョブ型が注目を集めるにつれ、そうした考えの人はますます増えています。やりたいこと・追求したいものがハッキリしていて「マネジメントをするよりもコードを書いていたい」「マネジメントをしていると最前線の技術に疎くなるのではないかと心配だ」という話も聞きます。
このような組織において、マネジメントを担う人材を見いだし育てることは、他組織と比べて難しいといえます。本稿では、このような専門職組織での管理職の育て方を考えます。
●専門職志向の人が管理職を経験する「3つの意義」
実は筆者自身も「管理職になりたくない」専門職の会社員でした。企業の管理職向けのテストや研修を開発する仕事ですが、自分自身は正直なところ、できることならずっとモノづくりだけをしていたいと考えていました。管理職になると、さまざまな調整ごとに時間を取られて好きな仕事ができなくなったり、専門性を維持できなくなったりするのではないかと感じていたからです。
エンジニア職や特定の専門職の場合、その分野における専門性を維持・向上させたいという理由で、管理職になることをためらう人も少なくないようです。また管理職の負荷が過重になっている問題や、負担に対して十分な報酬を期待できないといったことも、管理職が敬遠される要因となっています。
しかし、長い目で見れば管理職になることには意義・メリットもあります。
●意義1.キャリアの幅が広がる
専門職志向の人が管理職を引き受けるメリットの一つは、キャリアパスの広がりが期待できることです。現在企業において中堅〜管理職手前くらいの年代の層は、65〜70歳くらいまで働くことが当たり前になります。その年齢までずっとプレイヤーとして第一線を走り続けるという選択肢ももちろんありますが、それ以外にも複数の可能性を描いておいた方が環境の変化には柔軟に対応できそうです。
特定領域の専門性とマネジメント経験の両方を保有している人材は、専門性だけの人材に比べ、キャリアの選択肢は広がる傾向にあります。
●意義2.広い視野で新たなテーマ設定ができる
専門職志向の人が管理職を引き受ける意義の2点目は、管理職の視界で事業環境やサービス、プロダクトを捉えることで、プレイヤー時代とは異なる新たな探求テーマを発見できる可能性があることです。
管理職になるということは、それまでに入ってこなかったような、より経営に近い情報が入ってくるということでもあります。新たな情報を得ると、これまでよりも対象物がより詳細に見えてきたり、別の角度から捉えられるようになったりと、仕事上のブレークスルーが起きやすくなります。
もともと専門職志向の人は、仕事そのものにはモチベーション高く取り組めていることが多いため、研究しがいのあるテーマや取り組んでみたい対象が見つかると、それをポジティブに受け止め、推進することができます。
●意義3.権限を生かしてより大きな仕事やチャレンジができる
専門職志向の人が管理職を引き受ける意義の3点目は、権限を生かしてより大きな仕事やチャレンジができることです。
どんな職種であっても、管理職になることの最大の利点に、組織のリソースを借りてスケールの大きい仕事ができることがあります。もちろん、そこには責任も伴いますが、やりたいことが明確にある人や、新しいことに取り組むことそのものに喜びを感じる人は、管理職としての権限を存分に生かして自分のやりたいことを組織の戦略推進にうまく統合していけると良いでしょう。
管理職の仕事のこのような側面は、実際に管理職を経験することによって認識されることが多い醍醐味でもあります。
筆者が所属するリクルートマネジメントソリューションズが行った調査では、管理職になりたくなかった人が管理職昇進後にその気持ちがポジティブに変化した理由を尋ねたところ、「より大きな影響力を周囲に及ぼすことができているから」(32.7%)、「現場の仕事とは違う面白さがあるから」(32.7%)と、管理職ならではの仕事のダイナミックさ、面白さを指摘する声が選択率の1位を占めています(「管理職意向の変化に関する実態調査」2016年)。
●プレイングマネジャーの時代
筆者自身も、結果として管理職になりましたが、以上のような意義を感じることは実際にありました。また思った以上に、プレイヤーとしての専門性を発揮できる場面も多いように感じました。
昨今の管理職はプレイヤーとしての業務を持ついわゆる「プレイングマネジャー」がほとんどです。これも筆者の所属企業が行った調査ですが、150人の管理職中、プレイヤー業務を持たないと答えたマネジャーはわずか2.7%しかいませんでした。
つまりどんな管理職でも、ほとんどの場合プレイヤー業務を多かれ少なかれ持つことになります。
従来、プレイングマネジャーは良くないものであり、マネジャーはマネジメントに専念すべきであると言われてきました。しかしここまでプレイングマネジャーが増えている以上、プレイングマネジャーであることを前提とし、むしろその特性をポジティブに捉えてマネジメントを再考してみるとどうでしょう。
変化の激しい時代だからこそ、プレイヤー業務を持ち専門性を磨き続けながらマネジメント業務も担うことが、管理職の一つの在り方として注目されます。このような管理職の在り方は、専門職志向の人にとっても、選択肢の一つとして考える価値のあるものではないでしょうか。
●これからの管理職が身につけるべき「戦略的プレイング」
リクルートワークス研究所が提言する「プレイングマネジャーの時代2020」によれば、すぐれたプレイングマネジャーの要件の一つとして「プレイング業務を戦略的に活用する」というスタンスがあります。高いチーム成果を実現するマネジャーは、プレイヤーとしての業務にメンバーの育成やコンディション把握など、複数の戦略的意図を持たせているというのがその内容です。
もしあなたがエンジニアや専門職の多い組織を束ねる管理職で、次の管理職候補を育てようとしているのであれば、ぜひあなた自身が戦略的プレイングマネジャーになることをお勧めします。
つまり、自分自身が管理職の仕事を面白がるところをメンバーに見せたり、管理職であってもプレイヤーとしての仕事の中で新しいチャレンジができることを示したりすることが、戦略的プレイング業務に当たります。
管理職とはこうあるべきという像にとらわれず、自分自身の仕事領域における新しい管理職像を自ら実践し、後に続く人に示すことが、最も有効な管理職育成です。
●著者情報:児玉結
リクルートマネジメントソリューションズ HRDサービス開発部主任研究員。広告業界などを経て2008年に入社し、以来一貫して企業向け研修など人材育成サービスの企画に従事。新入社員〜管理職まで、幅広い領域の企業研修の企画を担当。マネジメントやリーダーシップ、学習や成長といったテーマでの調査・研究も行っている。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN