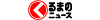クルマのタイヤは、走れば走るほどに消耗し劣化していきますが、もしもタイヤを交換せずそのまま乗り続けた場合、一体どうなるのでしょうか。主に夏タイヤの場合で紹介します。
劣化した「タイヤ」は安全性も低下?
クルマのタイヤは、走れば走るほどに消耗し、また時間の経過などによって劣化していきます。
そうして劣化したタイヤは走行性能が低下するため、定期的な交換が推奨されています。
では、もしもタイヤを交換せずにそのまま乗り続けた場合、どのような事態が発生するのでしょうか。夏タイヤの事例を中心に紹介します。
クルマのタイヤの摩耗は、おおよそ5000キロの走行で1mmすり減るといわれており、1万キロで2mm、3万キロ走るとなんと6mmも摩耗する計算になります。
そんな摩耗したタイヤで実際に走行すると、一体どうなるのでしょうか。
まずは「濡れた路面」で滑りやすくなります。
タイヤの表面には溝が作られており、これが排水機能を高めています。
しかし、摩耗して溝が無くなると排水機能が低下。タイヤと地面の間に水の膜が生じ、「ハイドロプレーニング現象」呼ばれるブレーキもハンドル操作も効かなくなる危険な状態に陥る可能性が高まります。
また、たとえ乾いた路面であっても摩耗が進めばタイヤが地面を捉える力が低下します。
同時にブレーキをかけた際の制動距離が伸びたり、乗り心地も悪化します。
くわえて走行性能が低下すると、それだけクルマを動かすのにも余分なパワーが必要になるため、ガソリンの消費量も増加。
つまり燃費も悪化してしまうのです。
「交換タイミング」は3〜4年か?
このように、タイヤが劣化するとスリップしやすくなるほか、ブレーキの効きが悪くなるなど非常に危険な状態になります。
そのことからも、摩耗した状態のタイヤで公道を走ることは法律で明確に禁止されています。
道路運送車両法の保安基準を見ると、タイヤの溝の深さは1.6mm以上を有することが定めており、これを下回ると車検に通らなくなります。
また、タイヤの溝が1.6mm以下の状態で公道を走行すれば「整備不良(制御装置等)」として、普通車の場合は反則金9000円と違反点数2点が科せられるのです。
そして多くのタイヤは、溝の深さが1.6mm以下になると「摩耗状態が危険であることを示すサイン」が現れます。
これはスリップサインと呼ばれるもので、タイヤ側面に記された「三角マーク」からタイヤの溝側を見ると溝の底部が盛り上がっているもの。
タイヤの溝が1.6mm以下になると、この盛り上がった部分がハッキリと見えるようになり、タイヤの交換時期を知らせてくれるのです。
※ ※ ※
新品のタイヤの溝の深さは、約8mmほど。
先述のように1万キロ走行すると2mm減る計算になるため、おおよそ3〜4年で次の新しいタイヤへと交換することが求められます。
ただし走行距離が少なく、タイヤの減りがあまり見られない(溝が残っている)からといって、長期にわたって使用するのもNGです。
タイヤメーカーによると、ゴムの性能劣化を考慮し、使用開始後5年以上が経過した場合は走行距離に関わらず交換を推奨しています。
新しいタイヤは決して安い買い物ではありませんが、摩耗したタイヤを交換せずに走り続けることにはデメリットしかありません。
もちろん冬場に使うスノータイヤ(スタッドレスタイヤ)も同様に、整備不良にならないよう定期的にチェックし、早めの交換を心がけるべきでしょう。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN