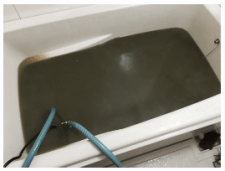『「存在感」はつくれる』(大塚ちづる 著、フォレスト出版)の著者は、日本の総合商社勤務を経て、米国投資銀行ゴールドマン・サックスの東京支社、ニューヨーク支社とアジアパシフィック支社で約20年勤務してきたという人物。
その過程においてはさまざまなビジネスリーダーと関わり、アドバイザーとして5000人以上におよぶグローバル人材の育成・管理に携わってきたのだそうです。
そんな私がビジネスパーソンのコーチングにおいて最も重視しているのが、「プレゼンス」です。プレゼンスとは、直訳すると「存在感」ですが、その場にいるだけで議論をコントロールしてしまう、直接話していなくても信頼してしまう、つい仕事をお願いしたくなってしまう、そういった「影響力」もプレゼンスに含まれます。(「プロローグ」より)
もちろん、第一印象もまた重要なプレゼンスのひとつ。なぜなら第一印象や「周囲からどう見られているか」は、キャリアアップや転職において欠かせない要素だともいえるからです。
しかも自分の本当の可能性が他人の目からは見えないからこそ、その可能性を持っている人間だと相手に思わせることが大切なのだと著者は主張しています。
もう一つ、ビジネスにおけるプロとは、エキスパートであることを他人にしっかり伝えられる人だと思います。プロの仕事をすれば良いわけではありません。第一印象からプロであることが必要だということです。(「プロローグ」より)
つまり著者は、プレゼンスの大切さを理解してもらおうという思いから本書を執筆したわけです。ポイントは、日本の外資系企業で働く“もったいない人材”が、ニューヨーク帰りのメンターによってプレゼンスを磨かれ、本当の自分の可能性を発揮していくというストーリー仕立てになっている点。そのため読者は、プレゼンスの重要性を無理なく理解できるわけです。
きょうは第4章「人に理解されるためのコミュニケーション」のなかから、その解説部分に注目してみたいと思います。
プレゼンス上級者は「謝らない謝り方」で許される
仕事にミスはつきもので、場合によっては「謝る」ことも必要になるでしょう。しかし謝るというのは、プレゼンス的にはとてもリスクの高い行為なのだそう。
たとえばプレゼンの場でつい話が長くなってしまい、相手から「早く結論を」と冷たく釘を刺されたとします。しかし、そこで「申し訳ございません」と素直に謝ってしまったら自分のミスを認めたことになるため、その場での“影響力”は低くなってしまうわけです。
プレゼンスの低い人の話を積極的に聞こうという人はいません。だからなるべく謝らず、回避するようにします。
もしも話が長いと指摘されたら、「これから良いところですから」「そうですね、ちょうど良い頃だと思いますので、本題に入りましょう」とポジティブに切り返します。
こう言えば話が長いことはあなたのミスにはなりません。あくまでも想定内のことにしてしまいます。上手くいけばこのスマートな切り返しに、相手は一目置いてくれるかもしれません。(155ページより)
そもそも「すみません」と謝るのは、相手に許しを乞う行為。相手にとってはどうでもいいことであるとも解釈できるわけで、だとすれば謝る側の単なる自己満足だと言うことになってしまいます。
したがって一刻も早くミスを修正し、正しい情報を伝えることのほうがよほど相手に対して誠実であるわけです。
それでも、大事な会議に遅れて大勢の人を待たせてしまったら、謝りたくなるのが人情でしょう。
そういうときには平謝りするのではなく、「お待たせしました」の一言で良いのです。卑屈になって謝るより、颯爽と部屋に入って「お待たせしました。では始めましょう」と悪びれずに言うほうが、相手も「怒り」というネガティブな感情がそがれるので、その場の空気にプラスに働きます。(156ページより)
そうすれば「ここまで悪びれていないということは、なにか特別な理由があったのだろう」と相手が理解してくれるそうで、それこそがプレゼンスの真骨頂だというのです。(155ページより)
理解されるにはオープンマインドであること
コミュニケーションの基本は、「オープンマインド」であること。たとえば会議でも、心を開いて本音で話し合ってこそ、建設的な意見や考えが生まれるということです。しかし、それはなかなか難しくもあるでしょう。そこで著者は、自分がオープンマインドになっているかどうかを事前に確認してみることを勧めています。
オープンマインドであることを表現するしぐさで一番有効なのはやはり「表情」です。
とくに重要なのは、顔に占める面積が非常に大きい口まわりです。コロナ禍でマスク生活を強いられた際に意思疎通がとれず苦労した人は多いでしょう。それは口角の動きが見えなかったからです。(159ページより)
たしかにそのとおりで、マスクをしていると表情が読み取りにくくなるため、笑っていても怒っていても同じ顔に見えてしまいがち。しかし、だからこそ逆の発想をすることもできます。つまり、口角さえ上げておけば、自然と微笑んでいるように見えるものだということ。
当然ながら、それはオープンマインドな印象につながります。本当は心が下がり気味だったとしても、口角をつねに上向きにしておけばイメージが変わり、結果的にはまわりに自然と人が集まってくることになるわけです。
しかしそうはいっても、仕事に集中したいとか、考え事をしたいとか、あるいは本当に気分が落ちていて話しかけてほしくないというようなときもあるもの。そんなときは無理をせず、“いまは話しかけないで”サインを出すといいそうです。
私は小さなマスコット人形をデスクに用意して、それを人が見えるところに置くようにしていました。その意味は事前にまわりの人に伝えてあるので、これが出ていると「あ、今は話しかけないでほしいんだな」と適度に距離を置いてくれます。(160ページより)
顔に出して精神的なバリアを張るよりも、たしかにこうしたやり方のほうがスマートで効果的かもしれません。(159ページより)
「プレゼンスは、自分の可能性を引き出すための魔法」だと著者は表現しています。そうした考え方に基づいた本書を活用し、“もったいない人材”から“輝く人材”へとステップアップしたいところです。
>>Kindle unlimited、2万冊以上が楽しめる読み放題を体験!
https://www.lifehacker.jp/regular/regular_book_to_read/ 「毎日書評」をもっと読む
https://voicy.jp/channel/2066 「毎日書評」をVoicyで聞く
Source: フォレスト出版










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN![ライフハッカー[日本版]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/img/ip_logo/lifehacker.gif)
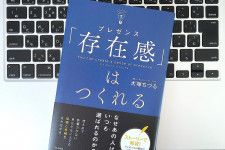
![ライフハッカー[日本版]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/lifehacker/s_lifehacker_2405_book_to_read-1476.jpg)
![ライフハッカー[日本版]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/lifehacker/s_lifehacker_2405_book_to_read_weekend_56.jpg)
![ライフハッカー[日本版]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/lifehacker/s_lifehacker_2405_book_to_read-1474.jpg)
![ライフハッカー[日本版]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/lifehacker/s_lifehacker_2405_book_to_read-1471.jpg)
![ライフハッカー[日本版]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/lifehacker/s_lifehacker_2405_book_to_read-1469.jpg)
![ライフハッカー[日本版]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/lifehacker/s_lifehacker_2405_book_to_read-1467.jpg)
![ライフハッカー[日本版]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/lifehacker/s_lifehacker_2405_book_to_read-1466.jpg)
![ライフハッカー[日本版]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/lifehacker/s_lifehacker_2405_book_to_read-1465.jpg)
![ライフハッカー[日本版]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/lifehacker/s_lifehacker_2405_book_to_read-1464.jpg)
![ライフハッカー[日本版]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/lifehacker/s_lifehacker_2405_book_to_read-1460.jpg)