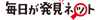この記事は月刊誌『毎日が発見』2024年4月号に掲載の情報です。

私の人生は何だったのか
生涯多くの本を著した高名な哲学者の晩年の生活を伝えるドキュメンタリー番組を見たことがある。原稿を口述していたその人は突然こう呟いた。
「一体、私の人生は何だったのか」
「何だったのか」というのは、否定的な意味が込められているのだろう。どれだけ多くの仕事をし、それによって富と名声も手に入れたとしても、死を前にしては何の価値もない。そうであれば、自分が成し遂げてきたことには何の意味もなかったのではないか。仕事だけではない。自分のこともすぐに忘れられてしまうのではないか、と。
ローマ皇帝のマルクス・アウレリウス(※1)は次のようにいっている。
「すぐにお前はすべてを忘れるだろう。そして、すぐにお前のすべても忘れられるだろう」(『自省録』)
「すべてのものは儚(はかな)い。記憶するものも記憶されるものも」(前掲書)
そもそも、自分自身が消えてしまうのである。これが人生なら生きることにはたして意味があるのか。老哲学者もこのようなことを考えて、「一体、私の人生は何だったのか」と呟いたのだろう。はたして、こんなふうに思わないで晩年を生きることはできるのだろうか。二つのことを考えなければならない。
※1 121〜180年。第16代ローマ皇帝。著作に『自省録』がある。
生の痕跡
まず、仕事は決して無にはならないということである。死がどういうものかは誰にもわからない以上、死ねば何もかも忘れることになるかどうかはわからない。しかし、自分のすべてが忘れられるかはわからない。アウレリウスは「すぐにお前のすべても忘れられるだろう」といっているけれども、彼が書いた『自省録』が今も読み継がれるというようなことはたしかにある。
たとえ仕事も自分のことも忘れられることになったとしても、自分の生の痕跡は残る。仕事といっても形になるものばかりではない。直接、間接に人から影響を受けることなしに生きることはできない。幼い子どもを見れば心が癒やされる。何も作り出さなくても、子どもはまわりの大人に影響を与えているのである。誰かの語る言葉を聞いて、また、本を読んで心を揺さぶられることもある。自分も何かの仕方で他者に影響を与えている。その影響は、喩(たと)えてみれば、池に投げ入れられた石によってできた波紋がやがて見えなくなってしまっても、いつまでも続く。
このように人に影響され、自分も影響を与えるのは、人と人がつながっているからである。この人とのつながりは、過去・現在・未来のすべての人類、さらには生きているものも生きていないものも含めたこの宇宙の全体にまで及ぶとアドラー(※2)は考えている(『人間知の心理学』)。
時間的には、未来のすべての人類とのつながりまでも考えるとすれば、自分が死んでからの世界のことも考えなければならない。内村鑑三(※3)は次のようにいっている。
「われわれがこの世の中にあるあいだは、少しなりともこの世の中を善くして往きたいです。この世の中にわれわれのMementoを遺して逝きたい」(『後世への最大遺物』)
この地球を愛した証拠、同胞を愛した記念碑(memento)を置いて逝きたいという。自分が忘れられないために残すのではないのである。
「次の世代に役立つようにと木を植える」(『老年について』中務哲郎訳)
これはキケロー(※4)が引くスターティウスの言葉である。今、木の苗を植えても、それがどうなるかは自分の目で確かめることはできない。それにもかかわらず、農夫は仕事に励む。自分ではない他の人のためにする将来への備えは、自分がこの世界からいなくなっても残るのである。この木を植えるというのは比喩であり、自分が生きたことを後世に残すことはできる。亡くなった人の言葉をふと思い出す時、その人の存在を強く感じることがある。一体、その人は何をいおうとしたのかを考えることもある。その時、ずいぶんと前に亡くなった人の言葉が今も生きた力となって働いていることに驚く。
※2 アルフレッド・アドラー。1870〜1937年。オーストリアの精神科医、心理学者。
※3 1861〜1930年。キリスト教思想家。
※4 紀元前106〜紀元前43年。共和制ローマ末期の政治家、弁論家、哲学者。
今を生きる
「一体、私の人生は何だったのか」と思わないで生きられるために考えなければならないもう一つのことは、今を生きることである。後世に何かを残すということと相容れないと思われるかもしれないが、何かを残そうとすれば、先のことを考えてはいけないのである。
サマセット・モーム(※5)が次のようにいっている。
「あまりに時間がかかるというので若い時は避けるような仕事にも、老年になると造作なく取りかかれるものである」(The Summing Up)
これは普通に考えられていることと反対である。老人は人生に限りがあると考えて大きな仕事に着手しようとしないが、若い人は自分の前にある人生が長いと考えるので、大きな仕事を手がけられると普通は考えるが、実際には、若い人の方が時間があるはずなのに、手がけようとしないことがある。数えるからである。時間はあったのに、なぜ途中で仕事を投げ出すのかといわれることを恐れ、必ず完成できるという確信がなければ着手しようとしない。
他方、老人は残りの人生が短いことを当然のこととして受け止めているので、数えない。手がけた仕事がたとえ完成しなくても、そのことで誰からも責められることはないだろうと考えられる。
鈴木大拙(※6)は、親鸞の『教行信証』の英訳の仕事を引き受けた時、九十歳間近だった。しかし、翻訳を成し遂げられるだろうかとは考えなかったのであろう。誰かが手がけなければ、跡を継ぐ人もいない。その誰かになろうと思ったのだろう。
たしかに、老人であっても、あるいは老人であれば、若い人以上に先の人生が短いことを思って大きな仕事に取りかかれないことはあるだろうが、仕事だけでなく先のことを考えないで生きられるようになれば、人生で成し遂げてきたことが何も残らないのではないか、自分のことも忘れ去られるのではないかと絶望することはないだろう。
※5 1874〜1965年。イギリスの小説家、劇作家。著書に『月と六ペンス』などがある。
※6 1870〜1966年。仏教学者。禅について英語で著作を行った。著書に『日本的霊性』『禅とは何か』などがある。
※記事に使用している画像はイメージです。
岸見一郎(きしみ・いちろう)先生
1956年、京都府生まれ。哲学者。京都大学大学院文学研究科博士課程満期退学(西洋哲学史専攻)。著書は『嫌われる勇気』『幸せになる勇気』(古賀史健氏と共著、ダイヤモンド社)をはじめ、『幸福の条件 アドラーとギリシア哲学』(角川ソフィア文庫)など多数。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN