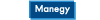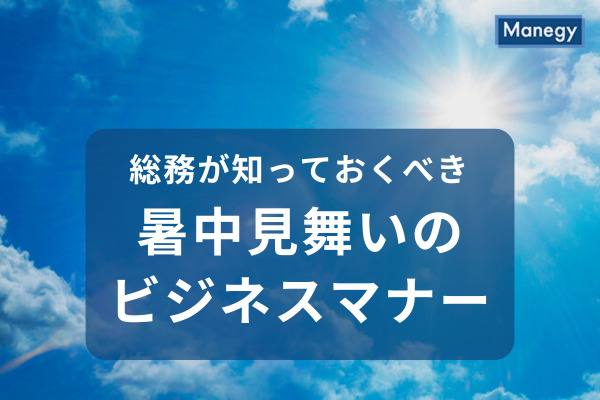
最近はメールで済ませることも多い季節の挨拶ですが、大切な顧客や取引先に対しては、丁寧な時候の挨拶をしておきたいものです。今回は暑中見舞いの書き方として、総務担当者が知っておくべきマナーについて紹介します。
目次本記事の内容暑中見舞いの基礎知識
暑中見舞いは二十四節気に沿った慣習であり、7月7日頃の小暑から22日頃の大暑を経て、8月8日頃の立秋前日までの間に季節の挨拶を送ります。立秋を過ぎてから8月末までの期間は、「残暑見舞い」として区別しなければなりません。
ビジネスの場合は主に取引先、または顧客などに送ることになりますが、各部門担当者から総務が作成を任されるかもしれません。そのため年賀状と同様に、基本的なマナーと書き方を知っておく必要があります。
ビジネス版暑中見舞いの書き方
暑中見舞いは一般的なはがきや手紙とは体裁が異なり、「拝啓〜敬具」のような頭語と結語のセットは必要ありません。全体の構成は4つに分かれており、それぞれに形式と内容が決められています。基本的には以下の点に注意して、全体を組み立てるとよいでしょう。
①お見舞いの挨拶
「暑中(残暑)お見舞い申し上げます」または「暑中(残暑)お伺い申し上げます」が一般的で、本文より大きめの文字にして句点はつけません。
②主文
日頃の付き合いに感謝する言葉とともに、7月中は「盛夏の候」「酷暑の候」「炎暑の候」、8月に入ると「晩夏の候」「残暑の候」「秋夏の候」などの時候の挨拶で主文をまとめます。夏季休業のお知らせを添えてもよいでしょう。
③結びの挨拶
相手の健康を気づかう言葉が一般的ですが、ビジネス版では「今後ともよろしくお願いいたします」でも十分でしょう。
④日付
詳細な日付は記入せず、年号・年数に続けて「盛夏」、残暑見舞いの場合は「晩夏」「立秋」などの言葉を添えます。
最後に簡単な例文を紹介します。
暑中お見舞い申し上げます
平素よりご高配を賜り、誠にありがとうございます。
酷暑の候、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
尚弊社では以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
8月○日〜8月○日
ご了承の上、今後ともよろしくお願いいたします。
令和○年 盛夏
好感度アップのワンポイント
日本の挨拶文には、伝統的な型があります。その型を崩すことは相手に失礼でもあり、自身の知識を疑われることにもなります。できれば社内に礼儀作法のマナーブックを備え、正確な表現をチェックしたほうがよいでしょう。
しかし、決まった文面で印刷されたはがきでは、相手を気づかう心が伝わりません。ここが難しいところですが、「今年の暑さは格別ですが、くれぐれも体調にはお気をつけください」などの、簡単な一言を自筆で付け加えると、相手側の受けとめ方が大きく変わります。
まとめ
ビジネスの暑中見舞いは、プライベートとは異なる部分もあるので注意が必要です。現在は印刷はがきが主流ですが、手書きでひと言添えると、相手に対する気づかいが伝わります。また、暑中見舞いを受け取った場合には、必ずお礼の気持ちを込めて返信することを忘れないようにしましょう。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN