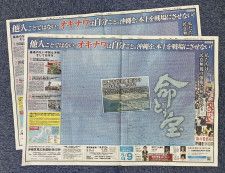特定利用空港・港湾に合計370億円 災害対応の強化に期待できるが…気になる「米軍の利用促進」
内閣官房国家安全保障局によると、通常の公共事業は民生利用の必要性に基づき予算を配分する。「特定利用空港・港湾」に選ばれ自治体などの施設管理者と政府が平時や緊急時の円滑な利用について確認書を交わすと、予算を配分する際に自衛隊や海上保安庁のニーズも加味する。事業を促進して使いやすくする狙いがある。
特定利用港湾となった博多港には予算17億円を充てた。管理者の福岡市港湾計画部によると、大型船舶の航路を確保するために海底を掘り下げ、岸壁を強化する事業。河川の土砂がたまりやすいため、数年前から整備を進めているという。
吉岡麻子計画課長は「災害時の物資輸送など九州の玄関口である博多港の役割は大きい。訓練を通して自衛隊との連携が進めば災害対応の強化につながる」と話す。
沖縄は、国管理の那覇空港と石垣市管理の石垣港が選定されている。県が管理者の施設は予算計上の方法や米軍の利用が増えるのではないか、といった不明点を確認中で「判断を下す状況にない」(港湾課)と慎重な姿勢を崩していない。
米軍は日米地位協定によって民間港を使うことが認められている。3月11日には米海軍のイージス駆逐艦が石垣島(石垣市)に寄港。水深が足りないことから市が接岸を拒否したため、沖合に停泊し、民間船に乗り換え上陸した。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN