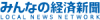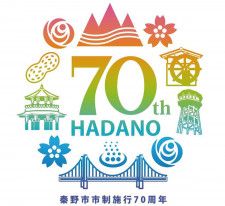現在の町名となっている「上里」が誕生して5月3日で70周年を迎えた。(本庄経済新聞)
JR高崎線・神保原駅北の街並み
今から約330年前の元禄(げんろく)の頃、現在の上里町は21の村に分かれていた。その後、一部の村で合併が起こった。1889(明治22)年、元禄年間から続いた石神村・忍保(おしぼ)村・八町河原村が合併しそれぞれの村から1字用いて「神保原村」、嘉美村・三町村・七本木村・堤村が合併して「七本木村」、長浜村・帯刀(たてわき)村・五明(ごみょう)村・藤木戸村・大御堂(おおみどう)村が合併して「長幡村」、黛村・金久保村・昆沙吐(びさど)村・勅使河原村が合併して「賀美(かみ)村」が誕生した。
同町の前身である「上里村」は1954(昭和29)年5月3日、4つの村が合併して誕生した。「上里」の村名は、県内で一番上(北)に位置しており、円満な農村であること、簡単に書きやすいことなどから選ばれたという。当時の人口は1万6979人。村役場は、旧神保原村役場に定められたが、他の旧村役場もそれぞれ「支所」として残った。
上里村は1971(昭和46)年7月30日、当時の村長が埼玉県知事に対して、上里村の町制施行認可申請を行った。10月10日に県議会で審議され、同月12日「埼玉県報」で告示、県知事から自治大臣(当時)に届け出が行われ、11月3日付けで「上里町」となった。2021年には「町制施行50周年」を迎えた。現在の人口は3万485人(2024年4月末日時点)。
町内を通るJR高崎線の「神保原駅」(上里町神保原)は1897(明治30)年11月に開業。上里村が誕生する前であり、当時の村名「神保原村」から「神保原駅」と名付けられ現在に至っている。同駅は、開業以降、再開発が行われず大正・昭和初期の面影が残る駅舎で、「上里」の村から町への変遷を見守ってきた。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN