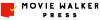閉塞感が漂う時代をうがつ可能性にあふれた映画。『渇水』をネタバレなしでレビュー
■現代が抱える問題を映しだした「市民に寄り添う」映画
ゆとりや豊かさ、ひいては“潤い”が足りない。いま述べたものは僕個人の感覚だが、とはいえ時代の一側面、“気分“としてニッチなものではないであろうことも肌で感じている。そうした渇きを抱えて生きるなかで、一つの作品に出合った。タイトルは『渇水』(公開中)。この字面、まさにいまの状態を示したものではないか。
本作は1990年に発表され、芥川賞候補作になった河林満の小説を原作とし、企画プロデュースを白石和彌、監督を高橋正弥が手掛け、生田斗真が主演を務めた映画だ。料金滞納家庭の水道を停める仕事を行う水道局員の岩切(生田)が、母親(門脇麦)の庇護を存分に受けられていない幼い姉妹(山崎七海、柚穂)と出会い、己の存在意義を自問する――。公と民、貧と富。自然の恵みである水すらも、金がなければ自由に享受できない社会…。他人事には思えない題材に、興味という次元を一つ飛び越えた“渇望“を感じた。33年前に発表された小説を、いまの感覚で映画化した本作を飲み干すことが、この困難な時代を生き抜く活力になるのではないか。つまりいまの自分にとって必要な作品に違いない、という確信めいたものがあったのだ。
映画は時代を映すものだ。人や生活、社会を掘り下げて描けば、舞台や時代設定によらず自然と現代性が立ち上がってくる。不謹慎な言い回しだが「時代が荒めば傑作が増える」というのは実に理にかなっていて、理不尽な現実に相対する“武器“、あるいは癒し悼む“祈り“として文化芸術への必要性が高まる。カンヌ国際映画祭の審査員賞に輝いたラジ・リ監督作『レ・ミゼラブル』(20)や、ケン・ローチ監督の『わたしは、ダニエル・ブレイク』(17)、是枝裕和監督の『万引き家族』(18)などもそうだが、作品は現実から生まれる。そうした「市民に寄り添う」映画の系譜に、『渇水』もあるといっていい。
そしてまた、「時代を先見する」慧眼も名作、傑作の条件。映画という表現はインスタントに撮って出しができないぶん、数年先の時代の流れを読む力が必要になってくる。あるいは、時代に左右されない“普遍性“をしっかりと宿らせることができるかどうか。10年以上かけて映画化にこぎつけたという高橋監督は「原作で描かれている事象は2020年代の現代でもなにも解決していない」と語っているが(公式サイト内のコメントを参照)、『渇水』はこの国が30年以上抱える恒常的な問題を、もう歯止めが効かないところまで来ている現代の切迫感をもって描写している。
■ちりばめられたモチーフにより刷り込まれる「水」のイメージ
そう感じられる要因は、生活感だ。いまこの瞬間、我々と同じ世界で生きている人々の肖像や生活を切り取っていられるかどうか。劇映画であり職業俳優を起用している以上フィクションでしかないのだが、観客が自らを重ね、溶け合える「生の痛み」が伴うかどうかで作品の見え方はまるで変わってくる。
そして『渇水』は、この生活感を生みだすにあたり、様々な工夫が施されている。一つは、汗。登場人物の体表を流れる汗を丹念に映し取ることで、綺麗なだけではない生々しさ=生活感や、日照り続きで渇いているという状況の説明、「水」というテーマにもリンクする映像言語といった要素をカバーしているのだ。汗や雨、水槽にプール、川に滝、公園の水飲み場にシンクやシャワー、浴槽に溜めた水、ビールなどの飲み物に溶けたアイス等々、劇中では多彩な水にまつわるモチーフがちりばめられており、さりげなく滑らかに観客の脳内に「水」のイメージを刷り込んでいく。
また、個人的に惹かれたポイントは、具体的な地名を入れていること。本作は群馬県の前橋市を中心に撮影が行われたそうだが、架空の街ではなく「前橋市周辺の話」という設定になっていることで、現実味が段違いに高まっている。群馬県といえば、日本でも有数の猛暑エリア。「水不足」や市民の「渇き」にも説得力が付加され、切実な物語として観客に訴えかける効果をもたらしている。
『渇水』は生活感を担保する“汚し“の演出も効いていて、料金滞納家庭の部屋を一目見るだけで生活苦を感じられたり、岩切が暮らす無機質な家(妻子が出ていったことで、人がいた痕跡が抜けていく)とのコントラストが際立ったり…。それでいてリアル一辺倒にならず、映画的な瀑布のシーンや家の外観を上下動して観察するカメラワークを盛り込んだり、姉妹に女子高生がエールを送るシーンには「絶望だけでは終わらせたくない」という作り手の“意志“を感じられたりと、いい意味でトーンが無難に整えられていないのだ。そしてこの衝動にも似た荒々しさが、後半に用意された岩切の“暴走“につながる助走の役割も果たしている。要は、生きづらさを粛々と描いているのではなく、押し込めていた憤りや願望、祈りといった原液の感情が漏れ出てしまっている瞬間を繕わず、隠さないということ。そこに我々は、作り手が「描かずにはいられなかった」正直さを感じるのだ。
■心に闇を抱え、狂気の欠片を漂わせる岩切を体現した生田斗真
そうした微妙なバランスを完璧に魅せ切ったのが、生田斗真。『予告犯』(15)や『友罪』(18)、『彼らが本気で編むときは、』(17)等々、“痛み“を抱えた市井に生きる人物たちを繊細に演じてきた彼が演じる岩切は、ただの苦労人ではない。心に闇を抱えていて、狂気の欠片が常に漂っている。それでいて同僚の木田(磯村勇斗)のように自分の感情を素直に露出できないぶん、体内によどみが溜まってしまっており、2人で飲んだ時に「テロでも起こすか」と冗談交じりに言うが、その眼は笑っていない。かといって『ファイト・クラブ』(99)や『スクラップ・ヘブン』(05)のように破壊衝動に身をゆだねることもできず、風船がどんどん膨らんでいくような危うさだけが増大していく。
ダークサイドにずりずりと引きずり込まれていく「病みかけ」な人間の生々しさを解像度高く具現化した生田の芝居が、先に述べた作品に漂う不安定さと呼応し、終盤に決壊する――。見せ場のシーンをある種アンコントロールに見える荒々しさで描き切ったという意味でも、『渇水』はどこか歪で生々しく、それでいて私たちと同じストレスを抱えながらもがく“信頼できる“一本。いまこの時代に世に放たれる意味が、しっかりと宿っていた。
余談だが、主人公の岩切という名前も興味深い。「岩を切る」と聞いて想起するのは「うがつ」という言葉。「涓滴(けんてき)岩をうがつ」ということわざがあるが、わずかな雫であっても、一滴一滴が長い年月をかけることで岩にまで穴をあけるさまを示している。作り手の想いを乗せ、歳月をかけて完成したこの『渇水』もまた、閉塞感が漂う鬱屈としたこの時代をうがつ可能性にあふれている。
文/SYO
※高橋正弥監督の「高」は「はしご高」が正式表記
※山崎七海の「崎」は「立つ崎」が正式表記










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN