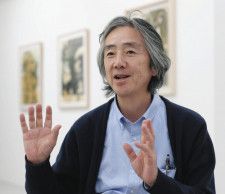画家・大河原愛氏が描く絵は、精神をどこか遠くへ置き去りにするような寂寥感を漂わせながら、同時に人の魂を落ち着かせる力が宿っている。
2020年には『ブレイク前夜』(BSフジ)で取り上げられ、月刊『アートコレクターズ』(生活の友社)の「完売作家特集2024」では人気作家として名前を連ねるなど、活躍の目覚ましいアーティストだ。絵画だけでなく、桐野夏生『日没』(岩波書店)では装画も担当するなど、その描線が多くの人々を魅了している。客観的にみれば“売れている画家”といって差し支えないだろう。
だが大河原氏は、戸惑ったように「10代の頃、親からも絵の才能がないといわれ、当時自分でもそう思っていました。幼少期は劣等感だらけのところからスタートして、あの頃は、『絵を描いていなければ自分に生きる価値はない』くらいに感じていたんです」と真顔で答える。彼女の半生を紐解くと、どうしても自分に自信が持てない理由と、画家として描き続けられる理由の双方が浮き彫りになった。
◆「成績優秀な兄」と比べ続けられた
「おそらくそれは、生まれ育った家庭環境に原因があるようにも思うのですが」
大河原氏の家族構成は、両親と兄がひとり。学生時代の父親は、働きながら妹や弟を高校に通わせるなど、苦労を重ねている。それでいて成績も優秀な人物だったという。当時は、会社員として夜間警備の仕事に従事していた。家庭の経済的事情で進学できず、学ぶことを断念した父親にとっての自慢は、成績優秀な兄だった。
「兄は大して勉強していないのに本当に優秀な人で、いわゆる成績が“オール5”でした。勉強以外に運動神経も良く、父親はそんな兄のことをいつも褒めて自慢していました。そして、そんな兄に対して『東大にいけ』と父はいつも言っていました。結局、持病があった兄は父の反対を押し切り、自ら近くの有名大学に入学しましたが……」
しかし学業ならば大河原氏も苦手ではなかった。
「小さい頃は、『兄がいかに優秀か』を毎日のように父から聞かされていました。ただ、自分も勉強が不得手だったわけではなく、兄と比較されたくない思いもあって勉強していたので、成績は良いほうでした。体育は平均的だったので、兄に大きく劣る点はそこだけだったと思います。それでも父が嬉しそうに語るのは兄だけ……。兄ほどでないにしても、なぜ私は同じ点数を取っても褒められもせず、期待もされないのか……と思っていました」
◆“風変わりな父”が兄ばかり褒める理由は…
大河原氏は実際、父親に「なぜ自分を褒めてくれず、いつも兄ばかりなのか」と問うたことがある。
「そのときの父の回答は、微笑みながら『愛は女の子だから……』でした。どんなに努力をしても、父親から認められることはないと気づいた瞬間でした」
兄しか褒めない父親。身体的な虐待を受けているわけではないものの、緩やかに苦しい時間が続いた。何かの折に父に刃向かえばすぐに「出て行け」と言われ、親から守られている実感を得ることはない。学生時代の大河原氏は、「自分はなんのために生きているのか」という思いに陥ることもあったという。
「大人になってから気づいたのは、父はかなり風変わりな人だということです。母の親族の集まりに行って、そこで母のことを小馬鹿にして顰蹙を買ったり、レストランでも味にケチつけたり、人の気持ちへの共感性が欠落しているように思えました。
また、家の中はいつもモノだらけで、父の服が詰まったタンスや10年以上前の新聞や本、ビデオなどが山積みになって、通路も狭くなっていました。家族全員で片付けるようにお願いしても、『読むんだ』『捨てるな』の一点張り。片付けると怒られます。お風呂やトイレはまめに洗うし、入浴は毎日長時間入り、外出時の服装も清潔感がありました。にもかかわらず、とにかく自分の荷物を捨てようとしない。家の中も不衛生さはないものの、タンスの上まで父のモノが置いてあって、落ちてきそうで安らぎを感じられない家でした」
◆たまたま入った美術部が居場所になった
父親の言葉に傷つき、翻弄された子ども時代。本人に悪気がないため、いくら話しても周囲の気持ちは伝わらない。
「父の空気を読めていない発言も、悪意からくるものではないと知っているからこそ、複雑な思いでした。父の自己中心的に見える言動の受けとめ方もわからないし、自分の気持ちをわかってもらえない辛さに打ちひしがれる日々でした。小さい頃にこのような父を見ていたからこそ、『人の気持ちや痛みに寄り添えるひとでいたい』『人に優しい言葉をかけられる人でいたい』と強く思うようになりました」
父親から認められず、自己否定されたように感じ続けてきた大河原氏が絵画と出会ったのは、中学生の頃だ。
「中学では運動部に入りたくなくて、たまたま美術部に入部したんです。そこではじめて鉛筆デッサンを教わったら顧問の先生が、『うまいじゃないか!』とすごく褒めてくれました。両親からろくに褒められたこともない私は、初めて人から褒められたように感じて……自分はここに居ていいんだと思えた瞬間でした」
◆「芸術の才能がある」と自負していた父は…
絵の道を選んだ大河原氏は、母親の目にはどのように映ったのか。
「高校は美術科へ進学しました。他の生徒との展示会を見せたあと、母から『あなたは才能がない』と言われて。当時は自分でもそう思いました。目の前のものをデッサンしろと言われたら得意でしたが、自由に描くように言われても、本当に何を描いていいか自分でもわからなくて苦しかったんです。自分にしかできない表現はなんなのかと、いつも模索していました。美大に入学してからも思うように描けなくて、何度も絵をやめようかと考えました」
家族との関係性が画家としての姿勢や作風に与えた影響は大きい。
「父はいつも『自分には芸術の才能があるんだ。もっと時間があれば、退職したら素晴らしい作品が作れるんだ』と言いながら、リビングに置かれた3台ものテレビを見続けていました。そんな父の姿を見て育ったので、『何かをしなければ』と焦りを感じ、絵に打ち込む原動力にもなりました」
◆「描けなければ生きる価値はない」と思った
どう人と接したらいいのかもわからず、何が『普通』かもわからない――。一時期のそんな心理状態が、大河原氏を絵に向かわせた側面もある。
「人前ではちゃんと『普通』でいなければと気を使いすぎて疲れきってしまい、その影響で一人で絵を描くことにより打ち込んでいった面もあります。当時は『私には絵しかない。こんな自分は、せめて絵でも描けなければ生きる価値はないんだ』と思うくらいに追い込まれていました。
絵を描くようになってから思うのは、絵を認めてくれる人がいたから、心の闇に飲み込まれずに済んだということです。私の絵を見てくれる人たちの言葉に救われてきたから、描き続けることができ、画家になれました。感謝しかありません」
◆あの父がいたから「画家になれた」
理由が何であれ、生きづらさを感じている人は多い。大河原氏は、芸術に出会えたことによって、その生きづらさが少し緩和されたと話す。
「本当は、勉強だけでなく絵も頑張ったら、いつか父が兄ではなく自分を認めてくれるんじゃないかってどこかで期待していたんだと思います。ただ親から無条件に愛されたかったのに、それが得られなかったから、心の穴を埋めるために12歳からずっと絵を描き続けているんだとも思います。でも創作活動は、誰よりも心の傷を補填してくれました。絵があったから人に依存することもなく、ただ色やフォルムに夢中になれた。だから創作は、芸術は、素晴らしいと私は思っています」
芸術への向き合い方がみえてくると同時に、大河原氏はより深い自らの内面とも向きあうようになる。
「私が人間の絵を描くとき、顔でも体でも、どこかのパーツが必ず欠損しています。いったん全部顔や体を描いても、すべて描くと気持ちが落ち着かなくて消してしまうんです。きっとどこか、無意識に、何かが欠けた自分を絵に反映させているんだと思います。
どんなに努力しても、親からの無条件の承認を手に入れられなかったけれど、実はあの父がいたから、がんばり続けられた。あの父がいたから画家になれたんだと、思えるようになったんです。
自分も困難な環境で育ち、たくさん傷ついてきたからこそ、得られた力や学びもあったと今は思える。自分が傷ついた分だけその感情を周囲への優しさや共感へと変えようというのが私自身のテーマです。そこからつけた絵のタイトルを、『鼓膜に残る静寂を優しさに変えるすべについて』としています」
◆誰かの痛みに寄り添えるような絵が描きたい
闇の中にも光はきっとある、心の傷は力に変えられる。そう大河原氏は語る。
「だから、もしも孤独や心の傷を抱えている人がいるとしたら、『絵や創作は、あなたに寄り添ってくれるよ』と私は伝えたい。そして、誰かの痛みに寄り添えるような絵が描けたらーーそんな思いで今は絵を描いてます」
より大きな悲しみやわかりやすい不幸の前では、日常の些細な傷など、ないも同然で時間は過ぎる。心に微小な切り傷を抱えた人たちは、社会の鈍感さよりもまず自らの繊細さを嘆くだろう。弱者は、強者の理論で自転するこの世界から振り落とされずにいるだけで、精一杯だ。
どんな作品にも、芸術家たちが紡ぎ出す細く淡い神経の一本一本が通う。強くもなく、大きな声を発するわけでもない、不器用にしか生きられない仲間たちのために、今日も大河原氏の芸術は佇む。
<取材・文/黒島暁生>
【黒島暁生】
ライター、エッセイスト。可視化されにくいマイノリティに寄り添い、活字化することをライフワークとする。『潮』『サンデー毎日』『週刊金曜日』などでも執筆中。Twitter:@kuroshimaaki










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN