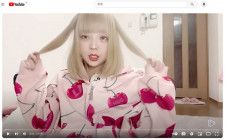◆娘ほども年の離れた女性に熱を上げる中年弱者男性
新宿タワマン刺殺事件の和久井学容疑者、そして頂き少女りりちゃんこと渡辺真衣被告に騙されたおぢ達。中年弱者男性にまつわる事件がクローズアップされています。なぜ娘ほども年の離れた女性に熱を上げてしまうのでしょうか?
フリーライターの西谷格氏は、そうした男性を「自分を客観視できない残念な人」と切り捨て、こう続けています。
<いい歳をした大人が、親子ほど歳の離れた人間を恋愛感情込みで推す感情は、本来ちょっと恥ずかしいと捉えるべきではなかろうか。>(「新宿タワマン刺殺、和久井学容疑者に「同情」などできない理由」ニューズウィーク日本版 2024年5月10日配信)
筆者も西谷氏と同意見です。ネット上では男性を中心に、ずる賢く金品をせびる女性への批判が多くあがっていますが、むしろそこで怪しいと感じるセンサーが働かない男性側のほうが深刻なのではないでしょうか。それこそが、西谷氏の言う客観性の欠如だからです。
◆問題の根源は「幼少期からの刷り込み」
しかしながら、これを中年男性だけの問題とすることにもためらいを感じます。なぜなら、男は物心ついたころから仕事で成功し、稼ぎ、いい女と付き合うことがゴールだと教えられてきているからです。
そこで、仕事も先が見えてきた、給料もこれ以上上がりそうもない。そんな自分にもいい女と付き合えそうなチャンスが転がり込んできたら、どうでしょう? その穴を埋めてなけなしのプライドを保とうと考えても全く不思議ではありません。
こうした罠にハマってしまう根源には、“モテ”があるのではないでしょうか。このモテなければという強迫観念が客観性を失わせ、年齢なりの余裕、良い意味での諦めを失わせてしまう。それが幼少期から刷り込まれていたとしたら病巣は根深いと言えるでしょう。
だから、これは中年の弱者男性に限らず、むしろ男性全般における問題なのですね。
◆女児向け本に感銘を受ける成人男性
そうした中で、2019年に発売された『自分をもっと好きになる【ハピかわ】かわいいのルール』(池田書店)が、いま20〜40代の男性に売れている(※)のは象徴的な出来事です。小学校高学年の女子に向けた本に、なぜ社会人男性が感銘を受けているのでしょうか?
※「なぜ? 女児向け本、社会人から大反響で10万部突破 編集者が明かす、意外なヒットの理由」Real Sound 2024年5月10日配信より
『ハピかわ』のコンセプトは明快です。他人との関係をどうやって気持ちよく作っていくか。そのための具体的な方法を細かく説明しているのです。たとえば、人の目を見て挨拶をする。猫背にならない。下品ではない笑顔の作り方。清潔感あるファッション。
こうした内容から伝わるのは、自分という人間は他人のために存在しているということ。そうした心配りが相手に伝わるような振る舞いこそが重要だと言っているのですね。そう、まさに客観性の話なのです。
モテるモテない以前に人としてわきまえておくべきことを教えてくれるのです。
◆日本に「男性向けの教科書」がない理由
筆者は『ハピかわ』を読んで、これは紳士の心得そのものではないかと思いました。アメリカでロングセラーの『HOW TO BE A GENTLEMAN』という本があります。2022年には改訂版の日本語訳『ドアはあけたらおさえましょう』(ジョン・ブリッジズ 訳酒井章文 サンマーク出版)が発売されました。コンセプトは全く『ハピかわ』と同じです。
<大事なのは、まわりの人が気兼ねなくいられるようにすること、嘘偽りなく、心からすてきな人物でいることだ。>(p.4)
<紳士の目標とは、自分のためではなく、友人や知人、そして世界全体のために、その場を暮らしやすくすることなのだ。>(p.267)
こうして言葉遣い、テーブルマナー、メールの返信の仕方、会釈の大切さなどを、あらゆるシチュエーションを想定して説いている本です。
なぜ日本にはこのような男性向けの教科書がないのか。あったにしても、なぜモテ要素が入ってきてしまうのか。
そこに闇を感じるのですね。
◆おろそかにされてきた男子教育
『ハピかわ』が20から40代の男性の支持を受けていることは好意的に報じられていますが、筆者は必ずしもそうは思いません。なぜなら、その事実自体におろそかにされてきた男子教育という空洞があるからです。
これからの社会、特に労働市場はどんどん女性が有利な環境になっていきます。これまでは男性上位だったテクノロジー、科学、数学などの分野でも女性の方が優れた業績を残す傾向にあるとの調査結果もあります。
これまでのように男が職業や経済活動において主導権を握る状況がますます成り立ちにくい世の中になりつつある。その中で、稼ぐ力、モテのみを男の価値とすることには無理が生じてきます。
◆社会全体として、新しい男性像を構築しなければならない
現代の男性が置かれた困難な状況を書いた本『Of Boys and Men: Why the Modern Male Is Struggling, Why It Matters, and What to Do about It』の著者、リチャード・リーヴスはこう書いています。
<男性に関する問題は、ほとんどはその男性自身の問題であると定義される。その男、あるいは男の子を一人ずつ矯正していかなければならない、と。こうした個別のアプローチは間違いなのだ。>
稼げる稼げない、モテるモテないではなく、社会全体としてもう一度新しい男性像を構築していかなければならないと言っているのです。
具体的に共有できるイメージがないから、何をもって男であるかが、誰もわからなくなってしまったのですね。
アン・ハサウェイ主演の映画『マイ・インターン』で、ハサウェイ演じるCEOが若手社員を前に現代の男性に対する不満をぶちまけるシーンがありました。
<いまじゃ誰も男のことを“男性”なんて呼ばないの。気づいてた? 女性は女の子から大人の女性に成長した。けど、男は年齢とともに幼稚になっていった。これは長い目で見たら大問題よ。>
小学校高学年の女子に向けた本から40代の男性が学ぶ構図も、これに当てはまるのかもしれません。
いずれにせよ、タワマン刺殺事件、『ハピかわ』現象からは、長らくほったらかしにされてきた男の教育という問題が浮かび上がってくるのです。
文/石黒隆之
【石黒隆之】
音楽批評の他、スポーツ、エンタメ、政治について執筆。『新潮』『ユリイカ』等に音楽評論を寄稿。『Number』等でスポーツ取材の経験もあり。Twitter: @TakayukiIshigu4










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN

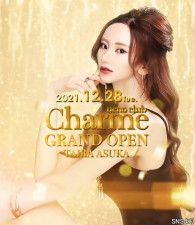
![男を騙す[頂き女子]最新事情】](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/nikkan_spa/s_nikkan_spa-2002345.jpg)