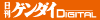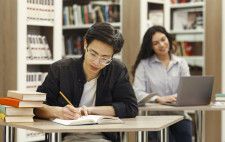新年度が始まって約2カ月、新しい仕事や部署での生活にも慣れてくる一方、気負ってスタートしたことによる疲れが出てくる時期かもしれない。しかし、この先、まとまった連休は、夏休みまでなく、疲れは残さずにその都度、しっかりと休むことが重要だ。実は、だれもが必ず行っている「休息」には、戦略が重要なことが分かってきた。
◇ ◇ ◇
年を重ねると、十分に睡眠を取ったつもりでも朝起きると何となくだるく疲れが取れていないことはよくある。睡眠不足や疲れを解消しようと、週末は昼まで寝て体力回復に努めたら、月曜からは再び睡眠不足に……。
アラフィフ記者にとっても耳が痛い話だ。疲れをため込んで休日を迎えることはしばしばで、休んでも体力が回復しないのは年のせいか、それとも体力が落ちたのか。いずれにせよ加齢に原因を求めるが、そうではないという。
「休息というと、ソファでのんびりしたり、ベッドで休んだりすることをイメージする人がほとんどだと思います。確かにアスリートや体を使って仕事をする人は、それが休息かもしれませんが、デスクワークの人にとっては適度に体を動かすことで理想的な休息が得られるのです。つまり、日常生活を静と動で分けると、どちらか一方はよくなく、休息とはそれぞれのバランスを取った上で体を休めること。そのためには、毎日の生活で休息に向けた戦略が欠かせないのです。アスリートや肉体労働の人も、休日に寝ているより散歩などで体を動かす方が血流が促され疲労物質が取り除かれやすい」
こう言うのは、米ハーバード大と仏ソルボンヌ大の両医学部で客員教授の根来秀行氏だ。医師として内科学や抗加齢医学、睡眠医学などを幅広く研究。その成果から、グローバル化やIT化の進展で24時間常に仕事や生活が可能な現代人には、戦略的な休息が不可欠だと説く。その根底にあるのが、体に備わる制御機能だという。
「究極の休息は、睡眠です。しかし、良質な睡眠を得るには、時計遺伝子によるサーカディアンリズムと、交感神経と副交感神経からなる自律神経のバランスをそれぞれ整えることが大切。この2つは人体にとって重要な仕組みで、毎日の生活の中に2つをうまく機能させるように適切なタイミングで適切なスイッチを押すことが戦略的な休息です。そうすると、正しいタイミングで疲弊した細胞に酸素と栄養素が供給され、ひいては良質な睡眠が得られるため、しっかりと体を休めることができる。そんな生活を毎日続けると、当然、パフォーマンスが上がります」
現代人は夜間も交感神経が優位で…
根来氏はそのエッセンスを「ハーバード&ソルボンヌ大学ドクターが教える! 超休息法」(徳間書店)にまとめている。詳細は著書に譲るが、戦略的な休息を取るためのポイントを教えてもらった。
重要な会議やプレゼンの前に心臓がドキドキして緊張するのは、交感神経が優位になるためだ。そうすると、心拍数が上がり、血管が収縮。血圧は上がる。脳や筋肉に血液が集まり、頭の回転や体の動きはよくなる。
一方、副交感神経が優位になると、心拍数が下がって血管が拡張するため血圧は下がる。脳や筋肉への血流は減り、心身ともにリラックスした状態だ。
これが一般的な自律神経の仕組みで、一方が優位になると、もう一方は控えめになり、ゼロになることはない。両者が常にうまくバランスを取っているのだが、現代人は夜間に交感神経が優位になりがちで体が休まらないという。
「本来、夜は副交感神経が優位になって、リラックス状態になり、安眠に結びつくのですが、スマホやPCなどの普及でベッドでスマホを見たりすると、本来優位になるべきタイミングに副交感神経が優位になりません。そういう人は、たとえ眠っていても交感神経が優位なため、睡眠時間は足りていても、朝だるい状態で目覚めスッキリしないのです。その影響で日中に優位になるはずの交感神経は十分上がらず、仕事のパフォーマンスは下がりやすい」
自律神経が働くタイミングが逆転しているわけだ。根来氏は自律神経の働きを測定するデバイスを使ってデータを集めた結果、逆転現象の人が少なくないことを見いだした。それを改善することが戦略的な休息のひとつで、そのカギは朝にあるという。
「自律神経のバランスを含めて、あらゆる生体機能にリズムがあります。そのリズムを体内時計でコントロールしているのが時計遺伝子で、周期は24時間11分と判明。起床して朝日を浴びると、親時計がリセットされ、そのシグナルが子時計を調節するスイッチになって、自律神経が整います。2つ目のスイッチが食事で、特に朝食を起床後1時間以内に取ることは子時計に直接働くスイッチとして重要です。つまり、朝日を浴びてから1時間以内の朝食が戦略的な休息の一歩なのです」
3つ目のスイッチが運動だ。通勤の行き帰りで歩く。エレベーターなどはやめて階段を上り、ランチはやや遠めの店まで歩く。そうやって歩数を稼ぎ、「1日1万歩が目安」だという。デスクワークで座りっぱなしの人は休憩にスクワットしたり、適度にトイレ休憩を挟んで歩いたりしてちょこまか運動することが子時計を通じて自律神経のバランスを整えるスイッチになる。
「ランチの前後はぜひ歩いてください。精神を安定させるセロトニンは正午ごろに分泌が高まります。しかも一定のリズムを刻む運動でより分泌が促進されるのでウオーキングは最適。夜間に分泌されて安眠をもたらすメラトニンは、そのセロトニンから合成されるので、ランチ前後の散歩はとても効果的です」
ランチで腹がふくれると眠くなる。その眠気は満腹感によるものではなく、実は時計遺伝子による生体リズムの影響だという。13時くらいになると体温が下がり、眠気が誘導されるそうだ。
「そこで15分の昼寝をすると、午後の仕事のパフォーマンスが上がって、夜の睡眠も妨げません」
デスクワークを終えてダルくても電車で自宅の最寄り駅まで直帰するのではなく、むしろ1駅か2駅手前で降りて歩く時間を設ける方がよい。終業後の19時くらいにかけて筋肉が刺激されると、成長ホルモンが分泌されるという。
「成長ホルモンが最も分泌されるのは、睡眠に入って最初の深い眠りのタイミングです。その働きは成長期を過ぎた成人の場合、全身の代謝や細胞の修復など。19時の分泌と睡眠時の分泌が相まって、体を効果的にメンテナンスすることができるのです」
鼻から腹式呼吸を。4秒吸って8秒で吐く
そんな戦略的な休息の積み重ねが、究極の休息である良質な睡眠に結びつく。前述した通りスマホは就寝3時間前から見ないようにすることが副交感神経を優位にする条件のひとつ。もうひとつは入浴で、夏でもシャワーではなく、38〜41度の湯船で体を温めよう。それ以上だと交感神経が刺激されてよくないという。
「朝型の場合、12時から7時までの7時間睡眠が理想です。そうすると12時から1時の間に、成長ホルモンの分泌がピークになるのです。その時間を外れると、分泌量は半分になってしまいます」
仕事や人付き合いなどで、3食や運動のタイミングがうまく合わない人もせめて食事はなるべくきちんと取る。運動が無理なら、腹式呼吸を取り入れよう。
「呼吸法は、無意識に働く自律神経に意識的に介入できる唯一の方法で、どこでも時間を選ばず実践できます」
常に鼻呼吸で、横隔膜が刺激されると、副交感神経が優位になり、緊張がほぐれる。仕事の合間や移動中にやろう。①まず鼻から息を吐く②腹を膨らませながら4秒かけて息を吸う③お腹をへこませながら8秒かけて息を吐く。吐くときは、肛門から恥骨、へそ、横隔膜へとチャックを閉めるように肛門周囲の筋肉と横隔膜を引き上げるイメージでゆっくりと吐くのがコツだそうだ。①〜③をリラックスするまで繰り返す。
なるべくリズムよく。この単純なことを肝に銘じて戦略的に休めば、疲れた中高年もきっと元気を取り戻せるに違いない。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN