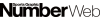やりたくないなら、それはそれで構わない
「娘にレスリングをやるように強制したことは一度もありません」
パリオリンピックで金メダルの期待がかかるレスリングの女子53kg級代表・藤波朱理(日本体育大)の父・藤波俊一さんはハッキリとそう言った。
俊一さんが切り盛りする三重県いなべ市のレスリング場「いなべクラブ」に朱理が出入りするようになったのは3歳の頃だった。7歳上の兄・勇飛がここでレスリングを始めていた関係で、まだ幼い朱理をひとりで家に置いておくことはできなかったからだ。
「ずっと道場で遊んでいるか、お母さんのヒザの上に乗って練習を見ている感じでした」
愛娘とはいえ、過度な期待を抱くことはなかった。レスリングや柔道の場合、経験者の親が息子や娘に夢を託すケースが多いが、藤波家はそうではなかったということだ。朱理も「わたしには全く期待していなかったと思いますよ」と振り返る。
俊一さんは「本人がやる気になるまで待とう」と長い目で見守った。レスリングをやりたいならやればいい。やりたくないなら、それはそれで構わない。そんなスタンスだった。1年後、朱理は「わたしもやる」とマットに上がり始めた。
それでも、俊一さんが舞い上がることはなかった。
「最初はレスリング半分、遊び半分。徐々にやる気が出てきた感じでした」
長男・勇飛に対しても、俊一さんは同じスタンスを貫いた。
「兄の場合は小1から始めたけど、試合が終わるたびに『(真剣に)やるのか、やらないのか。どうするんだ?』と確認していました」
のちに勇飛は世界選手権で銅メダルを獲得するなど将来を嘱望された存在だったが、オリンピックにはあと一歩届かなかった。俊一さんは「同じ兄弟でも性格が違う」と感じていた。
「妹の方がえらく負けず嫌いですね。子どものときにゲームをやっていても、勝つまでやりたがっていた」
その性格は朱理の成長を後押しした。俊一さんは「先に兄がどんどん強くなっていたこともいい刺激になっていたと思う」と推測する。
「自宅で家族4人でご飯を食べていたら、どうしても話題は全国大会で活躍するようになった兄が中心になるじゃないですか。そこで朱理は『お兄ちゃんに負けたくない』と思ったんじゃないですかね」
涙ながらに訴えた「もっと強くして」
本人のやる気に任せる一方で、俊一さんには「放っておくのも、もったいない」という葛藤もあった。
「いまでもそうですけど、指導者として、どういうふうに仕向けるかというのも大事な話。だからいかにその気にさせるか。いかにやりやすい環境を作るかという部分に苦労しましたね」
試合に出始めたときは負けることも珍しくなかったが、俊一さんは朱理が小学校低学年のときに放った台詞をハッキリと覚えている。
「お父さん、(心に)火がついた。頑張る」
その台詞に偽りはなかった。朱理は小学3年生時に全国少年少女選手権で初優勝。その後、6年生まで同選手権で4連覇を達成した。
小学校の高学年になると、俊一さんは「朱理は筋がいい」と思うようになった。
「毎日大人が練習しても、うまくなければタックルに入れない。でも、朱理は相手の足に触るのがうまかった」
しかし、中学に入学すると、朱理はふたたび負け始める。土をつけたのは、パリで日本代表として一緒に闘う櫻井つぐみ(57kg級)や元木咲良(62kg級)だ。また、現在は50kg級で活躍する伊藤海も、大きな壁として立ちはだかった。
いったい何が原因だったのか。
「反応は早かったけど、体力がなかった。そこで壁にぶち当たってしまった」
父の前で、娘は泣きながら呟いた。
「もっと強くして」
俊一は大きく頷いた。
「それからわたしも娘も本気になりました」
とはいえ、当時の俊一さんはいなべ総合学園高校の教壇に立ち、放課後は同校レスリング部の指導をする身で、高校生の指導のあとは朱理も所属していた「いなべクラブ」の指導が待っていた。時間はなんとか作り出すしかなかった。
「高校とクラブの合間の時間を使って練習するようになりました。練習(時間)以外の練習ですね」
指導者目線から、当時の朱理に足りないものは体力だということはわかっていたので、すぐに体力作りに取りかかった。
「腕をとられたら振り回され、それでテクニカルで負けてしまう。だからマット練習前に走らせて下半身を強化しました」
「シニアでも世界にいける」確信をつかんだ一戦
中学2年生になると、努力の成果は如実に現れる。2017年6月の敗戦を最後に、出る大会は全て優勝という破竹の快進撃を開始したのだ。さらに地元三重県で開催されたジュニアクイーンズカップで優勝を果たすと、俊一は「これはいけるかも」とヒザを叩いた。
「同じ階級には早生まれのひとつ上の学年の選手も含まれていた。そういう選手と競り合いながらも勝ち切ったので、自信が生まれました」
中学3年生になると、カデット(現U-15)のカテゴリーのアジア選手権や世界選手権にも出場し、いずれも優勝を果たした。
極めつきは翌年、地元いなべ総合学園高に進学して挑んだインターハイだった。学年がふたつ上の櫻井つぐみを撃破。中学時代の雪辱を果たすとともに、1年生にして高校日本一に輝いた。俊一さんはこのときの試合内容を克明に覚えている。
「最初は4点リードされたけど、タックルに3回連続で入って6点を奪って逃げ切った。あの一戦で朱理の実力に対しての自信は確信に変わりました。絶対にシニアでも世界にいける、と思いましたね」
そのために俊一さんは体力作りに加え、組手のスキルを磨くように指導した。
「結局、力はまだなかったので、タックルに入っても潰されてバックに回られての失点が多かった。逆にタックルに入られることはほとんどなかった」
一般的にレスリングといえば、タックルが最もイメージしやすいテクニックだろう。しかしタックルに入るためには、組手によって相手を崩す過程が必要になってくる。
「だから『手を使え』と、組手のことは口を酸っぱくして言っていましたね」
体力作りと組手を徹底して練習することで、朱理は高校生にしてシニアのレスリングでも頭角を現すようになっていく。長所と短所を知り尽くした父という名トレーナーがいたおかげで、藤波朱理はすくすくと成長していった。
<続く>
文=布施鋼治
photograph by Getty Images










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN