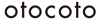最高にデラックスで最高にスペクタクルな映画。ヨルゴス・ランティモス監督とエマ・ストーンのコラボレーション『哀れなるものたち』は、両者の代表作として語り継がれていくはずだ。 アラスター・グレイ原作の本作は、ヨルゴス・ランティモスのフィルモグラフィーでもっともオーディエンスに開かれた作品であり最高傑作だ。圧倒的なプロダクションデザイン、演技、演出、カメラワーク。ここにはあらゆる情熱がほとんど狂気のレベルで注ぎ込まれている。
私見ではエマ・ストーンの出演作にハズレはない。製作会社「フルート・ツリー」を立ち上げ、最近ではジェシー・アイゼンバーグの初監督作品『僕らの世界が交わるまで』のプロデュースも担ったエマ・ストーン。『バービー』を製作した「ラッキー・チャップ エンターテインメント」のマーゴット・ロビーと共に、現在のアメリカ映画界におけるエマ・ストーンの行動から目が離せない。
フランケンガール・ゴーズ・トゥ・イエロー・ブリック・ロード
巨大な幼児、あるいは幼児の脳を埋め込まれたフランケンガール。ヨルゴス・ランティモスの『哀れなるものたち』は、絢爛なドレスを着た女性が飛び降り自殺を図ろうとするシーンから始まる。不吉なまでに眩しい輝きを放つ青いドレス。渦を巻くように荒れる波。橋の欄干から落ちた女性の遺体は、継ぎはぎだらけの痛ましい顔面を持つマッドサイエンティスト、通称“ゴッド”ことゴッドウィン・バクスター(ウィリアム・デフォー)によって拾われる。ゴッドウィンは女性のお腹の中にいた赤ん坊の脳と遺体の脳を取り換え、彼女の蘇生に成功する。20代の大人の身体を持った幼児ベラ・バクスター(エマ・ストーン)の誕生である。この映画はある女性の人生の終わりから始まるが、同時に新たな生命の誕生から始まっている。生きる機会、尊厳を奪われた母親の人生は、ベラによって生き直される。ベラの体には母親の生きた人生、傷が、タトゥーのように刻まれている。

鍵盤に両足を乗せピアノを弾く幼少期ベラのファーストシーン。幼少期のベラが言葉ではなく“音”で始まるのは象徴的だ。ゴッドウィンによって創造されたベラは、まだまともに言葉を話すことができない。この映画には大人の身体を持つベラの幼少期から大人になっていく過程が描かれている。ゴッドウィンの顔面と同じくアンティークの継ぎはぎで出来たような屋敷。ベラは言葉未満の言葉を放ちながら無邪気に物を破壊していく。ベラはまだ外の世界を知らない。世の中の秩序を知らない。ゴッドウィンによる教育は“監禁”と似ているが、ことはそう単純なものではない。ゴッドウィンには、ベラを自分の理想の女性として作り上げていくような身勝手な意思はないのだ。ゴッドウィンはベラの“父親”として彼女に寄り添い続ける。そこには惜しみないやさしさがあるが、当然矛盾もある。脳を入れ替えて人間を蘇生させるという実験そのものが、そもそも身勝手極まりない行為だからだ。自分の身体を使って実験をしてきたゴッドウィン。ゴッドウィンの継ぎはぎだらけの顔面は実験=傷の履歴、歴史なのだろう。それはベラの身体に刻まれた母親の傷と相似関係にある。そしてゴッドウィンは矛盾の中を生きていることに自覚的に見える。ベラを人々の欲望から遠ざけるために屋敷に閉じ込めることは、同時にゴッドウィンの支配下に留めることでもある。しかし支配はゴッドウィンの望むことではない。ここにヨルゴス・ランティモスのフィルモグラフィーを特徴づける“監禁”というテーマが、不穏な透かし絵のように浮かび上がってくる。

外界との接触を禁じられた子供たち、家族を描いた『籠の中の乙女』(2009)や、独身のままでいると動物に変えられてしまう『ロブスター』(2015)のホテル。ヨルゴス・ランティモスは“監禁”をテーマにした、アイロニカルとも黙示録的とも一概に形容できないユニークな作品を撮ってきた。ベラが世界を旅する『哀れなるものたち』は、ヨルゴス・ランティモスのどの映画よりも世界に、そして多くの観客に開かれている。むしろ例外的とも思えるほど楽しく、開放的だ。屋敷における破壊行為や、膣の中に果物を入れて遊ぶベラは、どこまでも無邪気さに溢れている(助手のマックスの戸惑いのリアクションを細かく捉えるズームイン/アウトを織り交ぜたカメラワークが実に素晴らしい!)。
ベラが自由主義を纏った男性ダンカン(マーク・ラファロ)と旅に出るまでの幼少期は、まさしくヨルゴス・ランティモスの“監禁”のテーマを踏襲している。出発前のファースト・エピソードがモノクロで撮られ、ベラが世界に色彩を発見していくというプロセスは、『オズの魔法使』(1939)と同じ構図である。いわばベラはエメラルドタウンに向かう黄色いレンガ路(イエロー・ブリック・ロード)を発見する。しかし屋敷を飛び出したベラは、“世界の良識”という名の新たな“監禁”を体験することになる。自分の欲望に正直なベラは、世界にとって悪夢、モンスターに他ならない。ダンカンはベラの無秩序さに惹かれ、外の世界の快楽を彼女に教えようとする。しかし新時代の自由人を気取っているダンカンは、結局のところ旧来の家父長的なコントロール・フリークであることを隠せない。無軌道だがスポンジのように物事を学んでいくベラの成長速度は、ダンカンにとって次第に手に負えないものになっていく。思い返せばダンカンに対するベラの優位には、初めから伏線があった。何度も快楽を望むベラと、何度も続けてセックスはできないと語るダンカン(ベラの“熱烈ジャンプ”という言葉が面白い)。男性なるものの敗北へ向けたプロローグ。素晴らしきベラの自由!そして、ああ、なんて憐れなダンカン!

色彩の発見、すべてを体験せよ
エマ・ストーンは『哀れなるものたち』のベラのことを、自分の演じた「もっとも偉大なキャラクター」だと語っている。本作には最高のエマ・ストーンが刻まれている。『ラ・ラ・ランド』(2016)やサタデー・ナイト・ライブ、アーケイド・ファイアーのウィル・バトラーのソロ楽曲のPVで、既にエマ・ストーンの高いダンスの技術はよく知られているが、それでも本作のダンスシーンには格別なものを感じずにはいられない。歩行のままならない幼児期のベラの動きは、すべて異形のダンスのようであり、身体の動きに対する意識が生まれる以前、脳が手足に指令を出すことを知る前の、真に原始的なダンスのように見える(まるでピナ・バウシュのダンスのようだ)。また本作は脚本の筋に沿って撮られた、いわゆる“順撮り”ではないという。驚くべきことに、エマ・ストーンは幼児期を撮影した次の週に大人に成長したベラを演じていたそうだ。ベラ・バクスターという破壊の象徴。ベラと同じように、エマ・ストーンの演技も時間という概念を破壊する。

ヨルゴス・ランティモスとエマ・ストーンにとって本作は『女王陛下のお気に入り』(2018)に続く2度目の長編コラボレーション作品だが、2人のコラボレーションはお互いの可能性を広げる理想的なコラボレーションといえる。ここにはお互いが新しい自分を発見していくような喜びがある。ヨルゴス・ランティモスにとっては、大きな資本の作品を撮ることで、ほとんど狂気的ともいえる豪華なプロダクションデザインの実現に成功している。アンティークの継ぎはぎで出来たような本作のエクストリームなインテリアのデザイン性にはレトロフューチャーの趣がある。そしてどこかパンキッシュですらある。その意味で『クルエラ』(2021)のエマ・ストーンのイメージと地続きでもある。幼児期のベラの衣装は、ヴィクトリア朝の突然変異なベビー服のようだ。

全体的な世界観としてはティム・ウォーカーのファッション写真に近い(プロダクションデザインを担うショナ・ヒースはティム・ウォーカーの長年のコラボレーター)。またフランシス・フォード・コッポラの『ドラキュラ』(1992)が撮影の参考にされたというエピソードも非常に興味深い。たしかに『ドラキュラ』の古典映画的技術と石岡瑛子による衣装のマリアージュは本作に通じるものがある。
ヨルゴス・ランティモスは大きなバジェットで何一つ作家の個性を失うことなく、むしろこれまで以上にクリエイションの自由を手に入れ、マッドで突然変異的な世界の構築に磨きをかけている。まるでこの映画を撮るために映画作家になったのではないかと錯覚させるほどに。すべてのシーンが飛び出す絵本のように瞳にめがけて飛び込んでくる。ド級のスペクタクルである。本作の真のマッドサイエンティストはゴッドウィンではなく、ヨルゴス・ランティモスその人なのだ。ベラと同じように私たち観客も色彩を“初めて”発見していく。ベラはすべてを体験する。

誰のものでもないベラ
世界をこの目で見てみたいというベラの欲望。ベラという世界地図。あるいはベラという身体的な日記。ロンドンから出発したベラ・バクスターの物語(原作はグラスゴーが舞台)は、リスボン、アレキサンドリア、パリへと進んでいく。かつて泣き止まない赤ん坊を殴りかかる勢いで威嚇していたベラはどんどん成長している。ダンカンの支配=監禁が及ばないほどの自我をいつの間にか纏っていく。ベラの成長に合わせて微調整されていくエマ・ストーンの演技、衣装の変化がとてもスリリングだ。
そして船は行く。ベラは船の旅で老婦人マーサ(ハンナ・シグラ)と連れの男性ハリー(ジェロッド・カーマイケル)と出会う。この船上のシーンがたまらなく好きだ。偉大なるハンナ・シグラの出演は、本作を撮るにあたって研究されたというライナー・ヴェルナー・ファスビンダーの映画へのオマージュでもあるのだろう。愉快で知的な老婦人マーサがベラに決定的な影響を与える。ベラは明らかにマーサに好感を持っている。ベラが初めて知った大人。それがマーサなのかもしれない。マーサとの出会いによってベラはいよいよ覚醒する。“世界の痛みを背負っている少年”とベラに形容される青年ハリーは、ベラに向かって忠告をする。良識は君を壊してしまうと。良識、あるいは秩序というこの世の“監禁”の枠に収まらないベラ。自我の目覚めたベラによって徐々に“去勢”されかけていたダンカンの威厳、権力はついに失墜する。どこまでも憐れなダンカン。マーク・ラファロの戯画的された演技には風刺画のような滑稽な魅力がある。



ベラの好奇心と向上心は留まらない。それはダンカンのような男性に欠けていることでもある。ベラにとって教養を身につけていく行為は、世界がどのようにできているか、その不平等な仕組みを知ることだ。したがってベラが教養に“監禁”されることはない。ベラの好奇心はむしろ彼女自身を解放していく。
再びヨルゴス・ランティモスの映画における“監禁”という主題が映画に滲みだす。世の中の秩序に従順な生き方を“監禁”された状態とするならば、“監禁”されていた方が生きやすいということになる。たとえそこに重大な欠陥があろうとも、世の中のルールに従っていれば身の安全は守られる。ベラは自らの身体を実験台として、この世界の欠陥、不平等を知り、疑問を日記のように身体に刻んでいく。この点で“親”であるゴッドウィンが自らの身体を実験台にしたのと相似の関係を結んでいる。そしてこのレール=実験や探求から降りた方が、ある意味で楽に生きていけることも知っている。しかしベラの内なる獣性は人間であること、理性に先立っている。その姿はさながら反逆の象徴、フェミニズム・パンクの闘士のようですらある。パリの娼館で出会った女主人(キャスリン・ハンター)は、かつてベラと同じような理想を抱いた闘士だったのだろう。彼女の全身はタトゥーで覆われている。それは彼女が負ってきた“傷”の歴史なのかもしれない。

『哀れなるものたち』は不当な扱いを受けた女性、母親の人生を生き直す、物語を正しい方向に書き直す娘の戦いの記録だ。ベラ・バクスターというヒロインは、フランケンガールでもマリオネットでもなく、新しい人間の姿なのかもしれない。絶対不服従の精神。私という存在をあなたに許してもらう筋合いなど初めからないのだ。本作の橋の欄干から身投げをするファーストシーンは、撮影の最終日に撮影されたという。エマ・ストーンはインタビューでこのときの感動を涙ながらに語っていた。死から始まった生。ヒロインの身体に刻まれた戦いの記録=傷。誰のものでもないベラの誕生はこの消えない傷口から始まったのだ。
文 / 宮代大嗣
作品情報 映画『哀れなるものたち』
映画『哀れなるものたち』
96回米アカデミー賞 作品賞 / 監督賞 / 主演女優賞等11部門ノミネート!!
自ら命を絶った不幸な若き女性ベラが、天才外科医ゴッドウィン・バクスターの手によって奇跡的に蘇生することから始まる。蘇ったベラは“世界を自分の目で見たい”という強い好奇心に導かれ、放蕩者の弁護士ダンカンの誘いに乗り、壮大な大陸横断の冒険の旅へ出ていく。やがて貪欲に世界を吸収していくベラは、平等と自由を知り、時代の偏見から解き放たれていくのだった。
監督:ヨルゴス・ランティモス
原作:アラスター・グレイ「哀れなるものたち」(早川書房)
出演:エマ・ストーン、マーク・ラファロ、ウィレム・デフォー、ラミー・ユセフ ほか
配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン
©2023 20th Century Studios. All Rights Reserved.
公開中
公式サイト searchlightpictures










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN