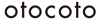『余命10年』や『新聞記者』『ヤクザと家族 The Family』で知られる藤井道人監督の国際共同プロジェクト『青春18×2 君へと続く道』が、台湾をはじめアジア各地での公開を経て5月3日に日本公開を迎える。日台合作映画となる本作は、18年前の台湾と現在の日本を舞台にしたラブストーリー。自らが立ち上げた会社の代表の座を解任されたジミー(シュー・グァンハン)が訪日し、初恋相手・日本人旅行者アミ(清原果耶)との18年前の想い出を回想しながら彼女の故郷を目指していく。チャン・チェンがエグゼクティブ・プロデューサーを務め、グァンハン、清原に加えて、ジョセフ・チャン、道枝駿佑、黒木華、松重豊、黒木瞳らが共演した。本稿では、本作のオフィシャルライターを務めたSYOが、その魅力を紹介する。
藤井道人監督との出会い
藤井道人監督と初めてお会いしたのは、2020年の2月だった。元々SNSを通して繋がりはあり、僕がA24関連のイベントに出演する際にゲスト登壇を相談し、快く引き受けて下さったのだ。第43回日本アカデミー賞で監督賞を含む6部門にノミネートを果たした直後で、周囲の状況が目まぐるしく変わっていく渦中だったかと思う。
その後、『青春18×2 君へと続く道』のプロデューサーでもある前田浩子氏が手掛け、清原果耶さんが主演した『宇宙でいちばんあかるい屋根』の連続インタビューを(コロナ初期のためオールリモートで)行い、7月に僕の独立を挟んで『ヤクザと家族 The Family』でマスコミ用プレスへの寄稿を賜り、短編映画プロジェクト「DIVOC-12」内の『名もなき一篇・アンナ』でオフィシャルライターとして現場に一部同行し――といった具合に一つずつ、かかわりが深くなってきた。最近では脚本の制作段階からお話を伺う機会も増え、そういった意味では作品を客観的に論ずることは僕にはできそうにもない。この文章を藤井さんが読んでいないことを(恥ずかしいので)切に願いながら書くと、自分の人生の恩人であり、ものづくりの先輩として常に刺激をいただいている。

脚本時点で感じた、新たなる“ピュアさ”
『青春18×2 君へと続く道』についてのお話を伺ったのは、脚本制作段階のことだった。記憶をたどると恐らく2022年末から2023年の正月あたりで、フィードバックのメモが手元に残っている(藤井さんは脚本を送ってくださり、意見を募るスタイルを取っているのだ)。劇中でジミーが語る「SLAM DUNK」のセリフについて、いちファンとしての重箱の隅をつつくようなリクエストを行ったのだが(その結果は本編で確認してほしい)、テキスト時点でもどこか懐かしく、エモーショナルで、それでいて台湾映画の“土”と“風”を感じさせる味わいが漂っていた。これはあくまで僕の感覚だが、『宇宙でいちばんあかるい屋根』『余命10年』に連なる系譜の作品であると同時に、よりピュアな部分に進もうとしている印象を受けたことを覚えている。
残念ながら撮影には同行できなかったものの、台湾での様子はちょいちょい伺っていて、有意義な時間になっているのだなと嬉しく思っていた。その後、編集段階で映像を見せてもらい、またフィードバックを行ったのだが――上記の感覚と共に、藤井監督の中で“痛み”の扱いが変わったような、さらなる進化を感じた。

台湾の夜市や夜空に浮かんでゆくランタン、バイクの2人乗りシーン、日本の雪景色や古き良き町並み等々の映像美は言うまでもなく素晴らしく、18歳と36歳を完璧に演じ分けたシュー・グァンハンさんの芝居に驚かされ、清原さんの“忘れられない人”ぶりにさらなる魅力を感じたりと、心を動かされたシーンは数多くある(ちなみに、劇中に登場する温かみある絵の数々は、藤井さんのお姉さん・よしだるみ氏によるものだ)。藤井作品の特徴として、ただ画が綺麗とかただ芝居がいいというものはなく、全ては人間を描くために機能している。お互いに「好き」という言葉を言い出せないジミーとアミの切ない心情が、美しい映像に乗るからこそ観る者の胸に響くのだ。そういった意味では風景描写こそ心情描写であり、そのポテンシャルを最大限生かせるスクリーンで観たら凄まじい感動が押し寄せてくることだろう。すでにアジア各国でヒットを記録しているのも納得で、台湾と日本の各地を辿る“旅映画”の側面はあれど、地域性や言語、文化を超えた「ただ、人を想う」という普遍的ながらどうしようもない人間の“魂”のようなものがクリティカルに届いてくる。

“痛み”をエレガントに描くことで、幅広い層に響く感動作に
そのうえで、先にちらりと述べた“痛み”について語ってゆきたい。藤井作品は、絶望から目を背けずに真摯に描くことで血の通った人間ドラマを構築してきた。単なるお涙頂戴ものにはしなかった『余命10年』然り、コロナ禍で傷ついた人々の心を代弁した『名もなき一篇・アンナ』然り。『ヴィレッジ』はその究極で、個人の絶望を表現として最大化・最深化してスクリーンに叩きつけることで、あれだけの濃度に到達できたのだと感じている。未だ多くのファンを抱える『青の帰り道』もシリアスな痛みとセットの青春物語だし、『デイアンドナイト』にも心痛な描写は多い。人間描写を大切にする以上、こうした“重さ”は付いて回るものだが、『パレード』を経て、本作で「一つ抜けた」ネクストステージに着地した感がある。

前作『パレード』は、「喪失」をテーマにした死者たちの物語であり、死によって隔たれる哀しみや凄惨ないじめシーンが登場する。が、そこだけでは終わらない。パレード(祝祭)というタイトルが示すように、たとえ暮らす場所が変わっても命は終わらないという“希望”が示され、死者の世界でも生者の世界でも「映画」というメディアの存在・映画制作という連帯がそれぞれの世界で生きる人々を孤立から救っていく(故人が生きた証が映画に記録される側面も)。 そして『青春18×2』では「再生」がテーマに据えられ、傷ついた人々を周囲の人間が、さらには作品自体が抱擁するような“優しさ”の温度が、より高くなっている。これまでが当事者の痛みをダイレクトに見せつつ観客に共振させるようなつくりだったとすれば、『青春18×2』ではそこを抑えたエレガントな魅せ方に変化しているのだ。それは表現として軟化したというわけではなく、より引いた目線で――例えるなら保護者のような、慈しみ守る存在として――等身大性は保ちながら、周辺視を行う“ゆとり”が感じられるのだ。
本作は藤井監督のおじいさまの出身地に合わせて、舞台を原作の台北から台南に変更したという。また藤井監督は撮影時にジミーと同じ36歳で、自身のパーソナリティを投影した部分は多いそう。ただ、そうしたエピソードを踏まえたうえで、本編を観ても私的で内にこもった作品にはまるでなっていない。むしろそうした要素を作品のクオリティ向上のピースとして客観的に処理できるような“抜け感”が、いまの藤井監督には漂っている。




“剛”に加え、“柔”の演出が光る
前述したピュアさにしても、リアルタイムな生々しさとしての無意識的なそれではなく、昔の手紙を開封して読み返すような意識的なものであり、とはいえ装置として利用もしていない。この絶妙な位置取りが、登場人物/観客の両獲りを成しえているようにも見受けられ、藤井作品史上おそらくもっとも世代的なレンジの広い結果につながったような気がしている。
深く心を打つ作品は、観る者が相応の覚悟を要するものでもある。『ヤクザと家族 The Family』や前述の『ヴィレッジ』などはまさにそうした作品で、心を持っていかれる力作の中で藤井監督の映像センスが目を喜ばせる効果を発揮していた。対して『青春18×2 君へと続く道』では、あえて描きすぎず、どこまでも優しさや慈愛に満ちた目線や映像に注力することで逆説的にジミーとアミの運命の切なさを掻き立て、観る者の感情を増幅させる。そして作り手の「絶望だけでは終わらせない」という意志を素直に出すことで、我々観客が安心して見届けることが叶うのだ。日本/台湾、さらには世界に響くスケールの物語と、作り手の覚醒が見事に融合している。

これまでの“剛”に加え、“柔”をも手に入れた藤井道人監督。すでにアナウンスされているだけでも3本以上の新作が控えており、表現者としての「第2章」がどこまでの高みに届くのか、楽しみに追いかけてゆきたい。
文 / SYO
作品情報 映画『青春18×2 君へと続く道』
映画『青春18×2 君へと続く道』
高校生・ジミーのバイト先に現れた日本から来た4つ年上のバックパッカー・アミ。ひと夏を同じ店で働き過ごすことになった2人だったが、次第にジミーはアミに淡い恋心を抱いていく。夜道をバイクで2人乗りしたり、映画を観に行ったり、2人の距離は縮まっていったが、突然、アミが日本に帰ることに。気持ちの整理がつかないジミーに、アミは“ひとつの約束”を提案する。時が経ち、あるきっかけで久々に実家を訪れたジミーは、日本に戻ったアミから18年前に届いたハガキを見つける。初恋の記憶がよみがえったジミーは、過去と向き合い、今を見つめるため、初めての日本での一人旅へ。アミとの思い出の曲を聞きながら列車に乗り、ジミーが向かうのは彼女の故郷。ジミーはアミとの再会を果たせるのか。
監督・脚本:藤井道人
原作:「青春18×2 日本慢車流浪記」
出演:シュー・グァンハン、清原果耶、ジョセフ・チャン、道枝駿佑、黒木華、松重豊、黒木瞳
配給:ハピネットファントム・スタジオ
©2024「青春 18×2」Film Partners
2024年5月3日(金) TOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー
公式サイト seishun18x2










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN