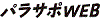ここ数年、競技場や児童施設など、大勢が集まる場所に配置され始めている“センサリールーム”。センサリールームはどのような空間で、何を目的としたものなのか、ご存知でしょうか。 今回は、公益財団法人日本サッカー協会(JFA)と共にセンサリールームプロジェクトに取り組む東京藝術大学のプログラム“DOOR”を取材。東京藝術大学学長でJFA社会貢献委員会の委員長でもある日比野克彦さんと、東京藝術大学DOOR特任助手の新妻葉子さんにお話を伺いました。
欧米では当たり前のセンサリールームを日本にも

これまで、特別なニーズを持つ子どもとその家族にとって、スポーツ観戦は身近なものではなかったかもしれません。特に、大きな騒音や強い光、人混みが苦手な自閉スペクトラム症や感覚過敏の症状がある子どもにとってスタジアムは、あまりにも刺激が多い場所です。
そんな特別なニーズを持つ子どもとその家族が安心してスタジアム内で観戦できる空間が、センサリールーム。明るすぎない照度と、大きな音や声などの大音量の遮音が施され、人混みや周囲の視線を避けた安心できる部屋になっています。
センサリールームとは、もともとは感覚を発達させたり落ち着かせたりするために設計された特別な部屋を指し、ヨーロッパを中心に約50年前から乳幼児や子どもたちのセラピーなどに用いられてきました。欧米でクワイエットスペース、センサリースペースとも呼ばれるタイプのセンサリールームが、最近日本でもスポーツ観戦などを中心に広がりを見せています。
「ヨーロッパでセンサリールームは当たり前の存在。イングランドだと、ほとんどのサッカーチームのスタジアムにセンサリールームが配置されていて、照明や大きな音、人混みなどが苦手な子どもでも安心してサッカーを観戦できるようになっている。それなら日本のスタジアムにもセンサリールームを取り入れて、誰ひとり取り残さないスポーツ観戦を目指そうということで、JFAと東京藝術大学DOORが連携して実施することになったんです」(日比野さん)

DOORとは、日比野氏がディレクターを務める東京藝術大学の履修証明プログラム“Diversity on the Arts Project”の通称。「アート×福祉」をテーマに「多様な人々が共生できる社会」を支える人材を育成する事業で、2021年からプログラム実践演習という科目の受講生と共にセンサリールームプロジェクトに取り組んでいます。
「初年度は、センサリールームについて学ぶことからスタートしました。試作や展示を経て、受講生から面白いアイデアがたくさん出たんですけど、それをプロダクトにする技術力が受講生たちには不足していたので、学内外のインストーラーなどプロの力を借りてセンサリールームを実装しました」(新妻さん)



受講生のアイデアが詰まった作品を2021年の第101回サッカー天皇杯の試合会場に配置し、それまでスタジアムに足を運ぶことができなかった子どもたちとご家族に、安心して試合を観戦できる環境を提供しました。このことを皮切りに、JFAが主催する多くの大会でDOORのセンサリールームが採用されています。
「日常の中で、センサリールームを利用したり目にしたりしているお子さんやご家族には、アートの視線で作られたセンサリールームをユニークだと感じてくださっているようです。時には、我々が想定していなかった使い方をするお子さんもいて、思い思いに楽しんでいただいてます」(新妻さん)
しかし、2022年に作品のレンタルを開始したところ、不思議なことが起こったと言います。
「借り手からすると、(前述の)『えらべルーム』のような大きな什器は輸送や組み立てが少々ハードなようでして、手書きの看板のレンタルが人気でした。日比野さんが文字を「分かち書き」という方法で描いた下絵に受講生たちが色を塗った看板で、わざわざレンタルするほどのものでもないような気がしたんですけど、皆さん『いやいや、これがよい。貸してください』とおっしゃって……。その中でも、スタジアムの入口でお客様をお待ちするときやお部屋まで案内するときに使える看板、お部屋に飾れる看板、トイレの案内看板などがよく借りられました」(新妻さん)

なぜこのシンプルな看板が人気なのか。分析した結果、センサリーな空間に大切なのは機能面だけでなく、「迎え入れられている」という感覚なのではないか、と感じたそう。
「貸出を始めた当初は、大きな作品もレンタルしてもらえるように送りやすいパッケージを作ろうとか足りない機能を付加していこうという話にもなったのですが、おそらくそういうことではないんだろうなと。それで、もう一度原点に帰ろうということで、2023年度は視点を変えてセンサリールームプロジェクトに取り組むことにしたんです」(新妻さん)
ただ刺激を遮断するのではなく、心地いい空間を作る

2023年度は、それまでの活動で見えてきた“迎え入れる気持ち”、“迎え入れる形”に着目してフィールドワークを実施。受講生一人ひとりが様々な場所を訪れ、「迎え入れられている」、「心地がいい」と感じることを徹底的に探し出した後に、それぞれが理想とする架空の町“センサリーシティ”のマップを作成したそう。
「DOORは、単なるセンサリールーム開発チームではないので、自分事としてどう活かしていくのか、どうやって福祉の世界に還元していけるのかというところがやっぱり大事。そこで今年は、社会全体、地球全体を心地のいい場所にすることを意識した授業を展開しました」(日比野さん)

「マップを作成した後、街全体を再現することは難しいけれども、感覚を再現することはできるということで、それぞれマップの中から要素を1つ選んで、自分が感じたセンサリーを1分の1で作ったんです。それがこれなんですよ」(新妻さん)

今回、DOORが出展した芸術未来研究場展(会期終了/東京藝術大学大学美術館、2023年11月10日〜26日)にお邪魔し、これまでのセンサリールームプロジェクトの内容と共に、2023年の受講生が制作したユニークな作品を体験。 一般的なセンサリールームは静かで落ち着く空間ですが、そこに心地いいと感じる道具や機能が加わることで、万が一、興奮をしてしまったり居心地が悪いと感じたりしたときでも、スムーズに情報を遮断して意識を逸らすことができることを実感しました。
スポーツ×アートが生み出すものとは?

ところで、現代の日本を代表する美術家の一人でもある日比野さんは、なぜJFA社会貢献委員会の委員長を務めているのでしょうか。アートとスポーツはまるで違うもののように感じますが、どちらも身体表現であり大差がないと日比野さんは語ります。
「足元にボールがあればサッカーになって、手元に筆があれば絵になるというだけで、アートもスポーツも根本は一緒で『表現』の一つ。道具を使わないマラソンランナーだって、東京マラソンに参加したり、自分が走る姿を家族や沿道の人に見てもらったりするのは自己表現だと思うんです。そういった捉え方で、美術館にあるアートだけでなく、スポーツや街の中にも『表現の場』を広げていけば、センサリーな空間が増えて居心地のいい地球になるんじゃないかと考えています」(日比野さん)
東京藝術大学でもダイバーシティ&インクルージョンな環境づくりを行うなど、多様な社会を目指して精力的に活動する日比野さん。多様な人々が集まる東京藝術大学には、元々、個性や文化が受け入れられやすいという特性があるそうで、「一人ひとりの違いを尊重するという考え方を基盤にすれば、多様性ある社会を築くこともそれほど難しくないはずです」ともおっしゃっていました。
それぞれが持つ個性や文化を尊重する東京藝術大学と、アートの力を借りて新しい応援スタイルを取り入れるJFA。センサリールームを通して見えてきたのは、多様な社会を実現しようとする両者の柔軟かつまっすぐな姿勢でした。スポーツ×アート。このような強力なタッグによって、今後、より自分に合ったスタイルでスポーツやスポーツ観戦を楽しめるようになるのではないでしょうか。
text by Uiko Kurihara(Parasapo Lab)
photo by Yoshio Yoshida
写真・資料提供:Diversity on the Arts Project










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN