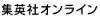人生100年時代といわれるが、実は人間の歯の耐久年数はその半分のおよそ50年。80歳になるまでに8本以上の歯を失うと、咀嚼能力が著しく低下する。できれば人生の最後まで自分の歯で食事を楽しみたい……。そんな人類の夢をかなえるべく、歯が生える薬が開発中であり、今秋から臨床実験がはじまるという。
この研究を長年、牽引している北野病院歯科口腔外科主任部長の高橋克氏に話を聞いた。
歯はそもそも「増える」特性を持っていた
――そもそも歯を生やすという発想のきっかけは何だったんですか?
高橋克(以下同) 実は1990年代に、歯は1つの遺伝子の変異で数が増えたり、減ったりすることがわかっていました。そのことを勉強しようと、歯科医師として働きながら、京都大学の大学院に進み分子生物学を、その後アメリカに留学して発生生物学を学びました。歯を新たに生やすというのは歯科医師としての夢です。
――その夢に向かって研究を続けるうちに、どんなことがわかってきましたか?
歯は生える数が決まっていて、全部で32本(親知らずを含む)あります。しかし、もともと数が足りない先天性無歯症という患者さんがいて、その割合は全体のおよそ1%くらいなんです。また、逆に歯が32本より多くあるのを過剰歯といって、やはり1%くらいいます。歯の数は決まっているはずなのに、増えたり、減ったりといった揺らぎ(余地)があるんです。
※先天性無歯症:生まれつき一部の歯が生えない症状
先ほど言いましたが、1つの遺伝子の変異で歯が1つ増えるということがわかっていたので、少なくとも歯が生えることに関しては、可能性があるんじゃないかと思ったんです。
――歯生え薬は、どのようにして歯を生やすのでしょうか?
私たちの歯は永久歯が抜けると生えてきません。これは、USAG-1というたんぱく質が歯の成長を抑制しているからなんです。
歯は芽さえあれば生えてきます。だから、このたんぱく質の機能をなくせば歯が生えてくるということになります。そこでこのたんぱく質をターゲットにして、歯を増やすということを思いついたのです。
がんの治療で、がん遺伝子によって発生するタンパク質を標的にして増殖しにくくする、分子標的治療というのがありますが、歯を生やすのも同じようにターゲットを絞ります。
マウスを使っての実験では、100%の成功率!
――これまでの実験ではどんな結果が出ていますか?
マウスを使って実験をしました。中和抗体を打ったら歯が生えてきたんですよ。しかも条件さえ整えば、100%生えるという結果を得られたのです。
マウスは、乳歯がない動物なので、先天性無歯症の子を妊娠している母親に抗体を打ちます。すると歯が生えてきたので、腰を抜かすほどビックリしました。また歯がない犬にも投与したら生えてきたのです。
でも犬の場合、残念ながらマウスとは違って100%成功にはなりませんでした。今のところ、動物実験では副作用は出ていません。ゆくゆくは、注射で直接人間に薬を打って、歯が生えてくるようになると思います。この薬が合う人、合わない人がいるかどうかもいずれわかってくるでしょう。
歯がなくなっても明るい未来が待っている
――ちなみにお値段はどのくらいになるのでしょうか?
費用は今のところインプラント3本分を想定していますが、全然決まっていません。ただ使用する抗体製剤はけっこう高価なので、当然費用も高くなってくるでしょう。
※インプラントは1本で、30~40万円程度かかる
――どんな患者に有効ですか?
無歯症の専門外来をやっているのですが、お子さん(先天性無歯症の患者)を連れたお母さんたちはいつも泣いています。子どもに歯がないことに対して、申し訳ないことをしたと自分を責めています。
歯が少ないことは子どもの成長、発達に影響が出ます。食事を摂る効率も悪くなります。また歯が少ないということで、すきっ歯になったり、見た目が悪くなります。子どもにとってはデリケートな問題なので、治験が始まって、どんどん薬を活用できるようになると、親子の悩みを解決する突破口になり得ます。
――大人の生活は大きく変わるでしょうか?
もちろんです。大人には28本の歯(親知らずをのぞく)があり、歯がその半数以下になると、ごはんのようなやわらかい食べ物も噛めなくなります。そうなることで口腔機能が衰えてしまい、結果、認知症になりやすく、転倒が増えることが研究からわかってきています。
このような疾患を防ぐために、入れ歯や新しい自歯で失った歯を補うことが大切です。抜けても新しい自歯の登場で、歯科治療の幅が格段に広がりますし、生涯自分の歯でモノを食べることができるようになります。それはとても爽快なことなはずです。
歯が改善されれば、自然と健康寿命も延びます。まずは2030年を目処に、先天性無歯症の患者さんに薬を届けたいと思います。
取材・文/集英社オンライン編集部










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN