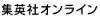球団による“搾取”から脱却し、選手たちの権利を獲得しようと、1984年に設立されたプロ野球選手会労組。その活動を、土台である法律の分野から支えたひとりの弁護士がいた。彼の心に火をつけたものとはなんだったのか。
中畑清と遠藤一彦が訪ねてきて…
中畑清がプロ野球選手会労組を結成する過程で、その活動を土台である法律の分野から支えてきたのが、弁護士の長嶋憲一である。しかし、長嶋は労働畑にいた法曹人ではなく、元々、上場企業の顧問として活動してきた人物であった。労働法については司法試験でも選択しなかったという。
そんな法律家が、日本で初めてのプロアスリートのためのユニオン設立に邁進していった背景はどのようなものだったのか。
「最初のきっかけは、広島カープの弁護士からの紹介だったんですよ」
オフィスでおもむろに口を開いた長嶋は、40年前の記憶を手繰り寄せた。
「広島市民球場で広島と巨人の試合をやっていたんだな。中畑とカープの山本浩二が試合後に流川で一緒に飲んでいたらしんだ。そこで中畑が浩二に組合について相談したところ、広島の弁護士につながった。で、そういう案件ならば、在京の法律家がいいだろうと、私に連絡がきたんです。
広島の弁護士から私には、『とにかくプロ野球というのは、選手の立場が弱いから、一度、中畑に会ってやって欲しい』と。中畑からもすぐに電話が来てね。『一両日中にお目にかかりたい』と言うんだ。それですぐに事務所にやって来た」
山本浩二は中畑清よりも7歳年上だが、チームを超えた情報と意志の共有がなされていた。そしてシーズン中であるにも関わらず、中畑は労を厭わずに銀座にある長嶋の事務所に現れた。大洋ホエールズ(当時)の主戦投手であった遠藤一彦も一緒だった。
長嶋はそこで、選手の置かれた環境と選手会の現状についてじっくりと説明を受ける。父親が読売新聞の記者であった長嶋は、その属性として巨人ファンではあったが、選手の置かれた状況については詳細を知る由もなく、統一契約書の問題も含めて初めて知ることばかりであった。
話を聞き終わった長嶋は思考をまとめると、中畑にこう告げた。
「選手会が社団法人のままじゃ仕方ないね。それは確かに労働組合を作ったほうがいい」
任意団体だった選手会は、柴田勲、松原誠、村田兆治ら幹部の尽力で1980年には法人としての設立認可を得ていた。しかし、好転するかと思われた組織化も社団法人のままではあくまでも非営利の法人団体に過ぎなかった。これでは機構側に対して、要望は出せても要求は出せない。
実際に中畑も「君たちが所属しているのは、そういう組織ではないよ」と、労務管理をしてきた海千山千の福祉委員会の担当者に言われて悔しい思いをしていた。
長嶋はこんなふうに感じていた。
「これまでプロ野球選手には自分は労働者だという意識がなかった。よく言われたのが、『個人事業主である選手は一国一城の主』で、誰かに使われているという気持ちを持ちえなかった。しかし、この辺でその観念を変える必要があるのではないか」
それゆえ労働組合という発想が生まれたのは必然であったが、実現のためのハードルは低くはない。職業野球の選手も労働組合法上における労働者であると主張し、組合の結成に至らせるには、それを東京都労働委員会に認めさせるための法的な理論構築と文書の作成が必要であった。
「労働者として認めさせるために、検討する時間を一週間くれないか」
長嶋はそう中畑と遠藤に告げた。巨人の5番打者と大洋のエースにもちろん異論はない。弁護士が本気になってくれたことは、大きな自信となった。
江川に「おい、卓」、中畑に「おい、清」
長嶋は今後、どういう手続きが必要なのか、探り始めた。労働法については門外漢であったが、情報を集めて検討に入ると、答えは早くに出た。
「調べれば調べるほどにプロ野球選手は労働者になれるとの考えに至った。それだけ厳しい労働条件だったんですよ」
調査をしていくうちに自然と義憤にも駆られていた。
「私がここで一肌脱ごうと思ったのは、要するに選手が背広組にバカにされていたんですよ。当時、球団の人が選手を何と呼んでいたか、分かりますか? 江川のことを『おい、卓』、中畑のことを、『おい、清』ですよ」
プレイヤーズファーストの精神からかけ離れたリスペクトの欠如。それが弁護士の心に火をつけた。
「それで一週間後に中畑と遠藤には、これから具体的に都労委に向けて動くけども、リーグやコミッショナーにはこのまま秘密裏で進めようと、念を押し合った。とにかく、事前に情報が洩れて潰されてはいけない、その一念だった」
長嶋は都労委と水面下で文書のやりとりを始めた。2回、3回と意見書を出すうちに都労委もまた理解を示した。返す刀で、自分が顧問をしている企業各社にも報告を入れた。
クライアントは名前を訊けば誰もが知っているナショナル企業ばかりである。労使の対立があれば、経営者側に就いていた弁護士が組合設立に尽力しているということが露見すれば、嫌な顔をされるかもしれない。しかし、それは杞憂だった。
意を決して「こういう事情でプロ野球の労組のために尽力しています」と話すと、どの会社もむしろおもしろがってくれた。「反対されるんじゃないかと予想していたんだけれど、その逆でした。いいじゃないか。やってみたらと」
ほとんどすべての会社が励ましの言葉を送ってくれた。「プロ野球は公的財産」という意識が企業役員たちの根底にあった。安堵しつつ、あらためて身が引き締まる思いだった。
資料をまとめ、都労委からの強い感触を得た長嶋は、選手会の総会に出席することを決意する。当事者となる12球団の全選手たちの前で直接、組合の説明をする機会を持つことは重要だった。会場のホテルに出向くと報道陣が群れを成していた。選手会としてはまだマスコミにも一切、洩らしてはならない議案であったが、弁護士の登場に気づいた記者が何人かいた。
「何で、先生が?」と聞かれて長嶋は焦ったが、ちょうどこの時期に在版の人気球団の某選手の女性問題が週刊誌を賑わしていた。「ああ、あの件ですか!アレですか!」記者はプライバシー保護の件だと勝手に早とちりしてくれた。
長嶋は法曹界の中でも自分がプロ野球労組のために動いていたことは、徹底して秘密にしていた。
「漏れたら潰される。別所、稲尾の時代がそうだった」
選手会総会が始まった。議事は粛々と進み、通常の議案が消化されると、いよいよ長嶋が紹介されて登壇となった。
外部の人間をシャットアウトしたバンケットホールの中で長嶋による労組結成についてのプレゼンテーションが始まると、選手たちは、初めて聞く組合という概念にとまどいを隠せなかった。野球に明け暮れて来たほとんどの選手たちは、労働者の権利確保について考える機会とは無縁の生活を過ごしてきたからだ。
社会人出身の選手もいたが、野球の技量を買われて入社した人間はそもそもが経営側に近い部署にとどめ置かれるケースがほとんどであった。
会場で選手からいくつか質問が上がって来た。集約すると、つまりところ「労働組合が出来るとしてそれは我々にとってどういうメリットがあるのですか?」というものだった。
長嶋は、選手が個人ではなく、組織として要求を出すことが担保されること、損害賠償などを球団ではなく、コミッショナーに出せるということなどを詳しく話した。その具体的な要求の中に選手たちが渇望する練習設備の充実や拘束時間の緩和、さらにはその先の一軍最低保障やFA権や年金があった。
この説明会は球団の分布に合わせて東(東京)と西(大阪)で二回に分けて行われ、内容が周知されるにつれて大きな支持が大きく広がっていった。その度に長嶋は選手たちへのかん口令を徹底させた。
「漏れたら潰される。別所、稲尾の時代がそうだったのだから」
すべての選手たちは見事にこの約束を守り切り、誰ひとりとして口外しなかった。
1985年、阪神タイガースが18年ぶりのリーグ優勝を決めてから16日後。9月30日に長嶋は地労委に組合資格審査請求を提出する。破竹の勢いのタイガースが続けて日本一になってから3日後の11月5日に想定通り、組合として認定された。
プロ野球に先駆けてプロの音楽家たちが作った日本音楽家ユニオンが2年前に認められていたことも大きかった。すべては秘密裏に行われ、その上で長嶋は登記を急いだ。
「法人登記してしまえば既成事実になるし、球団が潰そうとしてももう対等の立場で戦えるわけだから、選手にかん口令を敷いたまま急ぎましたよ」
そして11月19日にプロ野球選手会労組は法人登記される。これは間一髪とも言えた。都労委の中立の立場にある人間が、登記を終えた直後にマスコミに組合結成の動きをリークしてしまったのである。
「ナカハタさんじゃなくて、アカハタさんだね」
「それで野球界は大騒ぎになったんです。ただ、登記は終わっていたんで、文句を言われる筋合いはないと中畑と突っ走ることができました。機構や球団は、登記が無効だと騒ぐことも考えたようですが、都労委も認めているということであきらめたわけです」
プロスポーツ界における革新的な幕開けについて当時のメディアの扱いについて聞くと、小さく首を振った。
「あの頃にこの動きをしっかりと捉えたと思える記事を出したのは、東京新聞くらいだったね。あそこは一面で出したしね。あとの媒体は茶化したり、本質をずらしたり、それほどではなかった」
長嶋が電車に乗っていると、隣に座った学生が写真週刊誌『FRIDAY』を読んでいた。見開きで自分の顔が載っているのを見て「それ、俺だよ」と思わず声をかけそうになった。
当時の社会的な現象として、春闘を定着させた労働運動家の太田薫が総評(日本労働組合総評議会)の組合員を後楽園球場へ引き連れてきて中畑を応援した。これには「ナカハタさんじゃなくて、アカハタさんだね」と揶揄する評論家もいた。
また、選手会労組の初期稼働も決して順風満帆ではなかった。ヤクルトが1986年の開幕直前に脱退を宣言している。
「あれもね。親会社からの露骨な圧力だった。もうそれはわかっていたけど、中畑は黙って耐えていた。今でも覚えているけど、ヤクルトの選手が脱退の声明文を読み上げるときに『選手とチームは“おもてうら”一体です』と言ったんだ(笑)。要は表裏(ひょうり)一体と読めなかったわけだけど、自分たちの言葉ではなく言わされていたから、そんなことが起こったわけだ」
当時、ヤクルトの尾花高夫が中畑に「3か月待ってください、すぐに復帰しますので」と言ったという話を向けると、長嶋は驚いた顔でこう言った。
「それは知らなかったな。ただ私が感銘を受けたのは、このときは広沢克己がすごく頑張ってくれた。ヤクルトにおける動きは広沢が組合の意義を十分に理解して奔走したことが大きいんですよ」
後にヤクルトから巨人、阪神を渡り歩いた主砲・広沢は何を思って動いたのか。
文/木村元彦










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN