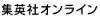米アカデミー賞で作品賞を含む7冠に輝いたクリストファー・ノーラン監督の『オッペンハイマー』は、日本では原爆をめぐる内容ということで公開が遅れ、ようやく3月29日に公開される。本作の見どころ、「難解だ」という感想がすでに多くあがっている理由を解説する。
美しければ美しいほど「野蛮」
私は、哲学者テオドール・アドルノの「アウシュヴィッツ以後、詩を書くことは野蛮である」という言葉を想起しながら、この映画を鑑賞せずにはいられなかった。アドルノの言葉が意味したのは、アウシュヴィッツだけではなく、ホロコースト一般とそれに類する大虐殺の後に詩(美しいもの)を作り出し、鑑賞することはホロコーストの悲惨を生み出した文化の肯定でしかなく、野蛮な行為だということである。
広島と長崎への原爆投下についても同じことが言える。そしてとりわけ、映画を一編の交響曲のように、あるいは詩のように緊密な美しさに仕上げることに長けたノーラン監督がロバート・オッペンハイマーについての伝記映画を作ったのだから、この映画は完成度が高ければ高いほど、美しければ美しいほど、「野蛮」であることは避けられない。
それでもなお、私はこの映画が公開されたことを歓迎したい。というのは、私たちの世界にはそのような野蛮さが確かに存在するし、そこから(公開しないことによって)目を逸らしてはならないと思うからだ。
本記事では内容(といってもオッペンハイマーの伝記がベースになっているので、ほぼ周知の内容であるが)にはなるべく踏み込まずにこの映画の見方を提示しつつ、それに関連して少々深く、すでに批判のある「広島・長崎の不在」について考えてみたい。
本作を少しだけ難解にしているのは、時系列通りに展開しない構成である。終戦後の1954年、マッカーシズム(赤狩り)の猛威の中で、ソ連のスパイ疑惑で公聴会にかけられるオッペンハイマーと、大学生時代から長じてロスアラモスでの原爆開発、そしてプリンストン高等研究所の所長となったオッペンハイマーの姿が、パッチワークのように交互に描かれていく。
そのこと自体は、オッペンハイマーの大まかな伝記と戦前から戦後の世界史・アメリカ史のあらましを知っていれば、本作を理解する上でそれほど問題とはならない。
白黒とカラーが意味するもの
観客を戸惑わせるかもしれないのは、上記の物語が大部分はカラーで描かれるのに、一部は白黒で描かれることである。白黒で描かれるのは主に、上院での公聴会、そしてホテルでの原子力委員会の会議のシーンなどである。
オッペンハイマーのスパイ嫌疑の調査の場面が白黒で、それ以前の、ロスアラモスでのトリニティ実験を頂点とする時系列に沿った伝記部分がカラー、つまり戦前・戦中がカラーで戦後が白黒なのかと思いきや、そうではない。戦後であるはずの原子力委員会での尋問の場面はカラーなのだ。
通常の映画表現では、しばしば白黒は回想シーンに使われる。その直感に逆らっているだけでなく、戦前・戦中=カラー、戦後=白黒というわけでもないのだ。これが混乱のもとになるかもしれない。
簡潔な答えは、オッペンハイマーの視点がカラーで描かれ、ロバート・ダウニー・Jr.演じる、アメリカ原子力委員会の委員長ルイス・ストローズが中心的に描かれる場面が白黒で描かれているというものである。より正確には、ストローズの「視点」というわけではなく、オッペンハイマーの「主観の外側」と言うべきだろう。
実際、すでに出版された台本を読んでみると、白黒の場面は3人称で書かれているのだが、カラーの場面のト書きはなんと「私」を主語に1人称で書かれている。
これは映画の台本としてはかなり異例である。例えばこんな感じである。尋問者の「どうしてアメリカを離れたのか」という質問に続く台本は以下のようになっている。(なお、私は本作の日本語字幕版は未見であり、ここでも英語の脚本から独自に翻訳する)
室内。2022室、原子力委員会──日中(カラー)
部屋は小さくみすぼらしい。私は驚いて陳述原稿から目を上げて私の告発者のロジャー・ロブを見る。それから3人の委員(グレイ、エヴァンズ、モーガン)の方を向く。
オッペンハイマー:新しい物理学を学びたかったんです。
カラーの場面のト書きはこのように、「私」「私の」という1人称で書かれている。カラーと白黒のこのような利用は、ノーラン監督の出世作『メメント』を彷彿させるものであるが、その狙いはなんなのだろうか。
ひとつには、自らが開発した原爆が広島と長崎を地獄へと突き落としたことを知り、戦後に水爆の開発と核軍拡に反対するようになったオッペンハイマーと、原子力の利用を推進しようとするストローズとの対決を強調するためでもあるし、オッペンハイマーという個人の内的な物語と、外側の歴史とを結びつけて表現するためでもあるだろう。
この手法は確実に、この映画に独特な感触を与えている。この映画は通常の意味での群像劇ではまったくない。オッペンハイマーの主観に奇妙に閉じこもりつつ、「(主観的な)現実」と「(客観的な)歴史」が完全に統合されないままに、劇が進んでいく感覚を覚える。
広島・長崎の「隠蔽」と1人称
この手法と、原爆の問題は深い関係にある。すでに報道されている通り、『オッペンハイマー』は広島と長崎の被害の様子を直接に描くことはない。
これについてノーラン監督は「この作品はあくまでオッペンハイマーの主観に寄り添う1人称的なものであり、彼は広島と長崎への原爆投下をラジオで知っただけであるゆえに、それは描かない」という趣旨の発言をしているのだ。
この映画の大部分(カラーの部分)が1人称的なものであることを認めるとすれば、それはこの映画の道徳的な正当性を下支えしているということになるだろう。
つまり、この映画は、原爆を開発したことへの悔恨の映画であり、その限りにおいて、核兵器のもたらす悲惨を訴える映画である──オッペンハイマーの心理劇としての側面を強調することは、この主張を下支えするのである。
この主張は、私たちの直感に反する帰結をもたらす。つまり、この映画は1人称的になり、それを白黒の場面のストローズの原子力推進と対置することによってこそ、オッペンハイマーの「悔恨」を真に迫ったものとして表現し、核兵器の危険を訴える映画になっている。
オッペンハイマーの主観から踏み出さないこと=広島と長崎を描かないことによってこそ平和主義の映画となるというパラドックスがここに生じるのだ。
だが、この図式は結局のところ、成立していないと考えるべきである。私はここまで、この映画(のカラー部分)が1人称的なものであるという前提で論じてきた。それがノーラン監督のとりあえずの意図だった。
だが、映画は原理的に、例えば小説がそうなれるような意味で1人称になることはできない。もちろん部分的には、例えばカメラを人物の視点に固定するとか、1人称でのナレーションを入れるといった手法で1人称的にすることはできる(が、『オッペンハイマー』はこのどちらも行なってはいない)。
カメラの目が登場人物と世界をとらえた瞬間に、それは1人称的なものをすでに離れていると見るべきなのだ。
実際に、ト書きが1人称で書かれた『オッペンハイマー』の脚本から受ける印象と、できあがった映画から受ける印象は別物である。
先述のように、この映画には脚本の1人称に由来すると思しき奇妙な手触りがある。だがそれは、純然たる1人称とはもはや別物なのだ。だから、本当は、広島と長崎の惨状を映したとしても、ノーランが「1人称的」だと考えるこの映画の特質に傷はつかなかったはずだ。
広島と長崎を描かなかったことには、1人称的にすることとは別の動機があったと疑わざるを得ない。
つまるところ、この映画はオッペンハイマーの主観と、世界で起こったことを切り分けて描いた上で橋渡しすることに失敗している。だがカラーと白黒といった形式だけは主観と客観の両方を描きうると主張しており、それが観客の感性にすっと落ちてくることはない。
それは、本記事で行なってきたように、悟性(理性)で分析しないと了解できないものである。そのギャップこそが、私が「奇妙な手触り」と繰り返しているものの正体だ。この形式と、受容する側の感性が乖離することは、映画『TENET テネット』の時間の逆行シーンでも起きている。
ただし、私たちはみな、多かれ少なかれそのようなギャップの中を生きているのかもしれない。だとすればそれを易々と橋渡ししなかったのは、ノーラン監督のせめてもの「誠実」と言えるのかもしれない。
残る問題は、それが広島と長崎の「抹消」に帰結する──そしてそこには結局美学的な必然性はないかもしれない──という事実を、私たちがどう受けとめるかなのである。
文/河野真太郎
オッペンハイマー
監督・脚本・製作:クリストファー・ノーラン
製作:エマ・トーマス、チャールズ・ローヴェン
出演:キリアン・マーフィー、エミリー・ブラント、マット・デイモン、ロバート・ダウニー・Jr.、フローレンス・ピュー、ジョシュ・ハートネット、ケイシー・アフレック、ラミ・マレック、ケネス・ブラナー
原作:カイ・バード、マーティン・J・シャーウィン 「オッペンハイマー」(2006年ピュリッツァー賞受賞/ハヤカワ文庫)/アメリカ
2023年/アメリカ 配給:ビターズ・エンド ユニバーサル映画 R15
© Universal Pictures. All Rights Reserved.
公式サイト:oppenheimermovie.jp
IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation.
Dolby Cinema is a registered trademark of Dolby Laboratories.










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN