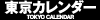公務員は安定してるけど、平凡な毎日にうんざり。刺激を求める28歳独身女がとった行動とは…
キラキラした生活を追い求めて東京で奮闘する女は、ときに疲れ切ってしまうこともある。
すべてから離れてリセットしたいとき。そんな1人の空白時間を、あなたはどう過ごす?
▶前回:「35歳を過ぎてまだ独身だけど、私は大丈夫」女が自信満々にそう思える意外な理由は…?
Vol.20 東京から直線の飛行距離約800km、退屈な毎日が愛おしく感じられる「とっておき」のご褒美旅行
金曜日18時、西東京―。
― うそ、もうこんな時間っ?そろそろ行かなきゃ!
定時に仕事を終えた里美は、ブラブラと散策していた駅ビルをあとにする。
急いで改札を抜けると、JR南武線快速から東急東横線急行に乗り継ぎ、1時間かけてようやく中目黒に到着した。
この日は、大学時代からの友達・真奈と秋穂と3人で、月1恒例の食事会をすることになっている。
― えっと、お店は…『クルン・サイアム』ね。
里美は、地図アプリを立ち上げようとスマホを手に取る。すると、LINEが立て続けに送られてきた。
真奈:『ごめーん!30分遅れるっ』
秋穂:『私も!真奈と同じくらいになりそう。ごめん里美、先に飲んでて』
そういえば、デザイン事務所で働く真奈も、フリーライターの秋穂も今週は仕事が立て込んでいると言っていた。
里美:『OK!じゃあお言葉に甘えて♡』
約束の19時。
「すみませ〜ん!シンハービールお願いします」
1人先に店に着いた里美は、グループLINEに返信を済ませてビールを注文する。すっきりとした飲み口にゴクゴク喉を鳴らしていると、グラスの半分が一気に空になった。
「はぁ〜、真奈も秋穂も仕事大変そう。でも…いいなぁ」
ソム・タムにエビのさつま揚げ―。食欲をそそるタイ料理のメニューを横目に、里美の口からは小さなため息が漏れる。
自分は彼女たちのように、仕事にやりがいや楽しさを感じたことがあっただろうか。大きな不満こそないものの、達成感や感動もない。
よくいえば平穏な毎日に、里美は自分がどんどん退屈な人間になっていくように感じていた―。
北崎里美、28歳。
中央大学を出てからは、東京の西側・いわゆる西東京エリアにある市役所で公務員として働いている。
両親や兄もそれぞれに行政系・福祉系の公務員として働く、まさに公務員家庭のサラブレッドだ。
そのうえ職場の市役所までは、実家からバスで20分と超近距離。あまりにも狭い行動範囲に危機感を覚え、一人暮らしを始めたのはちょうど2年前。
だけどその小さな変化に高揚したのも、わずか数ヶ月だけだった。
◆
19時30分―。
里美が物思いにふけっていると、真奈と秋穂がそろってやってきた。
「お待たせ、里美!ごめんね」
「シンハービール、私たちも頼もう?はい、お疲れさま〜!」
グラスを合わせて乾杯すると、2人はキンキンに冷えたビールにギュッと目を細める。
「今週めちゃくちゃ疲れたよ〜!今やってる広告デザインの仕事なんだけど、納品直前に修正が入っちゃって」
「私も!明日締切りのコラムがあるんだけど、重めの取材記事を書き終えたばっかりで頭パンパン。全然書けてないんだから。里美はどう?」
「え、あぁ…私?」
彼女たちから仕事の話題を振られると、里美はいつも口ごもってしまう。
「私なんて毎日定時で帰ってるよ。何もなさすぎるのが悩み…かな。2人みたいなクリエイティブな仕事って、本当に憧れちゃう」
自慢とも自虐ともつかない里美の返事に、すかさずフォローが入る。
「でも、それがいいんじゃない?ON・OFFの切り替えもしやすいし」
「そうだよ〜。何だかんだ言って、安定してるのが1番だよね」
仕事で羨ましがられるのは、週2日の決まった休日と定時就業。それと、福利厚生の厚さくらいだ。6年間働いてきて、ほかのことが話題にあがったためしがない。
とはいえ、そのおかげで休日の予定を立てやすかったり、自分の時間を十分に持てたりするのは里美自身もありがたく思っている。
これ以上何かを望むのは、贅沢なのかもしれない。けれど、安定や自由だけでは満たされない心のすき間があるのだ。
「う〜ん、だけど毎日退屈すぎるよ。何だろうなぁ、“わかりやすい変化”とか“非日常”みたいなものが必要なのっ」
お酒があまり強くない里美は、グラス3杯のビールでほろ酔いだ。本音をポロリとこぼしたかと思えば、語気まで強くなる。
「じゃあさ、思い切って1人旅とかしてみたら?里美、前の彼氏と別れてから全然旅行とかしてないよね?」
「そうそう、リゾートに行くとか?ラグジュアリーホテルでのんびりするとか。…そうだ!私がこの前取材で行ったホテルなんだけどね―」
秋穂がスマホの画面をスワイプすると、ハッと息をのむ1枚の写真が目に留まった。
真っ先に飛び込んできたのは、インフィニティプールの透き通る青。その先に臨むのは、立ちのぼる湯けむりと濃い緑の山々。
西東京にも自然は多いが、まったくの別物だ。見たことのない景色に、里美の視線はくぎ付けになる。
「ねぇ、秋穂!これどこ?」
「ここ、めちゃくちゃよかったよ〜!待ってね、今ホテルと私が書いた記事のリンク送るから」
秋穂が送ってきたのは、別府にあるラグジュアリーホテルのURLだった。
― 『ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ』…、聞いたことあるかも。
一緒に送られてきた記事にもザッと目を通す。ところが、秋穂がどれだけ素晴らしい時間を過ごしたのか、想像してみても今の里美には到底わかり得ないのだった。
規則正しく並ぶパソコンデスクや、カウンター越しに見る待合スペース。市役所には、何とも形容しがたい無機質さがある。そんな場所で長く働いてきたからか、ここ最近は自分の感性がひどく乏しくなってきているように思う。
前は「うそでしょ?」と声をあげていたニュースにも、今は「へぇ〜」くらいの温度感なのだ。
里美はそんな自分に気づき、密かに焦っていた。
「行ってみたい…な」
ふと気がつくと、指先は“宿泊予約”の文字をタップしていた。
1ヶ月後―。
里美は、羽田発のフライトに搭乗していた。
飛行時間は1時間40分。東京から直線の飛行距離で約800kmほど離れた大分県に到着する。
2泊3日分の荷物が詰まったスーツケースをピックアップ。空港バスとホテルのシャトルバスに乗り継ぐと、ぐんぐん森の中へ進んでいく。
― あっ、これって硫黄の香り…。
窓の外には、湯けむりが立ちのぼる温泉の数々。いつもの行動範囲から物理的に離れていくと、その分だけ心も日常から切り離されていく気がする。
バスは、ひたすら小高い丘の上へと走る。しばらくすると、秋穂が見せてくれた写真と同じ高台の好立地に位置するホテルに到着した。予約した「クラシックルーム」は、3日の滞在で約14万円。かなり奮発した。
それだけのことはあって、客室の全面ガラス窓からは自然豊かな山々や別府市内を望む絶景。テラスには、景色を楽しみながらくつろげるソファとテーブルまである。
ベッドのうしろ側の格子建具越しには、ツインシンクと大理石のバスルームだ。
「え、待って!思ってたよりも…100倍素敵っ」
里美は、普段の“はぁ”ではなく、“ほぅ”に近い感嘆のため息を漏らしながら、客室内をグルッと見渡した。時計は16時をまわったところだ。夕食まではまだ時間がある。
館内にある『ザ・ラウンジ』でソイラテを飲み一息つくと、ラグジュアリーなホテルにふさわしい『FOXEY』のティアードドレスに着替えて、入念にメイクを直した。
18時―。
予約していたレストラン『エレメンツ』へ向かう。
秋穂から、コース料理のメインまではレストラン内で。デザートはテラス席で食べるのがおすすめと聞き、スタッフに申し出ると快くOKしてもらえてホッとする。
まずは、食前酒にノンアルコールのシャルドネ スパークリング。ぶどうの香りと甘み、強めの炭酸に食欲が刺激される。
次に運ばれてきた「四季の恵みPLATE」は、地元の食材がふんだんに使われた前菜だ。
ライスペーパーで巻かれたアスパラガスと、そこに透けて見えるエディブルフラワーにキュンとときめく。ナイフを入れて口に運ぶと、新鮮でみずみずしい野菜本来の味が広がった。
メインは鰆。皮目はパリッと焼かれ、身はほくほくだ。
「う〜ん!美味しいっ」
淡白ながら上品な甘味も感じられて、ノンアルコールの白ワインとよく合う。里美は、心のなかで何度も大きく頭を縦に振り、小さなガッツポーズまでした。
すっかり浮かれた気持ちで、最後のデザートを前にテラス席へと移動する。ちょうど日が落ちたあとだった。別府湾と市内の夜景が、キラキラと里美の目の前に広がる。ソッと吹き抜ける風が、髪を優しくなびかせた。
抹茶のティラミスにフォークを滑らせる。なかからは、とろりと濃い抹茶のソース。舌触りがよくて、ほろ苦い。その余韻がいつまでも里美のなかに残った。
― そうだ、写真を撮って真奈と秋穂に送ろう。
そこで、里美はホテルにチェックインしてから一度もスマホに触れていなかったことに気づいたのだった。
― 私って、こんな過ごし方ができたんだ…。
自然と頬が緩む。
日々の退屈さに飽き飽きしていた里美は、SNSやネットニュースから新しい情報を得ることに躍起になっていた。
けれど、そこにはただ無作為に選ばれた似たような話題が並ぶだけ。何かを感じ取ることは難しかった。
しかし今、里美はただここにいるだけで、自分の五感が本来の働きを取り戻しているのをひしひしと感じている。
目に映る景色や、時折鼻腔をくすぐる硫黄の香り。まろやかな泉質の温泉に、耳に優しく響く鳥のさえずり。食事にゆっくり時間をかけて、心ゆくまで味わうなんてことはいつからしていなかっただろう。
正直、20代の自分にとってはかなり贅沢な2泊3日だった。ただ、それにも勝る“ここでしかできない体験”をしたのだと里美は思っている。
― もしまた心が鈍感になっちゃったら、ここに来たらいいんだ。
ご褒美旅行がこんなにも身に染みるのは、何てことない日々の暮らしがあるからこそ。そう思うと、市役所の市民課で働く毎日もほんの少しだけ愛おしく感じられる。
「2番の番号札をお持ちの方、どうぞ」
自分には、心を取り戻す場所がある。その後ろ盾ができたことで、里美はこれまでとは違った気持ちで今日も市役所のカウンターに座っている。
▶前回:「35歳を過ぎてまだ独身だけど、私は大丈夫」女が自信満々にそう思える意外な理由は…?
▶1話目はこちら:見栄を張ることに疲れた30歳OL。周囲にひた隠しにしていた“至福のご褒美”とは










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN