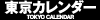帰国子女で外資系化粧品メーカーに勤める36歳女。日系企業に転職し直面した現実とは
東京を彩る様々な街は、それぞれその街を象徴する場所がある。
洗練されたビルや流行の店、心癒やされる憩いの場から生み出される、街の魅力。
これは、そんな街に集う大人の男女のストーリー。
▶前回:無意識にオトコを勘違いさせてしまう28歳女。上司から届いた、妙な親密なLINEの文面とは
Vol.7 『小さく背中を押す言葉/東京ミッドタウン』美緒(36歳)
六本木に咲く桜の木々が、満開を迎えた4月初旬。
この時期の多くのオフィスがそうであるように、美緒の働く東京ミッドタウンのオフィスにもまた、新鮮でどこかウキウキとした空気が漂っていた。
「みなさん。今日から私たちチームの一員となった、デザイナーの咲さんです」
「美緒さん、ご紹介ありがとうございます。皆様はじめまして、七瀬咲と申します。頑張りますのでよろしくお願いします!」
「じゃあ、咲さん。オフィスを案内するのでついてきてね」
「はいっ」
白シャツに淡い色のジーンズ、スニーカーといったカジュアルな装いの美緒のあとを、紺色のセットアップにローファーパンプスを履いた咲が追う。
― ちょこちょこついてきちゃって、可愛いな。まだ24歳だなんて、私より一回りも下だもんね。
美緒の仕事は、WEBデザイナーだ。東京ミッドタウンに本社を構える大手スポーツブランドで、今年控えている会員アプリの大規模リニューアルのプロジェクトリーダーとして準備をしていた。
チーム拡大のために、小さなデザイン事務所から業務委託の形で迎え入れたのは、デザイナー2年目の咲だ。
「咲さんは、クライアントにつくのは初めてなんだよね」
「はい、駆け出しの身分で美緒さんと一緒に働けるなんて…本当に光栄です」
帰国子女の美緒はアメリカの美術大学を卒業後、世界最大手の化粧品メーカーに就職し、数年の下積みを経てパリの本社配属となってからは初のアジア人WEBデザイナーとして注目を浴びた。
アジア市場でのマーケット拡大に一定の成果をあげた後、美緒が今の会社からのヘッドハンティングで凱旋帰国してから、2年の月日が経つ。
華やかな経歴とキャリア女性のロールモデルとしての存在感から、美緒の存在は最近少しずつメディアにも取り上げられ始め、界隈で注目を集めているのだった。
フランス在住時代は多国籍からなるチームメンバーと協業したり、出張で世界中を駆け巡ったりと刺激的な日々を送っていた美緒が、日系企業からのスカウトに応じて帰国を決めた理由は1つ。
美緒が学生時代から「世界を股にかける日本人デザイナー」として、尊敬と憧れの念で活動を追っていた“ジョージ・ミヤサカ”――宮坂譲司が、この日系ブランドのクリエイティブディレクターを務めていたからだ。
しかし依然として宮坂譲司は、美緒にとって雲の上の存在だった。
ドイツ在住の譲司が日本の本社に来る機会は少なく、今までに接点があったのは数回の電話会議のみ。直接顔を合わせたことはまだない。
憧れのデザイナーである譲司と仕事をしたいと願っていた美緒は、今回、アプリリニューアルという譲司直下のプロジェクトへの着任に強い意気込みを持っていた。
― 宮坂譲司の下で、刺激を受けながら仕事ができる。いつか顔を合わせる機会もあるはず。憧れの譲司さんに会った時、自信を持って振る舞えるように…。この一大プロジェクトは成功に導くんだ。
◆
新チームが始動して1ヶ月。ミッドタウン・ガーデンは鮮やかな新緑の季節を迎えていた。
朝から晩まで会議が詰め込まれ、どこへでも咲を連れてせわしなく行動する毎日。
会議室にこもりきりの日も珍しくなく、そんな日の美緒は、咲と連れ立って地下のパン屋さんやデリ店で軽食を調達し、揃って仕事へと舞い戻るのだった。
右も左もわからない咲を、業務過多の状況に追い込んでいることに美緒は負い目を感じていたが、咲はこの状況を成長の機会と捉え、徐々に現場に馴染もうと積極的な様子だ。
― でも…。
美緒は咲に持ち前の粘り強さや才能は感じるものの、仕事の段取りや意思疎通がスムーズでないことが気になっていた。社会人歴が短い上に、慣れない英語での会議が多いからなのかもしれない。
成果史上主義のこの会社では、別の会社の社員で、直接の後輩ではない咲の育成に時間を割くようなメンバーはおらず、咲が置いて行かれていてもフォローはない。
そんな空気を感じ取ってか、咲は力不足を気に病んでいるようだった。
しかし美緒は、自分のことを姉のように慕い、明るく前向きに学ぼうとする咲の姿勢を買っていた。
「咲さん。今日…実はお昼にダミーの会議入れておいたの。たまにはゆっくり美味しいランチ行こ!」
「ええ!嬉しい…行きましょう!」
美緒が選んだ店は、トリュフ料理の専門店『Artisan de la Truffe』。
本国フランスではパリの中心にほど近いマレ地区に、ブティックを併設した本店を構えている。
フランスの外食にしては良心的な価格帯で、駆け出しデザイナー時代の美緒のお腹と心を満たしてくれた、拠り所のような場所だった。
六本木で見つけたときは、日本では高いのかな…と思ったが、実際にはパリと変わらない価格帯でトリュフをたっぷり楽しむことができ、ホッとしたことを覚えている。
さらにはテラス席から四季折々のミッドタウン・ガーデンを眺められるとあって、このレストランは日本でも変わらずに、美緒の心の拠り所となっている場所なのだった。
「咲さん、1ヶ月ずっとバタバタでごめんね。本当に一生懸命キャッチアップしてもらって…感謝してる」
「いえいえ!みなさんにご迷惑おかけして…勉強させていただいてばかりで、申し訳ないです。早くお力になれるよう頑張ります」
「ありがとう。私もチームもまだまだ発展途上だから、一緒に頑張っていこうね」
それからもふたりはほぼ毎日、朝から晩までを共に過ごした。
会議室でチョコレートをつまんだり、仮眠を取り合ったり、ときにはカフェで休憩し、残業の合間に夜景を見に行ったり…。そんな日々の繰り返しでプロジェクトは過渡期に入り、季節は巡りゆく。
実力や年齢に差はあれど、向上心が根底にある美緒と咲は不思議とペースが合う。よい師弟関係を築いていると言えた。
暑く忙しい夏を乗り越え、心地よい秋風を感じられるようになった頃。成長を重ねる咲から、美緒の手が徐々に離れていく。
四面楚歌のような状況だった咲も徐々にチームに打ち解け、プロジェクトはうまく回り始めていた。
しかし美緒には、春からの数ヶ月間、ずっと悩まされていることがあるのだった。
「譲司さん、フィードバックありがとうございました。また対応完了次第、報告します。それでは…」
深夜23時。ドイツにいる譲司への進捗報告が終わり、プロジェクトはいよいよ山場を越えようとしていた。
― 年が明けたら、アプリのリリースだ。そして譲司さんが来日する…。
美緒の胸に込み上げていたのは、喜びや楽しみといった気持ちではない。
譲司と仕事で話すたび、その顔をモニター越しに見るたび、余裕のある声のトーンを耳にするたびに──。
まるで何かにせき立てられているかのように、美緒の心が落ち着かなかった。
美緒が譲司に対して抱いている感情。それは当初、ロールモデルとしての憧れだったが、いつしか羨望へと変化していた。譲司の才能や、自由な生き様に対する羨ましさと、自分自身に対する焦り。
― 私、このままでいいのかな。
14年間WEBデザイナーを続けて、個人としての知名度もあげてきたつもりだったが、結局は大企業にいる以上は歯車の一つに過ぎないのではないか?
大企業にしか勤めたことのない美緒は、企業名を背負ってでしか自身を語れないことに、クリエイターとしての疑問を抱き始めていた。
さらに、美緒の頭を悩ませる出来事がもう一つあった。予算の都合で、咲の契約延長が難しいかもしれないと上長から相談を受けたのだ。
― 今の咲さんはチームには欠かせない存在だって、何度も交渉しているけど…。
予算の話を出されては、一社員である美緒の立場ではどうすることもできない。こちらの意向を強く伝えて、会社としての判断を待つのみだった。
翌朝美緒が早めに出社すると、すでに咲がデスクについている。
こちらに気づいた咲に美緒は笑顔で手を上げたが、顔を上げた咲の目には涙が滲んでいた。
― まさか…。
恐れていたことが起きたのでは、と美緒の顔色がさっと変わる。
「どうしたの?」
「私…もっと美緒さんの元で働きたかったです」
話を聞くと、プロジェクトもクローズ段階に入り、予算担当者から年内での契約終了を言い渡されたとのことだった。
「そんな…」
やはり止められなかったんだ、と美緒は自身の無力さを心の中で嘆いた。
「チームのお荷物という印象が払拭できなかったみたいで…私が早く戦力として、地位を確立できていれば。デザインも英語も、もっと勉強しておけばよかったです…」
嘆く咲の肩に、美緒はそっと手を置いた。
美緒に心配をかけまいと気丈に微笑む咲。その瞳が赤く染まっていたのは、涙をぐっと堪えているからに違いない。
けれど美緒はその様子を見て、今この瞬間が、咲の成長に必要な転機であることを確信した。
「今からだって遅くない。まだ若いんだもん、いくらでもチャンスはあるよ…」
◆
それから4ヶ月が過ぎ、六本木ミッドタウンは最も華やかな季節を迎えた。
ズラリとグラスが並んだテーブルの向こうには、見慣れたはずのミッドタウン・ガーデンの風景が桜の花に彩られて楽しげな春色に染まっている。
「それでは、アプリリリースも無事済んだということで、乾杯!」
プロジェクトリーダーとして高らかに挨拶を終えた美緒は、テラスから見える咲き始めの夜桜に目をやる。
― また、春が来た。けど…。
1年前、同じようにここで季節を感じた。けれど、馴染み深い『Artisan de la Truffe』が会場だというのに、何かが足りない。
― やっぱり、咲さんがいないと寂しいな。
美緒はこの場に咲を招待していた。しかし、咲の姿は見えない。
やっぱり、契約が打ち切りとなった職場の打ち上げに来るのは、気が重かったのだろうか。
そう思いつつもどこか期待を捨てきれない…。ため息をついた、その時。
会場の入り口から照れくさそうな顔がのぞいた。
「美緒さん、お久しぶりです。アプリリリース、おめでとうございます!」
咲の登場に場がパッと明るくなり、楽しげにチームメンバーの輪に溶け込んでいく様子に、美緒は胸を撫で下ろした。
咲をこの場に呼ぶことには、チーム全員が賛成した。
咲は美緒が海外出張で飛び回っている間にチームの要として人一倍働き、少なくともメンバーからの信頼はきちんと得ていたのだった。
食事を終えて各々がくつろぎ始めたタイミングで、美緒は咲の隣に座った。
「美緒さん、報告があるんです。実は…所属するデザイン事務所を休職して、春から北欧のデザイン学校に通うことにしました」
「ええ!おめでとう。北欧かぁ、ワクワクするね」
「はい。行くからには楽しんで…成長してきます。遊びに来てくださいね」
そして迎えたお開きの時間。
「応援してる」と告げて、美緒は咲と別れた。
桜でも眺めて帰ろう、と庭園を乃木坂方面へ歩いていた時、目の前に現れた男性を見て美緒は心臓が飛び出そうになった。
「譲司さん!」
― さっき打ち上げの会場で挨拶はしたけれど、緊張でほとんど話せなかった…。まさかここで会えるなんて!
譲司は驚いた様子でこちらを見たが、すぐに美緒に気がつき笑顔になった。
「美緒さん。アプリのリリース、あらためておつかれさま。おかげでとても良いものが世に出せたね」
憧れの人からの労いの言葉に、美緒は胸がいっぱいになる。
それと同時に、譲司との仕事はひと段落したのだという実感が湧いてくる。直接話せるチャンスは、二度とないかもしれない。
「譲司さん、あの…私ずっと尊敬していました。あなたの背中を追って、デザイナーになると決めたんです。デザインで、世の中の課題を解消したいって」
切迫した美緒の様子を見て、譲司は何かを考えている。美緒は慌てて言葉を繋いだ。
「それで…一緒にお仕事できたことに感謝しています。ありがとうございます」
無理やりまとめてしまった言葉。しかし葛藤の末、美緒は本心を吐露した。
「でも、実は…このままでいいのか悩んでいて。譲司さんと一緒に仕事して、あらためて思ったんです。まだ成長したいって」
それを聞いた譲司は、ポケットから何かを取り出して美緒に手渡した。
「今からだって遅くない。まだ若いのだから、いくらでもチャンスはある」
触れた手の温かさに感動しながら、美緒は驚いて譲司の顔を見た。
なぜならその言葉は、美緒が咲にかけた言葉とほとんど同じだったからだ。
人生の転機に立ち会った瞬間にかけた、小さく背中を押す言葉。
― 譲司さんはどんな想いをこめて、この言葉を私にくれたのだろうか…。
探るような美緒の表情を見て、譲司は目で「手の中を見て」と合図する。
美緒の手に乗せられたのは、譲司の名前とWEBサイトのみが記載されたシンプルな名刺だ。
しかしロゴだけが印刷された裏面には、デザイン事務所の住所と電話番号が手書きで記入されている。
宮坂譲司の個人事務所は、連絡先非公開。その手書きのメモつきの名刺は…美緒が憧れの人に認められたという、ゆるぎない証拠なのだった。
「経験を積んだあなたは、どんな世界にだって出ていけるよ。良かったら、一度遊びに来て」
笑顔で去っていく譲司が、六本木の夜景に溶け込んでいく。
彼の背中を見送った美緒は、もらったばかりの名刺を夜空に掲げてみた。
満開の桜でいつもより明るい夜空を背景に、名刺がいっそう輝いて見える。
明日から紡がれる未来の楽しい予感を胸に、美緒は名刺を大切に鞄へとしまった。
▶前回:無意識にオトコを勘違いさせてしまう28歳女。上司から届いた、妙な親密なLINEの文面とは
▶1話目はこちら:バレンタイン当日、彼と音信不通に。翌日に驚愕のLINEが届き…
▶Next:4月2日 火曜更新予定
福岡にUターン就職した男が、3年ぶりに東京へ。思い出の地・赤坂は変わっていて…










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN