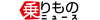「ジャンボ機」として知られているボーイング747は、前方にあるコブのような2階席部分「アッパーデッキ」を設計上の大きな特徴としています。なぜ総2階建てではなく、このような形状となったのでしょうか。
実は総2階建ても検討されていた?
「ジャンボ機」と呼ばれ民間航空業界を一世風靡したボーイング747。この機体は前方にあるコブのような2階席部分「アッパーデッキ」を特徴としています。なぜ総2階建てではなく、この「前方だけ2階」という独特の形状となったのでしょうか。
実はこの特徴的なデザインの始まりは、747のルーツが軍用輸送機の設計案であったことからです。
1961年から1965年にかけ、当時の輸送機より大容量の荷物を積めるモデルを求めていたアメリカ軍は、新型の大型戦略輸送機計画を立て、その設計案をボーイング、ロッキード、マクダネル・ダグラス(のちにボーイングと合併)に依頼。そのなかから次世代輸送機の選定をすることになります。
結果的に3社の案からロッキードのものが採用され、これがのちの「C-5 ギャラクシー」となります。ボーイングは、この競争に敗れたわけです。そのなかで、ボーイングは旅客型だけではなく、貨物型としても使える大型の民用旅客機の開発が必要と判断します。
そこで先述のロッキードに敗れた際の設計案をベースとした大型機開発に着手し、これがのちの747へとつながったのです。この開発の段階で、「ジャンボ」の特徴であるアッパーデッキが採用されることになります。
ただ、超大型の民間旅客機であれば、現代のエアバスA380のような総2階建てにした方が多くの乗客を乗せることができそうです。なぜあえて「前方のみ2階建て」としたのでしょうか。
あえて「前方のみ2階建て」となったワケ
ボーイング747が総2階建てとならなかったのは、総2階建てとすると貨物機として使うとき、1階部分にあたるメインデッキの容量が小さくなるためとしています。
総2階建てで胴体全体が大きくなるのに対し、「ジャンボ」のスタイルは、アッパーデッキ部分に若干の座席とコックピットを配置することで、1階にあたるメインデッキの天地前後ほぼすべての空間を旅客または貨物のスペースにすることができます。
このボーイングの「貨物機」を見込んだ設計戦略は、結果的に当たることになります。
たとえば旅客機として役割を終えた747シリーズの一部は、おもに海外の貨物航空会社で、貨物機としていまだ現役です。また、シリーズの最終派生型となった747-8は、旅客型より先に貨物型がデビューした稀有なモデルに。日本で唯一の貨物専用航空会社、NCA(日本貨物航空)はこのモデルの最初の発注会社「ローンチカスタマー」を務め同モデルの開発を後押しし、現在も主力機種として活躍しています。
「ジャンボ」の貨物機はメインデッキの収容力の高さだけでなく、機首部分が上に開く「ノーズカーゴドア」を多くの機体が備えており、大きな貨物などを直接積み込めることが強みのひとつになっています。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN