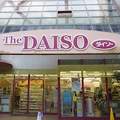JRトラブルが頻発…深刻な〇〇不足

3月6日にJR東日本が運行する東北新幹線「はやぶさ」「こまち」の連結部分が外れ、129本が運休、148本が最大約5時間遅れ、約15万人に影響が出るという事故が発生。1週間以上にわたり通常運行できない状況が続いた。東北新幹線では昨年9月にも「はやぶさ」「こまち」で走行中に連結が外れる事故が発生するなどトラブルが相次いでおり、SNS上では「最近、止まりすぎ」「コスト削減を優先しすぎでは」「以前はなかった凡ミスが発生」といった声があがっている。実際のところ、以前と比べてトラブルは増えているのか。また、背景には何があるのか。専門家の見解を交えて追ってみたい。
・JR東日本が運行する東北新幹線「はやぶさ」「こまち」の連結部分が外れ、1週間以上にわたり通常運行できない状況が続いた。
・専門家「必要以上のコストカットは逆にコストが増大する可能性があり、JR東日本に関しては絶対に削ってはならない部分のコストカットは行っていないでしょう」
・実際のところ、以前と比べてトラブルは増えているのか。近年深刻さを増している人手不足も影響している可能性。
今回のトラブルは3月6日午前11時30分頃、上野-大宮駅間を時速約60kmで走行中の東北新幹線で発生。西日暮里駅付近で約8m離れて停車し、東北・上越・北陸新幹線の上下線で運転を一時見合わせ。14日まで連結での運転を見合わせ、運輸安全委員会は「重大インシデント」と認定して鉄道事故調査官を派遣したが、詳しい原因はわかっておらず、連結に関係する部品に応急措置をほどこして運行が再開された。
ちなみにJR東日本では、中央・総武線の各駅停車で3~4年ほど前から、運転士の体調不良によるオーバーランや、停止位置より大幅に手前での停車、居眠り運転、急な運転士交代に伴う運転の一時停止などが相次いでいることが話題となっていた。2024年7月18日付「東京新聞」記事『電車のオーバーランがなぜか多発 中央・総武線の中野電車区、3年で40件 運転士の間では「中電病」とも』によれば、同路線の各駅停車(三鷹-千葉間)の運行を担当する中野電車区では、こうした事態が過去3年間に約40件発生しており、「中電病(なかでんびょう)」と呼ばれているという。
東北新幹線では昨年9月にも同様の事故が発生するなど、世間からは事故が相次いでいるというイメージが持たれているが、実際にトラブルなどは増えているのか。鉄道ジャーナリストの梅原淳氏はいう。
「昨年9月と今年3月に発生した『はやぶさ』と『こまち』との連結部が走行中に外れたトラブルは、異例の事態だといえます。新幹線はもちろん、在来線でもまず起きないような事態が一度ならず二度も起きており、国の運輸安全委員会による調査の結果が待たれます。いま挙げたトラブルとは別に、JR東日本の新幹線では確かに運転見合わせが頻発しているように見受けられます。件数は公表されていないので何ともいえませんが、2024年以降では1月23日に東北新幹線の上野駅と大宮駅との間で架線が切れるトラブルで東北新幹線東京駅-仙台駅間、上越・北陸新幹線の東京駅-高崎駅間が終日運休となったのに始まり、最近では3月26日も強風により長時間運転を見合わせました。運転見合わせの多くは自然災害によるもので、JR東日本側の責任ではないのですが、架線の切断や連結が外れることによる運転見合わせはJR東日本の責任で、トラブルは皆無にできないものの、多いと思われるのはやむを得ないでしょう」
■鉄道事業は固定費の比率が9割前後と高い
では、トラブルが頻発している原因はなんなのか。コスト削減などが影響している可能性はあるのか。
「JR東日本をはじめ、鉄道会社各社はコロナ禍以後、経費の節減に努めています。鉄道事業は固定費の比率が9割前後と高いので、輸送需要がわずかに減少しても利益が減ってしまいます。とはいえ、鉄道事業で安定して売上を維持するには安全で安定した輸送が前提となり、必要以上のコストカットは逆にコストが増大する可能性があり、JR東日本に関しては絶対に削ってはならない部分のコストカットは行っていないでしょう。
近年深刻さを増しているのは人手不足です。先に挙げた架線のトラブルでは架線の張力を保つテンションバランサのなかで、人の目による確認がより必要な滑車式と呼ばれる装置の破損が原因でした。メンテナンス頻度の低い装置への更新も同社は進めていましたが、人手不足の進行がより早かったために見過ごしたという見方もできるでしょう。
新幹線ではないのですが、JR東日本では2025年2月10日に山手線内回りの浜松町駅と新橋駅との間で線路異常が発生し、一時山手線の内回りの電車が隣を走る京浜東北線大宮方面の線路を走ることとなりました。その際、田町駅から西日暮里駅までの各駅では駅員が山手線の電車に対してホームドアを操作することとなりましたが、鶯谷駅では普段はホーム監視担当の駅員が配置されていないため、応援の駅員が同駅に到着するまで山手線の電車は鶯谷駅を通過していました。コストの削減とトラブルの多さ、ましてや事故との関連はいまのところ薄いとしても、ひとたびトラブルが起きたときの復旧面では課題を残したといえます」(梅原氏)
詳細はビジネスジャーナルをご覧下さい。
編集者:いまトピ編集部