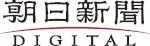福島県内が消沈した、あの日から1年。全国新酒鑑評会(酒類総合研究所、日本酒造組合中央会共催)の結果が22日に発表される。10連覇をめざした昨年、金賞は14酒にとどまり、想定外の5位に終わった。だが、今年出品した蔵元たちは、これまでと違い、どこか楽しそうだ。
この12年で金賞に9回選ばれた鶴乃江酒造(会津若松市)は、県産米の「福乃香(ふくのか)」で造った大吟醸酒を初めて出品酒にした。県農業総合センター(郡山市)が15年かけて完成させた酒米だ。酒造りも担う専務の林ゆりさん(50)は「連覇が途切れたので挑めた」。
「会津中将」を造る蔵元で、これまで、県の別のオリジナル酒米「夢の香(かおり)」を使った酒で出品を考えた時もあった。だが、金賞酒の定番酒米と言えば、30年以上も兵庫県産の山田錦だ。しっかりとした味わいになるため、ほかの米を寄せつけず、酒米の「王様」と言われる。
県内の蔵元にとって全国新酒鑑評会は特別だ。連続日本一は、原発事故の風評被害に苦しむ福島の復興を牽引(けんいん)する象徴になった。山田錦を外すわけにはいかなかった。
それが昨年、長年の「常識」が覆った。
全国一となった山形県の金賞受賞酒20点のうち半数が、山形のオリジナル酒米・雪女神を使った酒だった。「ボルドー」や「ブルゴーニュ」などのワインのように、産地で世界に売り込みを狙う県ぐるみの取り組みが功を奏した。
昨年、金賞を逃した林さんは言う。「山田錦を使って会心のできだと思ったのに金賞を取れないなら、もっと自由に楽しんでみようと」
「雪小町」を造る渡辺酒造本店(郡山市)は、昨年に続いて福乃香の大吟醸酒で出品した。昨年は入賞も逃したが、同じ酒が秋の東北清酒鑑評会では優等賞に選ばれて自信を持った。
隣の須賀川市の農家に作ってもらっている。「苗をいつ植え、どういう気候の中で米が育っているか、逐一連絡が来る。それが強み。山田錦の酒は強いから金賞には届かないかもしれない。でも、地元の『米、水、人』と三拍子そそってできた酒だと自慢できる」と渡辺康広社長(59)。
県内の蔵元に詳しい、県観光物産館の桜田武館長(54)は、こうした新たな動きを歓迎する。「連覇の重圧が消えて『挑戦元年』と言えるのではないか。酒造りの幅が広がる」
とは言っても、県内関係者が望むのは日本一への返り咲きだ。出品酒のうち2割ほどが金賞に選ばれる。今年は46酒が出品された。
9連覇を後押しした県酒造組合特別顧問の鈴木賢二さん(62)は言う。「3月にあった県の鑑評会の酒は去年よりもはるかにできがいい。最大のライバルは酒どころの兵庫県だと思うが、好結果が期待できる」(岡本進)
■全国新酒鑑評会で1位の県
2023年 山形
(2)兵庫(3)長野(4)新潟(5)福島
22年 福島
21年 福島・長野
20年 コロナ禍で決審中止
19年 福島
18年 福島・兵庫
17年 福島
16年 福島
15年 福島
14年 福島・山形
13年 福島
12年 新潟
11年 新潟










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN