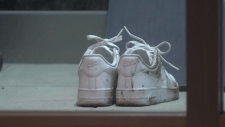刻々と変化する別府のまちに、
文化とコミュニケーションの新しい拠点が誕生
光浦高史さんは、建築設計をとおした空間再生や地域デザインへの取り組みで注目される建築家です。
神奈川県川崎市で生まれ、東京で学び、〈青木茂建築工房〉を経て独立。2009年から大分市に、2021年からは別府市に拠点を構え、由布市、竹田市、豊後大野市など県内をはじめ、北九州市や東京など県外でも活躍。別府のホテル〈GALLERIA MIDOBARU(ガレリア御堂原)〉の建築設計や、大分市の〈大分銀行赤レンガ館〉のリノベーションなどでも高い評価を得ています。

宿泊施設の設計や改修を何度も手がけていた高史さんが、陶芸家の妻・坂本和歌子さんとともに“宿主人”の肩書きを掲げ、自ら運営に取り組んでいるのが〈HAJIMARI Beppu〉です。
別府の南部と呼ばれるエリアに立つ、タイルのあしらいも印象的な4階建てのビル。半世紀ほど前、酒の卸問屋が倉庫としてつくった2層吹き抜けの大空間と事務所、そして上階を占める住居スペースが、高史さん&和歌子さん夫妻によって生まれ変わりました。

「宿という形態に、可能性とやりがいのある仕事だという感触を抱いていたんです。建築家として宿泊施設の設計を請け負うにあたって、何が求められているのか、どんなスペースが使いやすいのか、清掃のしやすさは、など、いろいろ試しながら具体的な課題を知り、新しい視点を得られるというのも大きな魅力でした」(高史さん)

「自由に実験できる場が欲しい」という思いは独立直後からあり、新しく建てるだけでなく、良い建物を後世に残していきたいという願いから、はじめは大分市内を中心に、数年前から別府に的を絞って既存建物を探していた高史さんと和歌子さん。そんなときにこの場所と出合いました。

高史さんがひと目で惹かれたという旧油屋ビル。決め手になったのは「2層吹き抜けで天井が高く、大きな開口部がある1階の元倉庫だったスペースの魅力ですね。かつて市役所通りと呼ばれていた大通りに面して開けた、人の出入りがしやすい、まちにつながっていきやすい空間だと思いました」

当初は借りる予定で手続きを進めるなか、ポロッともらした「ここ、売ってはもらえないですよね」という高史さんの言葉から事態が大きく動き、持ち主から「思い出のある建物なのでいいかたちで生かしてくださるのなら」と、1棟まるごと譲ってもらえることに。
建築設計事務所の移転、和歌子さんの工房の新設、器と焼き菓子の店〈うみとじかん〉のオープンに続いて、〈HAJIMARI Beppu〉が完成したのが2023年9月。土地にゆかりのあるクリエイターやアーティストと協働した新しい文化拠点が生まれました。

別府の魅力に触れ、暮らすように滞在する。
〈HAJIMARI Beppu〉の楽しみ方
別府市南部エリアに完成したHAJIMARI Beppu。道路沿いに大きくとられた開口部から館内を満たす心地よい騒めきと活気を感じさせる1階は、宿のレセプションとロビーラウンジ、カフェ、ライブラリー、コワーキングスペースとしても利用できる開放的なスペースです。

〈喫茶ゆあみ〉では料理家のワタナベマキさんが監修した「湯治のためのスープ」や、ビル内でひと足先にオープンした、うみとじかんの焼き菓子、台湾料理の定番である鶏肉飯(ジーローハン)など、地域の生産者から仕入れた食材でつくるフードとドリンクを提供。
「湯を浴びるという意味に加えて、温泉地での療養=湯治という古くからある習慣を意味する“ゆあみ”という言葉にかけて、体にやさしいメニューを提供しています」(高史さん)

大きなテーブルを囲むテーブル席、ソファ席やベンチ席などが選べる〈HAJIMARI LOUNGE〉は宿のロビーラウンジと喫茶スペースを兼ね、月2回ほど開かれるイベントの会場にもなり、アーティストの作品を見せるギャラリーとしての機能も。物販スペースには、坂本和歌子さんの器をはじめ、地域やHAJIMARI Beppuに関わりの深いクリエイターやアーティストたちの作品やグッズが並びます。

ライブラリーには、「文筆家の甲斐みのりさん、料理家のワタナベマキさんなどの著書、選書していただいた本、藤田洋三さんの写真集、アートを軸に活動するNPO〈BEPPU PROJECT〉の取り組みの関連書籍、別府の歴史をたどる本などが並んでいます。こちらの本はラウンジでも、宿泊のお客様なら客室でも、館内で自由に読むことができます」
奥に続く建築事務所のスペースの手前には建築の専門書、アートブックや、哲学書などが並ぶ本棚が置かれ、こちらももちろん閲覧OK。太っ腹です。

客室は3〜4階。かつてオーナー家族が暮らした2フロアが、サイズも間取りも異なる6部屋に改修されました。
「長期滞在をして仕事や制作に打ち込めるように、部屋ごとにレイアウトと家具のセレクトを変えています。室内やテラスに大きなスペースを設けていたり、複数人での打ち合わせにも使える大きなテーブルを置いたり、集中しやすい環境をつくってデスクを配置したり。ベッドの数も部屋によって違い、貸し出し布団を合わせれば最大5名まで宿泊できる部屋もありますよ」

注目すべきは最上階に位置するユニバーサルルーム。電動ベッドを備え付け、エレベーターから室内まで段差をなくしてバリアフリーを実現。別府市在住の画家、イラストレーターの網中いづるさんがこの場所で制作した大きな絵画が展示され、アートを親密に感じさせる空間がつくり出されています。

「網中さんをはじめ、安部泰輔さん、藤田洋三さん、〈Olectronica〉のふたり、宿主人である坂本和歌子など、大分県在住のアーティストによる作品が各部屋に展示されています。今後は3階から屋上までを結ぶ階段スペースもギャラリーとして活用していく予定です」

徒歩圏内に共同温泉がいくつもあるこのエリアならではのサービスとして、「1泊あたり1湯無料のチケットと、部屋に備えつけた温泉セットを持って湯巡りを楽しんでもらえたら。そうそう、大分在住の美術家、安部泰輔さんの“おふくろうさん”という作品は、湯巡りやお買い物のお供に持ち出すこともできますよ」


館内に置かれた家具のバリエーションと味わい深さも印象的です。実はこれらの家具は、大分県内各地と東京・目黒から運ばれてきたもの。
「地域の方々にお声がけして、思い入れがあるけれどいまは使っていない椅子をお譲りいただき、修繕、メンテナンスして使っています。リメイクした椅子の張り地は、別府で活動するユキハシトモヒコさんの温泉染め。色鮮やかで手触りのよい生地です。1階の大きなテーブルやソファなどは、目黒〈HOTEL CLASKA〉閉館の際に譲り受けた家具も多く、CLASKAを知る方には懐かしんでもらえると思います」


まちの余剰空間を再生して、
新しい人の流れを生み出す
かつては浜脇地区と別府駅前の新旧の繁華街を結ぶ地点だったというこのエリア。高史さんは、なぜいま別府のこの場所にHAJIMARI Beppuをオープンしたのでしょうか。
「このエリアは、市役所の移転もあって空きビルや空き家も増えているけれど、見方を変えてみれば空間的な資源が豊富な場所だとも言えます。縁があってこの場所を手に入れることができたので、ここからまちへと人の動きをつくり出し、地域の変化を促していきたいし、周囲へもその動きが広がってほしい。HAJIMARI Beppuがひとつのモデルケースになれたらいいなと考えています」(高史さん)

今後は、別府や大分に縁のあるアーティストのトークイベントを開催したり、作品発表の場としてラウンジを活用したりと、いくつもの計画が進行中です。
別府×アートという結びつきは、高史さんがこれまで手がけた仕事においても大きな比重を占めています。〈GALLERIA MIDOBARU〉の建築設計が2020年、1928(昭和3)年に電話局として建てられ、いまなお残るレンガホールに設けられた〈TRANSIT〉の展示室改修は2023年。

「GALLERIA MIDOBARUでは、BEPPU PROJECTがアーティスト選定などのキュレーションを、大阪のクリエイティブユニット〈graf〉がクリエイティブディレクションを担当しました。この仕事を通してあらためて実感したのが、アートとアーティストの力です。アートには人の考え方や物事のつながり方というものを変化させていくすばらしい作用があるんだなと感動しました」(高史さん)


大巻伸嗣、目[mé]、西野壮平、Olectronicaなど、国内外で活躍する12組のアーティストによる、別府を題材にした作品が展示されるGALLERIA MIDOBARU。1900年創業の〈関屋リゾート〉が営むホテルは、全国から、そして海外から、建築ファンやアート好きの注目を集めています。
「オーナーも交えディスカッションを重ねながら、どういった作品を置いていくかが決まっていったのですが、それを受け止める設計のほうは、ガチっと決め込むのではなく、リズム感のある空間を生むための仕組みを設定して、そこにアートが置かれることで空間がさらに変化する。アートが関わることで、建築というハードの面からも、思い切った表現を提案できました」

GALLERIA MIDOBARUに続き、新たな拠点としてアートの魅力を発信するHAJIMARI Beppu。別府市創造交流発信拠点として情報発信や移住支援を行う場所であるTRANSITにもほど近いこの場所が、別府という歴史あるまちの有機的な変化を、現在進行形で促す力になっています。

1977年神奈川県生まれ。早稲田大学理工学部建築学科卒業後、〈青木茂建築工房〉に所属。2009年、池浦順一郎とDABURAを設立。2014年〈DABURA.m〉に改組、代表となる。グッドデザイン賞ベスト100、建築九州賞作品賞など受賞多数。web|DABURA.m Inc.
address:大分県別府市千代町5-1
tel:0977-76-7667
access:JR別府駅から徒歩約13分、大分空港から車で約50分
営業時間:喫茶ゆあみ 11:00〜17:30(17:00L.O.) ※2024年4月以降は、金・土曜11:00〜20:00(19:30L.O.)
※イベントにより変更の場合があるので、SNSで要確認
定休日:火・水曜
web:HAJIMARI Beppu
Instagram:@hajimari_beppu
credit text:鳥澤光 photo:ただ(ゆかい)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN