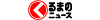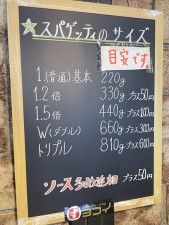便利なワンタッチウインカーが、違反になる可能性があります。一体どういうことなのでしょうか。
「5回点滅」じゃ足りない… 不便さ指摘する声も
近年登場した新型車には、便利な装備として「ワンタッチウインカー」が採用されるモデルが増えています。
一見すると便利そうな装備ですが、実はユーザーからは賛否両論が巻き起こっているほか、使用方法によっては違反になる可能性もあります。一体どういうことなのでしょうか。
道路交通法第53条では、車線変更や交差点を右左折する場合、クルマが動く方向を周囲に知らせるため、ウインカーを使って合図を出さなければならないと定められています。
具体的に合図を出すタイミングは、右左折しようとする地点の30m手前や、車線変更する3秒前などで、これらの行為が終わるまでウインカーを出し続けなければなりません。
ウインカー操作は、国産の右ハンドル車の場合、ハンドル付け根の右側にあるレバーを上に倒すと固定されて左ウインカーが点灯。下に倒すと固定されて右ウインカーが点灯します。
また、レバーを軽く倒すと固定されず、倒している間だけウインカー点灯が可能です。
そして、ウインカーレバーが固定された状態でハンドルを一定角度以上回転させた後、まっすぐに戻すと固定が解除され、ウインカーが自動的に消灯します。
一方、このウインカー操作時に、ゆるい交差点の右左折時や車線変更などでは、ウインカーレバーの固定が戻らなかったり、戻すのを忘れたりしてウインカーが“出しっぱなし”になってしまうこともあります。
この戻し忘れを防ぐのにワンタッチウインカーが有効です。
ワンタッチウインカーは名称の通りウインカーレバーをワンタッチ操作するだけで、ウインカー(方向指示器)が複数回点灯する機能です。
メーカーによって「コンフォートフラッシャー」「スリーフラッシュターンシグナル」など呼び方が異なりますが、概ね5回や3回などの点灯動作が繰り返され、戻し忘れだけでなく、車線変更などで短い合図を出す際にも有効です。
一見すると便利に見えるワンタッチウインカーですが、実際にはユーザーからの評価は賛成意見ばかりではないようです。
「間違えて操作したときに5回点滅するのうざい」「間違って(ウインカーを)出したらキャンセルできないから不便」と、ウインカーレバーの誤操作時に必要のない合図が継続してしまうことを不便とするコメントや、「ワンタッチウインカーだけでは合図としては不十分」「車線変更でも3回じゃ足らない」など、合図としての役割を果たさないことに疑問を呈する声もあります。
特に、点灯回数について交通ルールでは、先出の通り「交差点30メートル手前」「進路変更する3秒前」とされており、実際の点灯時間と法律を照らし合わせると、場合によっては合図不履行になる可能性も考えられます。
警察署交通安全課の担当者は、過去の取材でワンタッチウインカーでの進路変更について以下のように話しています。
「ワンタッチウインカーの点滅時間が約3秒だと仮定すると、3秒前にウインカーを出さなければならないので進路変更する直前、もしくは進路変更中に点滅が消えてしまう可能性があります。
当然ながら、進路変更する際にウインカーが出ていない場合は、合図不履行違反にあたる可能性があります」
このように不十分な合図と認められた場合、合図不履行違反として違反点数1点、反則金6000円が科されることになります。
ウインカーの本来の目的は、周囲を走るほかのクルマに自分の動きを伝えるためのコミュニケーション手段です。
ワンタッチウインカーの機能だけに頼って運転するのではなく、あくまで運転のサポート機能と捉えて、手動操作とともに上手に使うことが大切です。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN