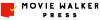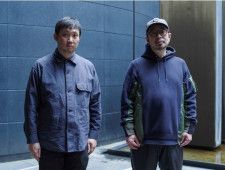幸福の“ゼロサム”を描く新奇なホラー映画『みなに幸あれ』。その“バッドエンド”が意味するものとは?【宇野維正の「映画のことは監督に訊け」】
下津優太監督の長編商業映画デビュー作『みなに幸あれ』は、その第1回の受賞作である短編をセルフリメイクしたものだ。大賞を受賞した監督には、受賞作品を長編としてセルフリメイクするか、あるいはまったく別の長編を撮るかの選択肢が与えられるわけだが、下津監督は躊躇なく受賞作の長編化に挑んだ。『みなに幸あれ』はその皮肉が効いた的確なタイトル、日本映画界でにわかにブーム化しつつある“因習村もの”としてのツカミ、そしてそこに込められたシリアスなテーマまで、商業映画として多くの観客に問うに相応しい作品であったからだ。
ホラー映画の作家には大きく分けて、「ホラーを撮るために生まれてきたような監督」と「数ある選択肢の中からホラーのジャンルに挑んだ監督」がいる。下津監督は日本ホラー映画大賞の存在が動機となって初めてホラー作品を撮った、後者の監督と言っていいだろう。しかし、興味深いのは今回の『みなに幸あれ』の制作を通して、そうした自身の作家としてのスタンスや心境に変化が生まれつつあることだ。
取材タイミング的に、下津監督にとって初めての経験となった今回のロングインタビュー。商業監督デビューにいたるまでの道のりだけでなく、世界的にもいまや若い映画監督にとっての数少ない“勝ち筋”となっているホラー映画を撮ることについての考察、そして『みなに幸あれ』の“バッドエンド”に込められた真意についても、じっくりと語り合うことができた。
※本記事は、ストーリーの核心に触れる記述を含みます。未見の方はご注意ください。
■「『死ぬまでに1本でもいいから映画が撮ればいいな』と思ってたぐらいだったんですよ」(下津)
――日本ホラー映画大賞の選考委員として、自分は下津監督の『みなに幸あれ』のオリジナル版を「選んだ側」の一人です。なので、最初に自分自身の選考委員としてのスタンスを伝えておくと、前提として、90年代の日本映画界で生まれたJホラーって、めちゃくちゃ偉大なカルチャーだと思うんですね。個別の作家は別として、これだけ世界に影響を与えた日本発の映画カルチャーって、ほかにないじゃないですか。
下津「それこそ、あとはアニメーションくらいですよね」
――はい、アニメーションは別として。実写作品においては、いまも世界中の作家に影響を及ぼしている。でも、だからこそ2020年代に入ってからこの賞が立ち上がった時、その偉大なカルチャーのフォロワーではなく、それを刷新するような新しい感性が宿った作品を送りだしたいと思ったんです。で、『みなに幸あれ』はオリジナルの段階から、作品のルック、編集のリズム、そしてテーマまで、まさにそういう作品で、「こういう作品に出会いたかったんだ!」となりました。
下津「ありがとうございます」
――日本ホラー映画大賞に応募したオリジナル同様、商業監督としての長編デビュー作となった本作もロケーションは福岡県の同じ場所ですよね?
下津「はい、同じロケ地です」
――現在は東京にお住まいですけど、出身は?
下津「北九州市出身です。高校まで福岡にいまして、大学は佐賀で、理系の機械システム工学科にいました」
―― そうなんですね。この連載でお会いする監督、自分が好きになるタイプの作品にそういう傾向があるからなのか、わりと理系出身の監督が多いんですよ(笑)。
下津「大学の選択で映画制作の授業があって、そこから自主制作で映像制作を始めるようになって、それと同時にサガテレビでアルバイトをしたり、地元でちょっとしたCMを作ったりとかして、大学を卒業してからはフリーランスの映像作家として、主にCMやミュージックビデオの監督をしてきました」
――東京に出てきたのは?
下津「25、6のころですね。九州で撮影した大きな案件に東京のスタッフがいらっしゃって、そこでつながりがいろいろできて、東京での仕事を依頼されたのをきっかけに上京したという感じです」
――その時点では、映画監督を目指してというわけではなかったんですか?
下津「基本的にCMばっかりやっていたので、正直、『死ぬまでに1本でもいいから映画が撮ればいいな』と思ってたぐらいだったんですよ。それで、日本ホラー映画大賞の存在を知って『これだ!』と懸けてみた感じです。それまでにも、他の賞にいくつか応募はしてたんですけど」
――30代に入ってすぐに今回の日本ホラー映画大賞を受賞したわけですよね。『死ぬまでに』というわりには、意外にも早く叶った(笑)。
下津「本当に運が良かったなというか(笑)」
■「日本映画にありがちな説明台詞の乱用も、海外ではマイナスと見られなくなるのかなって」(宇野)
――「こういう映画を作りたい」というような、作家としてのビジョンのようなものはあったんですか?
下津「広告の仕事で普通に生活はできていたんですけど、やっぱりあくまでも広告は広告だったので、クライアントありきの仕事だったわけですけど。自分がモットーにしているのは、言葉で語らず映像で見せるっていうことで。特に近年の日本映画だと、1から10まで説明するような、小学生にもわかるような説明的な映画が多いんですけれども。そうではなくて、僕は3から7ぐらいで説明して、説明台詞をなるべく廃して、映像で感じてもらうということをやりたくて」
――それは、よく言われる映画の一つの正しいあり方でもあるわけですけど、今回の『みなに幸あれ』に関して言うと、説明台詞的な台詞も結構ありますよね(笑)?
下津「そう、結構あるんですよ(笑)。オリジナルの短編のほうはそんなになかったんですけど、長編のほうはわりと入っちゃったなってのがあります。正直、そこはもっとブラッシュアップしたかったところで、悔いが残ってるとしたら、正直ホンだけなんですよね。現場での撮影だったり、編集だったりは、いまの自分のベストを尽くせたと思っていて」
――そうですね。話の流れでネガティブなニュアンスの質問をしてしまいましたけど、最初に言っておくべきだったのは、商業映画の長編監督デビュー作として、『みなに幸あれ』が本当に見事な作品だったということです(笑)。
「ありがとうございます(笑)」
――それと、説明台詞の問題については自分も映画批評においてはわりと指摘をするほうなんですけど、ちょっと考え方を改める必要があるのかなって思ったのは、『ゴジラ-1.0』が海外であれだけ受けてることなんですよね。これまで北米の観客は外国語映画を吹替えで観るのが主流だったわけですが、最近は字幕で観るようになっていて。そうなると、日本映画にありがちな説明台詞の乱用も、海外ではマイナスと見られなくなるのかなって。『みなに幸あれ』も、海外で賞を受賞されてますよね?
下津「はい。ありがたいことに(プチョン国際映画祭で最優秀アジア映画賞を受賞)。(第56回シッチェス・カタロニア国際ファンタスティック映画祭の上映で)スペインにも行った時も、いい意味で意外だったのは、おっしゃるように字幕上映ということで、説明台詞だとか棒読みだとかも気にならないのか、とても観客のリアクションがよかったことで」
――アニメーション映画の人気にも表れているように、現在の海外の観客は、日本の作品に“語り”の洗練を求めてるわけではないのかもしれないというのは、最近よく考えることです。
下津「そうかもしれませんね」
■「祖母役の方は、クランクアップの時には泣かれてました、重圧から解放されて(笑)」(下津)
――あと、棒読みに関しては、明らかな演出意図があるわけで、むしろ本作のチャームポイントだと思います。だって、あの短編から引き続き今回も出演されていた祖母役の方は、プロフェッショナルな役者の方ではないですよね?
下津「はい、しかもあの短編が初演技で」
――作品の中身を観た人なら誰もが思うはずですが、よくやってくれましたね。
下津「はい、本当によくやってくださって…。クランクアップの時には泣かれてました、重圧から解放されて(笑)。ほかにも候補の方が4、5人いたんですけど、役者経験のある方は、本当になんか『セリフを言ってます!』という感じの方しかいなくて。それだったら、逆に素人感がある人をキャスティングしようっていう感じで」
――素人感というか、完全に素人ですが(笑)。
下津「中盤に出てくるおじさんとかも、ほぼ演技をやったことがない方です」
――そこは“狙い”なんだと強調しておいたほうがいいと思います。ちゃんと、狙い通りの効果が出ているので。あと、そうした役者の台詞回しとも相まって、編集のリズムにもこれまでの日本のホラー映画にはない気持ち良さがありました。
下津「編集に関しては、予算をほかに割きたかったこともあって、自分で編集することにしたというのが正直なところなんですけど、結果的にはうまくいったと思います。そもそも、自分は現場でテストをしてそこから切り取っていくのではなく、最初から大体もう画を決めているんですよね。イメージとしては、カメラをセッティングして、その構図の中に役者さんが入っていただくみたいな、そっち側に近いんですね。シーンを切り取るというよりも。だから、編集も試行錯誤しながら検討するというよりも、もう撮る前から大体決まっていることが多くて。だから、そんなに大変な作業ではなかったです」
――撮影に入る前にコンテを書かれる感じなんですか?
下津「今回は“写真コンテ”と言って、スタッフにも協力してもらって、撮影前にすべてのコンテを用意していきました」
――じゃあ、それを事前に役者さんにも見てもらって?
下津「そこはちょっと悩んだんですけれども、今回全部共有させていただきましたね」
――ポン・ジュノみたいなやり方ですね。
下津「ははは(笑)」
――でも、作品を観るとわかります、そういうきっちりしてる感じ。先入観かもしれませんが、理系の方が撮った映画って感じがちょっとしますよね。
下津「そうなんですよ、ちょっと几帳面な感じで…」
――選考をしていてわかるのは、日本ホラー映画大賞の応募作って、見るからにめちゃくちゃホラーが好きで、短編にせよ長編にせよこれまでホラーばっかり作ってきたんだろうなっていう方もいる一方で、賞の趣旨に合わせて、ホラー作家というわけではないにせよ「これはホラーと呼べるかな?」っていうラインの作品を応募してくる方の大きく2通りにわかれるんですけど。下津監督は明確に後者ですよね?
下津「そうです、はい」
――『みなに幸あれ』は、日本ホラー映画大賞の存在を知って、そこから企画を立ち上げたんですか?
下津「そうです。他の応募作の監督の皆さんほどガッツリとホラー映画のファンというわけではなくて、普通の映画好きとしてホラーも観るぐらいだったんですね。なので、逆にそこが良かったのかもしれないです。正直、ホラーの古典と言われているような作品も観てなかったレベルだったので」
――それこそ、『悪魔のいけにえ』とか『ゾンビ』とかも?
下津「『悪魔のいけにえ』は受賞後、今回の長編を撮る前に勉強しないとと思って観ました(笑)。自分にとってホラーの入り口となったのは、ジョーダン・ピールの作品だったり、アリ・アスターの作品だったり、最近のA24あたりのホラーだったんで」
――でも、それが功を奏したのかもしれませんね。『悪魔のいけにえ』とか『ゾンビ』とか、純粋に映画としてすばらしいのは間違いないんですけど、ホラー作家にとって聖典になりすぎているというか。あまりにも影響力が強くて、そのフォロワー的作品が無限に作られてきたので。だから、下津監督のようなホラー作家が表れたのは、ポストホラーと呼ばれてきたA24の作品や、社会風刺的要素が強いジョーダン・ピールの作品がホラーファン以外の観客の間でも浸透するようになってきた時代の必然なんじゃないかと。
下津「そうかもしれません。そのラインを意識した作品って、日本ではまだあまりないなと思っていたので、そこを狙っていければなと思って…」
――本当に、それは大正解だと思いますよ。最初に言ったように、日本は日本でJホラーの磁場が強すぎて、若い世代の監督もどうしてもそこに引き寄せられがちだったので。
下津「そうですね。でも、いざ本格的にホラー映画の世界に入ってみると、表現できることの幅も広いし、ジャンルとしての可能性をすごく感じるようになって」
■「ホラー映画に慣れてる自分でも「ここまでやるかあ」って思いましたよ(笑)」(宇野)
――とりあえずホラー映画大賞を受賞して、こうして長編デビューもできたけれど、「今後はホラーにこだわらず作品を作っていくぞ」と思ってるわけではない?
下津「最初はそういうつもりもちょっとあったんですけど、逆に今回『みなに幸あれ』を撮ってみて、今後もホラーをやっていきたいなと思うようになって」
――おお!それはすばらしいですね!いざやってみたら肌に合った?
下津「そうなんですよ。あと、海外のいくつかの映画祭に出品して、そこでちゃんとリアクションがあったことも大きかったです。やはり海外に出て行きたいので、清水崇監督や中田秀夫監督のようにそれがハリウッドなのかはわからないすけど、海外で観られる映画を作っていきたいという思いは強いです」
――ホラー映画にはいくつか軸があって、「怖い/怖くない」という軸の他に、「グロい/グロくない」っていう軸もあるじゃないです。で、もしかしたらお客さんを選ぶことになるかもしれないけど、正直に言うと『みなに幸あれ』は間違いなくグロい(苦笑)。
下津「そうですね(苦笑)」
――ホラー映画に慣れてる自分でも「ここまでやるかあ」って思いましたよ(笑)。短編の時よりも、今回はさらにイッちゃってる(苦笑)。
下津「はい(苦笑)」
――そこには、作り手の適正もあると思っていて。例えば、医者でも外科医と内科医がいるように、ホラーにも外科手術的なホラーと内科的なホラーがあって、下津監督は外科手術的なホラーもちゃんとできる監督なんだという発見がありました。
下津「そうですね(笑)。本当に自由にさせていただけたので。例えば脚本に『おばあちゃんが組み体操をしながら出産する、破水した羊水が顔にかかる』とかって書いたんですけど、別になんにも言われなくて(笑)」
――どうかしてましたよ、あのシーンは(笑)。
下津「『あっ、これやっても大丈夫なんだ!』と思って。もう好き放題やってやろうと思って全部ぶつけた感じでしたね。本当にありがたかったというか、なかなかないですよね。1本目で、オリジナルで、新人監督で、これだけ自由にさせていただけるっていうのは」
――そこで萎縮しなかった下津監督がすごいんですよ。世の中には、本当に頭がおかしいとしか言いようのない監督っているじゃないですか。最近だったらアリ・アスターとか。彼ほどじゃないにせよ、自分の中に、ちょっとネジが外れてる部分とかを自覚されることはあったりします?
下津「実は、時々言われます。表面はこんな感じで穏やかなんですけど、サイコパスとか…」
――それはどういうところで?
下津「いや、どうやら考え方とか言動の節々にあるらしくて。別に暴力的だとかそういうことではないですよ。でも、20代半ばぐらいまでは閉じていたものが、映画を作るようになってからは『そこを開放していいんだ』ってきて」
――それは頼もしいですね。
下津「そういう意味では、自分のすべてをさらけ出して作った作品です」
■「古川さんのようなすばらしいセンスをもった役者にこの役を演じてもらえたのが、この作品の成功の一番の要因」(下津)
――でも、それが新人監督にしていきなりこれだけの作品を世に送り出すことができた、一番大きな理由かもしれないですね。つまり、ホラーにどっぷりじゃない人が新鮮なホラーを作ったっていうだけじゃなくて、その上で、ちゃんと監督自身の魂も入ってる作品になってる。無理してサイコパスを装う必要がなくて、素でサイコパスだったっていう(笑)。
下津「(笑)」
――先ほどもおっしゃっていたように、ホラーって実写映画で日本から世界を目指すとしたら、それだけで圧倒的なアドバンテージがありますよね。
下津「いや、本当にそう思っていて。正直な話、『ここ空いてる!』と思ったんですよ。メジャーの作品は特定の監督で回ってるし、なおかつ一番世界に出やすいジャンルと言われている」
――Jホラーとしてちゃんと実績を積み重ねてきているので、世界的にもリスペクトされてますしね。
下津「そうです。なのに、世界を狙ってる若手の監督があまりいない。『あ、行ける』と思って。だったら全部かっさらってやろうと(笑)」
――その戦略は本当に正しいと思います。特に北米では、ビッグバジェットのフランチャイズ作品とアニメーション作品以外のヒットって、ほぼホラーですから。特に若手の監督がいきなりボックスオフィスで1位を獲ったりするのって、いまではジャンルとしてはホラー以外あり得ませんからね」
下津「そうですよね」
――ホラーが有利とかじゃなくて、新人監督がメインストリームで勝負をしようとするなら、それ以外のルートがない。
下津「本当に。だから、あとはタイミングが大事だと思ってます」
――だけど今回、同じ作品を短編から長編にして作り直すのって、失敗する可能性も十分にあったと思うんですよ。でも、結果として短編のコンセプトはそのまま、蛇足的なことにもならず、ちゃんと約1時間半の長編映画になった。それは、なにが一番ポイントだったと思います?
下津「作品の9割9分の時間、古川琴音さん演じる主人公の”孫”が画面の中にいる。観客はその”孫”の目線で作品世界に入っていって、そこで奇妙な状況に取り込まれていくわけで。そう考えると、もう本当に古川さんのようなすばらしいセンスをもった役者にこの役を演じてもらえたのが、この作品の成功の一番の要因かなと思います」
――それは本当にそうだと思います。
下津「これは現場的な話なんですけど、古川さんが『こんなスケジュール見たことないです』っておっしゃるぐらいタイトなスケジュールというか、そういう製作の規模感だったので、ほとんど1テイクで撮ってたんですね。なので、本当に古川さんだからこそこんなやり方でも作品として成り立ったんだと思います」
――そういう意味では、この作品はホラー映画として、ダリオ・アルジェントの『サスペリア』とか『フェノミナ』とかの、いわゆる美少女ホラーにも通じるような正統派にも属しているんですよね。で、そこで重要なのは若い女性が酷い目に遭う時、その主人公にどれだけ自然に感情移入ができるかということで。逆に言うと、それができないと、主人公がどんな酷い目に遭っても観客は別にどうでもいいじゃないですか。
下津「(笑)」
――いや、正直そういうホラー映画って、日本にも海外にも山のようにあって。そこで鍵となるのは、奇妙な状況に入る前の日常の世界をいかにちゃんと描写できるかで。『みなに幸あれ』の短編を最初に観た時も、冒頭の主人公が電車に乗ってるシーンの時点で、他の応募作とは全然違う次元で作られた作品だと思ったんです。
下津「やっぱり恐怖って、日常に異物が混入して起こるものだと思うんですよね。ホラーを撮るとなると、まずその異物にフォーカスしがちなんですけれども、やっぱりその前の段階の日常が描けてないとそこに落差が生じないので。まさに、日常の生活を大切に描くことは心がけましたね。あと、今回良かったのが、メインのキャストさん以外は福岡のキャストさんなので、方言だったり言葉のニュアンスみたいなのが、なんかいいふうに転がったのかなって」
――確かに、今回の長編では方言の効果も大きいですね。そのおかげもあって、異常な世界に入った後も入りっぱなしではなく、ちゃんと日常の世界に一旦戻ってくる。そこの緩急がすごく効いてる。
下津「ありがとうございます」
■「ここで描かれているのはすごく現代的なテーマだと思っていて」(宇野)
――最後に、『みなに幸あれ』の本質的なテーマの部分についてちゃんと話をしたいんです。というのも、ここで描かれているのはすごく現代的なテーマだと思っていて。まさに、それは『みなに幸あれ』というタイトルにも込められているわけですけど、このテーマにしようと思った理由はなんだったんですか?
下津「そうですね。もともとは都市伝説で、”地球上感情保存の法則”っていうのがあるのを知りまして。物理の授業とかで”運動量保存の法則”みたいなのを習ったと思うんですけど。簡単に言うと、地球上に住む幸せな人と不幸な人を足し合わせるとゼロになるみたいな」
――いわゆる“ゼロサム”というやつですね。
下津「はい。それがおもしろいなと思って、学生のころからずっと頭の片隅にあって。それを企画を考えている時に思い出したんですね。もしそれが本当であれば、意図的に不幸な人を作り出すと、他の人が幸せを得られるんじゃないかという。でも、それってよくよく考えると僕らが生きているこの世界の成り立ちって、既にそうなってるんじゃないかって」
――なるほど。おもしろいですね。
下津「そのことをメタファーとして描こうとしたのが企画のスタートですね。僕の中の裏テーマとしては、もしかしたら観客によっては伝わらないかもしれませんが、現実と理想についての考えというのがあって。劇中で、あまり直接的ではないですが、いじめの描写がちょっとあって。いじめってなくならないし、なんなら大人もやってるよねぐらいの感じが現実で。一方で理想としては、いじめなんて世界からなくなればいい、というのがあるわけじゃないですか。でも、その現実と理想、どっちかを描くだけでは僕は駄目だと思っていて。理想だけで生きてる人がいるから、いじめを隠蔽するみたいなことが起きちゃうと思うんですよ。
みんなが、いじめはどこでも起こり得るってことを認識してないと、その問題に向き合うことができないと思っていて。なので、難しい問題に直面した時は、その現実をまず受け入れて、その上で理想を描くことが僕は大切なのかなと思うんですね。世界中のいじめをなくすことはできないけれど、目の前のいじめをなくすためには、それが第一歩という。ここでいういじめは、それこそ戦争にも置き換えることができるかもしれない。豚肉を食べるシーンの台詞もそういう考えで」
――序盤の食卓のシーンですよね?
下津「はい。別に豚肉を食うなって言ってるわけではなくて、豚が家畜として殺されてそれを食べてるっていう認識が、我々はちょっと薄くなっているのかなっていう。その現実をちゃんと理解して受け入れるってことが大事なのかなっていう」
――ただ、これって思想的な問題にもつながるわけですよね。要するに、みんなが幸せになれるという理想を掲げた思想には、例えば歴史的にコミュニズムとかもあったわけですけど、ある種、それの否定でもあると思うんですね。
下津「はい」
――その“幸せ”という言葉をあえて言い換えるなら、それぞれどんなアイデンティティを持った人間も、あるいは食肉の問題でいうなら動物も、すべての生き物は尊重されるべきだという理想があって。でも、現実世界でいろんな問題が起きている要因の一つは、そのような理想そのものだったりする。
下津「はい、そうですね。でも、その理想も描ければと思っていて」
――つまり、この作品では現実をメタファーとして突きつけるだけじゃなくて、理想を持ち続けることの大切さについても描いている?だとしたら、自分は理想の部分はあまり感じられなかったんですけど(苦笑)。
下津「そうですか(苦笑)。それはラストシーンの解釈になってくると思います」
――なるほど。
下津「パッと見はバッドエンドかもしれないですけど、単純なバッドエンドにはしたくなかったんです」
――自分が現代的だなと思ったのは、別にこれから話すことは個人的な思想ではなく、ただの現実認識の仕方ですけども。20世紀の世界には第二次世界大戦後も植民地主義が根深く残っていて、でも、21世紀に入ってそれがいよいよ隠蔽しきれなくなって、様々な経済活動や社会運動によって見直されるようになってきた。この20年の大きな違いって、かつて第三世界だとか発展途上国とかそういう言葉で呼ばれている国があって、世界中の富が欧米や日本などのごく一部の国に偏在していたのが、中国やインドを筆頭にBRICSと呼ばれる国々が発展していったことで、いわゆる南北問題はなくなってきた。グローバルサウスという最近の言葉も、まさにそのことを表しているわけですけど。でも、そうやってかつて貧しかった国の人々の生活の質がどんどん向上してきたと同時に、アメリカであったり、日本であったり、いわゆる先進国と呼ばれてきた国の内部に、これまで以上の格差が生まれているという。だから、世界レベルでは不均衡が是正されているという歴史の流れの中で、アメリカや日本は国内に深刻な格差問題を抱えるようになったという考え方もあるわけで。
下津「はい」
――『みなに幸あれ』は、まさにそのことをテーマにしてると自分は思ったんです。
下津「はい。劇中でアフリカの話も出てきますしね」
――あの”アフリカ”という括りは、ちょっと乱暴だと思いましたが(苦笑)。
下津「そうですね(苦笑)」
――まあ、劇中に出てくるかなり特異な登場人物の台詞なので、そこにツッコミを入れるべきかどうかは判断が難しいところなんですけど。それこそナイジェリアのラゴスなんて、もう世界有数の大都市ですからね。
下津「はい。ただ、そうやって本作のテーマをそれぞれの方が展開していただいて、いろいろ考えていただけれる余白があるようにと考えました」
――下津監督自身は、本作で描かれているような幸福の“ゼロサム”的な考え方を受け入れているわけではない?
下津「はい。なので、このタイトルは皮肉だけでなく希望の意味も込めてます」
――いずれにせよ、自分は今作のテーマってすごく重要なものだと思うので、下津監督が今後どういったキャリアを築いていくのかはまだわからないですけど、探求していく価値があるものだと思います。世界的にも共有されやすいテーマですし。
下津「ああ、そうですね」
――その過程で、そこで希望の度合いがちょっと増すのか、あるいは絶望の度合いがさらに増すのかがとても気になりますね。やっぱり、1本だけでその監督の作家性をすべて読み取るのって難しいので。
下津「はい。ちゃんと次の作品につなげたいと思ってます」
――今日の話の流れだと、それもやっぱりホラーで?
下津「まだ詳しいことは言えないんですけど、ホラーはホラーでも、ダークユーモア的なところに興味があって。こっちの人は怖がりながら観てて、あっちの人は笑いながら観てるみたいな」
――ああ、それはいいですね。今後も活躍を期待してます!
下津「ありがとうございます」
取材・文/宇野維正










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN