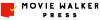アンナ・サワイと二階堂ふみが明かす「SHOGUN 将軍」がもたらした”希望”「私自身も誇りに感じた」
徳川家康にインスパイアされた武将、吉井虎永を主人公にした、1975年発表のイギリス人作家、ジェームズ・クラベルの小説を、ハリウッドの製作会社「FX」が新たにドラマシリーズ化した「SHOGUN 将軍」。プロデューサーと虎永役を兼任する真田広之のほか、国際的に活躍する日本人キャストが終結するなか、ひときわ目を引くのが、アンナ・サワイと二階堂ふみである。
『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』(20)などハリウッド大作でキャリアを積むサワイが演じたのは、英語(劇中ではポルトガル語という設定)も話すキリシタンで、主君の虎永に尽くす戸田鞠子。日本に漂着した英国人航海士、按針ことジョン・ブラックソーン(コズモ・ジャーヴィス)とのせつない運命に身を投じる役だ。そしてハリウッド作品の仕事が初となる二階堂は、亡き太閤の側室で、世継ぎである息子を守る落葉の方という役。虎永ら武将にも多大な影響力をもつ役を、毅然とした表情で演じきっている。この2人のドラマは「SHOGUN 将軍」の終盤で急展開をみせる。カナダのバンクーバー近郊での撮影で同じ時間を過ごしたサワイと二階堂は、日本での再会を心から喜んだ様子で、インタビューも和気あいあいとした雰囲気で進んだ。
■「ふみちゃんから学ぶことも多く、その姿を見ているだけで勉強になっていました」(サワイ)
――お2人は「SHOGUN 将軍」で、どれくらい撮影期間が重なっていたのでしょう。
アンナ・サワイ(以下、サワイ)「私は、だいたい10か月間、バンクーバーに滞在して撮影に参加していました。ふみちゃんは?」
二階堂ふみ(以下、二階堂)「半年くらいですね。でも合間に何度か日本に帰ったりしていたので…」
サワイ「コロナ禍での撮影だったので、自由時間にあまり一緒にいることができなかったですよね」
二階堂「でも、屋外なら大丈夫ということで、テラスのあるレストランでご飯を食べたり、美しいガーデンを一緒にお散歩したり、けっこうお話できた気がします。私は仕事のベースが日本でこれが初の海外作品でしたが、アンナちゃんは世界中のいろんな場所で活動しているので、どんなふうにお仕事をしているのか。そんな話をいっぱいしてもらいました」
――それで仲が良くなったのですね。
二階堂「アンナちゃんはとても魅力的なので、つい『話を聞きたい!』ってなっちゃうんです」
サワイ「撮影中に休憩時間があると、『そっちにお邪魔していい?』って聞いたりして、マスクを着けてお話しましたよね。私は時代劇が初めてだったので、ふみちゃんから学ぶことも多く、その姿を見ているだけで勉強になっていました」
――鞠子は虎永に忠誠を誓う側。落葉の方は虎永を憎み、彼を悩ませる役どころなので、ある種対立関係でもあります。どのような想いで共演しましたか。
サワイ「鞠子と落葉は、かつては大切な親友だったのに、政治的な問題で離ればなれになってしまう。もっと一緒にいたかったはずで、私はそのあたりの想いを意識していました。ただ対立関係にあっても、女性としての苦しみは言葉にせずとも理解し合っていたと思うのです。そうした感情をキープしながら演じました」
二階堂「鞠子と落葉には、共に守りたいものがあり、それに対してシンプルな答えを持っているという明確な共通点があります。それにもかかわらず、対局な部分もあり、そのせいか鞠子とのシーンを演じる際は、感情が揺さぶられ、かなりせつなくなりました。でも、この揺さぶられる感情こそ普遍的なんだと理解しました。アンナちゃんもお話ししたように、現代に生きる私たちには想像を絶するほどの苦しみを、当時の女性は背負っていたと思います。政治の道具にされた面もあるでしょう。そのなかで鞠子との友愛の心は、表に出すことはできません」
――その複雑な感情をサワイさんを相手に表現したわけですね。
二階堂「こうした秘めた感情を、アンナちゃんと一緒に演じると、脚本に直接描かれていない行間の部分や、落葉の新しい一面が引きだされた気がします。感情を作る面においても助けていただく瞬間がいっぱいありました」
サワイ「私のふみちゃんに対するイメージは、鞠子にとっての落葉に近かったです。鞠子のせつない感情が、ふみちゃんの目を見るだけで湧き上がってしまい…。『私、どうなっちゃうの?』って(笑)。でもいまこうして会うと、撮影の時のイメージと違うんですよ。大切な友人だけど、しばらく離れてしまった、という感覚でしょうか」
■「アンナちゃんはすごくプロフェッショナルなんです」(二階堂)
――今回の共演の前に、サワイさんは二階堂さんの出演作を観ていたのですか?
サワイ「もちろんです。特に印象に残っているのは浅野忠信さんと共演した…」
二階堂「『私の男』?」
サワイ「そう!すごく強烈でした。パワフルな演技を作品に捧げていたと思います。だから初対面の前は、ちょっと緊張しちゃって(笑)」
――二階堂さんは、サワイさんに会う前の印象は?
二階堂「アーティストでもあるし、アンナちゃんのほうが歳が上なので、インタビューなどを事前に読ませていただいていました」
サワイ「そうなんですか!?」
二階堂「はい、ググってました(笑)。でも実際にお会いすると、広い世界で活躍している方は大きな受け皿を持っていると実感できました。海外作品が初めてということで、いろいろ気負いすぎていた私が、アンナちゃんに会ってホッとできたんです。いろいろ教えてもらいました」
サワイ「いや、教えてないですよ。私って、ちょっとのんびりしていてユルい感じもあるので、自然とリラックスさせてたのかも」
二階堂「すごくプロフェッショナルなんです。重要なシーンに関して事前にオンラインで打ち合わせをした時も、アンナちゃんが自分で思っていることをみんなでシェアしたいと積極的で。その姿勢がカッコいいなって」
――それでお互いの距離が近づいていったんですね。
二階堂「日本の撮影現場の場合、スケジュールが朝から夜まで詰まっていることも多いんですが、今回は規模も大きく、その作品だけに集中する時間を与えていただいたので、アンナちゃんともコミュニケーションが取れたんです。その環境で心の持ちようも変わっていきました。アンナちゃんの姿から学んだうえに、真田(広之)さんともお話させていただき、何事も自分次第なんだと自覚できて、改めて出会いって、ありがたいと思いましたね」
サワイ「いやでも、ふみちゃんこそ、この厳しい芸能界で長く活動しているので知識豊富で、それなのにストイックで、私のほうこそ話を聞く側として吸収したものが多かったです。辞書みたいな存在で」
二階堂「それは言い過ぎです(笑)」
■「日本から来たスタッフと海外のスタッフの融合がおもしろかったです」(二階堂)
――日本が舞台の歴史ものをカナダで撮影したわけですが、特別な経験になりましたか?
二階堂「最初にセットを見学に行った時、そのスケール、大きさに息をのみました。ケータリングのキッチンカーで、常に温かくて美味しいスープが飲めたりして、そんな細かい気遣いにも感動したりして(笑)。ひとつのシーンを作り上げるうえで、私たちやスタッフの努力や手順はこれまでの作品と変わらないと思いますが、撮り方が違ったり、日本から来たスタッフと海外のスタッフの融合がおもしろかったですね」
――具体的にどんなふうにおもしろかったのですか?
二階堂「自由にクリエイティブしつつ、時代考証とのバランスを見極めながらキャラクターを完成させた感じです。髪飾りにしても『えっ、これは斬新!』というアイデアを出してくださったり、そのセッションする感覚はおもしろく、新しい経験でした。クリエイティブな現場は自由でいいんだと再認識できましたね」
――ハリウッドの現場を経験してきたサワイさんは、その点についてどう感じましたか?
サワイ「私の場合は、ふみちゃんのように『こうあるべき』という時代劇を経験していなかったので、現場のスーパーバイザーや専門家の方々の指導に従った感じです。時代考証もありますし、気軽な感じで『こうしてみよう』とはできないので、準備が綿密になされた印象です。私は時代劇の所作や着付けも初めて。歩き方はもちろん、鞠子は英語のセリフもあるので話し方もかなり練習を積みました。現場には日本のクルーの方も多く、通訳の時間もあったので、じっくり作品がつくられたのではないでしょうか」
■「日本人の私がどう思えるかと聞かれたら、満足できる作品になったと言えます」(サワイ)
――この「SHOGUN 将軍」が日本の人たちにどう受け止められると思いますか?
二階堂「それはいまも私がずっと頭の中で考えていることなんです。アンナちゃんはどうですか?」
サワイ「私は海外の日本人も関わった作品に何度か携わってきて、常に『どこか違うな』という感覚が付いて回っていました。それを繰り返したくなかったんです。『SHOGUN 将軍』も正直、最初はまた同じ気持ちになるかもと思ったのですが、ジャスティン(本作のエグゼクティブ・プロデューサーであるジャスティン・マークス)から『日本の人が誇りに思える作品にしたい』と聞かされ、希望を感じました。さらに現場に入ったら、多くの日本人の方が、いい作品を目指して闘っている姿を見て、私自身も誇りに感じたのです。日本人の私がどう思えるかと聞かれたら、満足できる作品になったと言えます」
二階堂「海外の人による外の視点と、日本人が肌で感じることや日本人として受け継がれてきたこと。その両方が感じられる作品になったと思います。10か月も作品に関わったアンナちゃんの話を聞いて、いろいろな場面で“希望”が見いだされたことを実感しました。この作品を観て、日本にリスペクトを持ってくれる方もまた増えるでしょうし。そんな希望的作品の最初の一歩になったと思います」
取材・文/斉藤博昭










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN