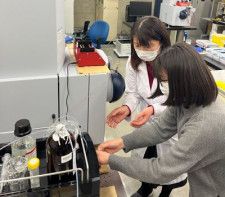政府は国際卓越研究大学で議論されてきた合議体の対象を拡大する国立大学法人法改正案を閣議決定した。今後、国会で審議する。私立大学と異なり国立大では、中期目標・中期計画や予算・決算など重要な案件が、現状では学長一人で最終決定できる状況にあるためだ。規模で上位の東京大学、京都大学、東北大学、大阪大学、東海国立大学機構は必須とする。その他の導入も可能で、2024年度以降の国際卓越大への再申請をにらむ国立大に広がりそうだ。

合議体となる「運営方針会議」は、国立大が産学連携やスタートアップ(SU)創出、財源多様化などで事業成長する上で、ステークホルダー(利害関係者)となる外部人材など委員3人以上と、学長で構成する。国際卓越大でガバナンス強化の仕組みとして議論され、認定要件となっていた。今回、事業規模が特に大きく「特定国立大学法人」となる大学は、認定によらず設置とする。
通常の国立大における「中期目標への意見と中期計画の作成」「予算と決算の作成」は、学長と理事で構成する役員会が審議し、学長(法人の長)が決定する。法的には審議結果と異なる決定も学長独断で可能だ。しかし外部資金が大きい大規模大学においては、学長交代による方針転換を含め社会的影響が大きい。そのため同会議で組織的に意思決定をする。
同会議は運営の監督や学長選考での意見も行う。施行は24年10月1日の予定。私立大では同様の制度がすでにあり問題ない。同会議設置の国立大には規制緩和で独自基金の繰り越し協議を適用除外とし、投資・運用のチャンスを逃しにくくする方針だ。
また今回の法改正では、全国立大学法人における長期借り入れや債券発行の要件を緩和。ハードの建物だけでなく、ソフトの研究プロジェクトにも使えるようにする。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN