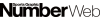「自然とワクワクした気持ちにあんまりならないんです。だから、オリンピックに出たいとかはないんですよね」
箱根駅伝“史上最高の2区”との呼び声も高かった2023年、99回目の箱根路。
その立役者のひとりが当時、青学大のエースだった近藤幸太郎だった。田澤廉(駒大→トヨタ自動車)、吉居大和(中大→トヨタ自動車)の2人とエース区間で繰り広げた3つ巴の区間賞争いは、駅伝ファンの記憶に強く刻まれたシーンのひとつだ。
そんな学生陸上界のエースは昨年、実業団のSGホールディングスへと活躍の場を移した。
今年1月のニューイヤー駅伝では2区を走り、初出場ながら18人抜きの快走。早くもチームのエース格としての立場を揺るがないものにしている。
そんなトップランナーが口にした冒頭の言葉は、これまでの陸上競技者のステレオタイプで考えれば意外なものだということになるのだろう。
「箱根から世界へ」という大会スローガンのもと、箱根路で活躍したエースたちの多くは、卒業後、オリンピックや世界陸上といった大舞台を目指すケースがほとんどだったからだ。実際に近藤と2区で争った田澤と吉居は、実業団入社の際に「世界の舞台で活躍することを目標に」と明言している。
「箱根→世界を目指す」は絶対なのか?
一方で、この近藤の言葉に同調したのは今年1月の箱根路で4区区間賞を獲得し、青学大優勝を決定づけるキーパーソンにもなった佐藤一世だ。この春からは近藤と同じくSGホールディングスに所属している。
「まずビジョンが見えない。ちょっと遠すぎて。もっと強くなっていけば自然とそういう目標も出てくるのかもしれませんけど……割と自分が現実主義者なのもあるのかもしれませんが」
2015年からの箱根駅伝4連覇をはじめとして、青学大の姿は近年、常に大学駅伝シーンの中心にあった。チームを率いる原晋監督のメディア映えするキャラクターも含めて、箱根駅伝人気をそれまでより1段階引き上げる立役者となったことは間違いない。
その一方で、箱根路で選手たちが活躍すればするほど、その後の世界大会で「日の丸を背負ったOB選手がいない」ことを指摘する声もSNSなどで大きくなっていた。
ただ、言葉を選ばずに言えば、箱根駅伝は1大会で200人以上が出場する関東のローカル駅伝である。当然のことながら、そのランナーがみな卒業後に世界を目指す必要はないはずだ。それはエース格の選手だろうと同じことだろう。
それでも大会そのものが持つ注目度の高さ、規模の大きさゆえ、多くの人たちにとって「箱根路で活躍したエース=次は世界大会を目指すべき」というイメージが出来上がってしまっているのが実情なのかもしれない。
最後は「選手個人のスタンス」次第?
そんな空気感は十分に理解しながらも、近藤は自身の考え方をこう語る。
「大学に入るときから『世界を目指したい』という気持ちが強い子は駒大とかにいくだろうし、箱根駅伝含めて駅伝が好きで、駅伝に勝ちたいという子は僕らみたいに青学を選ぶ。それだけの問題だと思うんですけどね」
佐藤も近藤の主張に賛同する。
「それは原監督云々とかあんまり関係なくて。僕はどこの大学に行ったとしても、同じような気持ちだったんじゃないかな。そこはもう個人次第ですよね」
2人がともに強調したのが「そもそも陸上競技ではなく駅伝が好き」というスタンスだ。
愛知県出身で中日ファンの近藤が「普段は陸上よりも野球を見るのが好き」と言えば、佐藤も「卒業旅行でイギリスに旅行し、プレミアリーグの試合を観戦した」ほどのサッカー好きなのだという。近藤が続ける。
「結局、駅伝はやっぱり別物なんですよ。今年の箱根は『駒大が大本命』と言われる中で青学が総合優勝しましたけど、駒大は色んなプレッシャーもあっただろうし、そういう面では青学の方が有利だった。“2年連続3冠”を目指すというのは、ものすごい重圧だったと思うので、そこはやっぱりチャレンジャーの方が強いですよね」
裏を返せば「チームとしての駅伝の強さと、ランナーとしての個人の強さの足し算」はやはり異なるということなのだろう。
青学大と駒大ではそもそものアプローチが異なる
近藤と佐藤が口をそろえたのは、「駅伝で活躍することを目標に掲げて、目の前の課題をひとつずつクリアしていった結果として学生トップクラスの走力がついた」ということだ。それは「世界で戦う」という目標を据え、最初からそこに向かって計画的にトレーニングし、走力を伸ばそうとする駒大のような大学とはアプローチの根本が異なる。
ただ、それはどちらが良いという話でもないだろう。高すぎる目標は時にモチベーションの低下も生む。「世界」を目指すことが、必ずしもすべての箱根ランナーにとって正解というわけではないのは自明のことだ。
今は「オリンピックに出たいとは思わない」という2人だが、まだ社会人1年目と2年目の若手でもある。
大学時代と同様に、一段ずつ階段を上っていった結果として、一番高いところが見えてくる可能性はもちろんあるはずだ。現に佐藤は「マラソンに興味がある」と言い、近藤は「マラソンは走りたくない」と嘯きつつも、オリンピックのマラソン代表選考レースである「MGCには出てみたい」と漏らしていた。
2人の根底には、自分を育ててくれた陸上界、駅伝界に「何かを残したい」という想いもあるという。
「世界で活躍するスター選手になって、子どもたちに夢を与える」ことはもちろんそのひとつ。だが、逆に言えばそれ以外にも陸上界に自身の経験を還元する方法はいくらでもある。
例えば近藤も佐藤も、現役引退後の指導者という道には「興味がある」と言う。
「今までやってきたことを誰かに教えられたら、伝えていけたらなという風には思っています。でも学校の先生とかは確実に向いていないので(笑)、クラブチームの指導者とかには興味があります」(佐藤)
「大学も面白そうですけどね。運営管理車、一度乗ってみたいんですよ(笑)。あとは個人でトレーナーとかもやってみたいです」(近藤)
有力選手であればあるほど、現役時代はその後のセカンドキャリアに想いを馳せることは少ない。一方で、青学大OBの2人はすでに具体的なキャリアプランも描いていた。そんなところにも2人の「リアリスト」な一面が見て取れた。
青学大の強さの秘訣は「現実主義」にアリ?
一見すると明るく夢想家。端的に言えば「陽キャ」なイメージが強い青学大駅伝チーム。だが、OBの元エース2人の話から見えたのは、その超リアリスティックな一面だ。
きっとその「現実主義」は、近年の青学大の駅伝における圧倒的な強さとは無関係ではない。自分を客観視し、過剰な目標を立てることをしない。その代わりに人目を引く「大作戦」の発令は、原監督の得意技でもある。
目の前の課題をひとつずつクリアしながら、できることを積み上げていく。過去のエースたちが積み重ねたその小さなひとつひとつが伝統となり、現在の「青学イズム」は生まれているのかもしれない。
文=山崎ダイ
photograph by Yuki Suenaga










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN