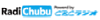中米にあるパナマ運河が通行の危機に直面しています。その原因は水不足。パナマ運河は水路に多量の水を投入して、高さの異なる場所へ船舶を移動させるので、水がなければ通行できません。 もし運河が通行できなくなると、世界中の物流に悪影響が出ると見られています。 5月13日放送の『CBCラジオ #プラス!』では、CBC論説室の石塚元章特別解説委員がこのニュースを解説しました。
最初はアメリカのものだった
パナマ運河は、太平洋と大西洋を中央アメリカのもっとも細い部分を貫いて結ぶ重要な運河。東西の海を繋ぐ運河ですが、地形の関係で南北に延びています。
スエズ運河を完成させたフランス人のレセップスがパナマ運河の建設に着手しましたが、難工事のため失敗。その後アメリカが工事に乗り出し、1914年(大正3年)に完成させました。
この工事には、日本人技術者の青山 士(あきら)さんも参加しています。その後青山さんは、東京の荒川放水路づくりでも活躍したそうです。
アメリカはパナマの独立をバックアップする代わりに、運河をアメリカのものにする条約を締結しました。しばらくの間、パナマ運河はパナマにありながら、アメリカのものだったのです。
1977年、アメリカはパナマ運河をパナマに返還し、現在は「パナマ運河庁」が管理しています。
大量の水が必要な理由
パナマ運河は、海抜26メートルの山越えが必要な地形の複雑さと、大西洋と太平洋の海面の高さの違いから、閘門(こうもん)式を採用しています。
これは、ゲートを開けて船を入れて後ろのゲートを閉め、そこに水を流し込むことで水面と同じ高さまで上げ、前のゲートを開けて船を前に進ませ、後ろのゲートを閉めるという方法です。
この方式は名古屋にもあります。水面の高さが異なる「堀川」と「中川運河」を船で通航できるようにゲートを両側に作った「松重閘門」です。
しかしこの方式には水が大量に必要。
パナマ運河の閘門システムのための水源は人口湖・ガトゥン湖ですが、降水量の減少によりその水位が低下し、十分な水がなくなってしまっているのです。
パナマ運河が水不足で通行の危機に瀕しているのは、これが理由です。
住民も使う水
海水は生態系への影響や塩害の恐れがあるため、閘門システムには淡水しか使えません。
パナマ運河庁は、船の数を減らす、船を数艘ずつまとめてゲートに入れるなどの工夫を行っているということです。
この問題をさらに複雑にしているのは、ガトゥン湖の水を運河だけでなく、周辺住民が生活用水にも使っているということ。
少ない水の割り振りもパナマ政府にとって大変なジレンマ。住民も大切ですが、パナマ運河を通る船から上がるお金は、国家にとってかなりの収益になっているのです。
先日行われたパナマの大統領選挙でも、これは争点のひとつだったそうです。
二大運河が同時に抱えるリスク
スエズ運河はイエメンの反政府勢力・フーシ派による船舶への攻撃のため通れず、多くの貨物船はアフリカ最南端・喜望峰経由のルートに変更しています。
5月の降水量が少ない場合、パナマ運河を通れる船もさらに少なくなってしまいます。
このように世界の二大運河が同時にリスクを抱えていたことは、過去にない事態です。
世界の物流の8割は船。パナマ運河を使っている国は、アメリカ、中国に次いで日本が3番手です。
LNGやLPGといったガスや穀物は、パナマ運河を通って日本にやってきているので、日本への影響もかなりあると考えられます。
物流コストがかかると、物価の上昇にも繋がります。
パナマ運河と聞くと遠い国の話のように思いがちですが、実は我々日本人の暮らしにも影響を与える可能性があるということです。
(minto)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN