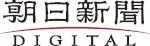「控訴を棄却する」
裁判長が主文を言い渡すと、女性(54)は両手の拳を強く握りしめた。憲法25条は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障している。それが脅かされたとき、裁判所が憲法のとりでとして守ってくれると、弁護士から聞いていたのに――。
国が2013〜15年に行った戦後最大の生活保護基準額の引き下げを巡り、受給者が違憲だと訴えた裁判。大阪高裁は4月、減額取り消しを求めた原告の訴えを退けた。女性も原告だった。
2人の子どもを育てるシングルマザーの女性が生活保護を受け始めたのは2010年だった。夫と離婚し、複数の飲食店や医療事務の仕事をかけ持ちし、昼も夜も働きづめになった。盆も正月もなし。過労で倒れた。
知人からは「休んで生活保護を受けなよ」と何度も勧められた。でも、「もうちょっと頑張れる」と無理をした。支援を受けることに、少し恥ずかしさもあった。
ただ、当時90代の父は認知症が進んでいた。母は足が悪い。無理をした体に介護が重なった。生活保護を受けることにした。
周囲の目は冷たかった。医療機関で働いていた時、看護師たちが、ある患者について「(生活)保護で来てんねんから」と陰でからかっていた。
保護基準引き下げの影響を痛感したのは、娘が中学に入った頃だ。
ある日、娘が泣きながら帰ってきた。お気に入りだった筆箱を見た同級生に「それ、百均やん」と言われた。娘は「貧乏をからかわれた」と感じた。いじめも重なり、不登校になった。高校1年で学校をやめ、以来4年間、家から出ることがなくなった。
娘は数年前、かかりつけの心療内科の医師から、躁(そう)と鬱(うつ)を繰り返す双極性障害と診断された。リストカット、オーバードーズ(薬の過剰摂取)。何度も自殺未遂を繰り返した。
今は息子が独り立ちし、20歳になった娘と2人暮らし。買い物に行くたびに物価高を感じる。卵はかつての倍の値段になった。入浴は2〜3日に1回だけ。食事も1日2回。もともと食が細い娘は夜1回しか食べない。
世の中は大型連休だが、「子どもと旅行なんて行ったこともない」。憲法がうたう「健康で文化的な最低限度の生活」とはいったい何なのか。いまは疑わしく感じている。(大滝哲彰)
【25条 生存権】すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN