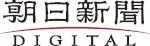盛岡藩の殿様は持病の痔(じ)の治療のため、四斗樽(だる)(約72リットル)で約1カ月に7回も温泉を取り寄せていた――。岩手、秋田、青森にまたがる盛岡藩の湯治事情に焦点をあてたユニークな企画展が、盛岡市のもりおか歴史文化館で開かれている。
7月7日まで開かれている「We Love 温泉!!―盛岡藩の湯治事情―」。学芸員の小原祐子さんが同文化館が所蔵する南部家関連の約6万件の史料を中心に、温泉や湯治をキーワードに史料を探し回った。
盛岡藩の領地は奥羽山脈に沿って至る所で温泉がわき出ていた。小原さんによると、南部家が統治していた江戸時代、藩主が領地内を視察する際は、温泉、湯治がセットになるケースが多かったという。
温泉好きな大名として有名だった3代藩主南部重直(しげなお)は盛岡でも江戸でも温泉を楽しみ、記録で確認できるだけでも、箱根(神奈川県)や那須・塩原(栃木県)、熱海・伊東(静岡県)に出かけていた。
8代藩主利視(としみ)は2週間かかさずに繫(つなぎ)温泉(盛岡市)に日帰りで通っていたほか、片道13日もかかる下風呂(しもふろ)温泉(青森県風間浦村)に湯治に出かけた記録(屋形様田名部下風呂御湯治之記)が残っている。下風呂の湯治旅は1カ月にも及び、道中で大湯温泉(秋田県鹿角市)にも入湯したという。
利視は1745年、領地内の温泉の名称や規模、立地、入湯者の有無を報告するよう調査を指示。さらに湯治客に聞き取りして温泉の効果まで報告させている。
旅先で藩主が温泉に入る場合、専用施設がないときは湯治用の湯小屋を建てるケースが多かったという。専用の木の浴槽は持参。15代藩主利剛(としひさ)が大湯温泉を訪れた際、4・7メートル×3・2メートルの湯小屋を準備した。
「痛所」があった利剛は温泉療養を幕府に願い出て、鉛(なまり)温泉(岩手県花巻市)に計3回、湯治に出かけた。ある1日、利剛は午前7時、正午すぎに入湯、マス釣りを楽しんだ後、午後5時にも温泉に入ったという。
側役(そばやく)が日々の出来事を記した「御側留帳」によると、9代藩主利雄(としかつ)は1753年、持病の痔を発症し、治療を始めた。約1カ月にわたって鶯宿(おうしゅく)温泉(岩手県雫石町)から温泉を取り寄せ、治療にあたった。馬を使い、12個の四斗樽を盛岡に運んだ。利雄は毎日入湯し、多い日は5回も入った。温泉効果もあり、痔はほぼ治ったという。
小原さんは「改めて湯治、温泉をキーワードに史料を見直すと、様々な発見があった。湯治を絡めた視察も多かった。まさか自分の痔の治療についての記録が後世に展示されるとは、藩主も想像していなかっただろう」と話した。
6月2日、7月6日に会場で学芸員が展示に関する質問を受け付ける。問い合わせは同文化館(019・681・2100)。(佐藤善一)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN