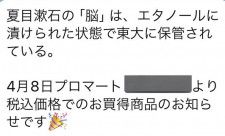西暦1867年2月9日、旧暦の慶應3年1月5日は、日本を代表する文豪・夏目漱石の誕生日である。また2月21日が「漱石の日」となった理由は、1911年のこの日に文部省(現:文部科学省)から送られる「文学博士」の称号を辞退したからだ。「自分に称号は必要ない」という理由はまさに芸術家とも言えるが、そんな文豪が生涯の伴侶とした女性はその真逆、芸術を解さない“悪妻”だったという説が定着している。果たして実際はどうだったのか?
(「新潮45」2006年4月号特集「明治・大正・昭和 13の有名夫婦『怪』事件簿」掲載記事をもとに再構成しました。文中の年齢、年代表記は執筆当時のものです。文中敬称略)
***
今に残る悪妻エピソードの数々
夏目漱石の妻、鏡子夫人は本当に悪妻だったのだろうか? 伝えられる鏡子像を集めると、やはり悪妻のイメージを反映するようなエピソードに満ちている。
鏡子が夏目漱石と結婚したのは、明治29年。漱石が30歳、鏡子が20歳の時である。漱石は当時、松山中学から熊本の第五高等学校の教授へ移ったばかりだった。漱石は当初、鏡子に俳句をつくらせたり本を読ませたりしたが、鏡子が文学にまったく関心を示さなかったため、早々にさじを投げてしまった。
漱石の仕事に関する無関心ぶりは、終生変わることがなかったようだ。初の新聞小説である「虞美人草」を連載中の頃、漱石は門下生に宛て、「善くても悪くても本当に読んでくれゝば 結構。僕ハウチノモノガ読マヌウチニ切抜帳へ張込ンデシマウ。ワカラナイ人ニ読ンデモラウノガイヤダカラデアル」という嘆きの書簡を送っている。
朝に弱い体質も
結婚して始めてわかったのは、鏡子が朝寝坊という悪癖を持っていたことだった。もともと鏡子は、士族の父を持つお嬢様育ちで(結婚時父親は貴族院書記官長の地位にあった)、家事は不得手であり、漱石に朝食を出さないで出勤させることも多かった。事実、漱石は大正3年の日記に「妻は朝寝坊である。小言を云ふと猶起きない、時とすると九時でも十時でも寐てゐる」と記している。
これに関して鏡子は後に「漱石の思い出」という回顧録の中でこう弁解している。
「朝早く起こされると、どうも頭が痛くて一日じゅうぼおっとしているという困った質(たち)でした。新婚早々ではあるし、夫は早く起きてきまった時刻に学校へ行くのですから、なんとか努力して早起きをしようとつとめるのですが、なにしろ小さい時からの習慣か体質かで、それが並みはずれてつらいのです」
この新婚の熊本時代、鏡子は初子を流産したためヒステリー症が激しくなり、漱石は夫人の扱いにほとほと手を焼いていたという。
英国留学の間は手紙を出さず
漱石が鏡子夫人への嫌悪感を募らせたのは、明治33年からの英国留学の間だったといわれている。英国へ着いた漱石がいくら手紙を出しても、鏡子からの手紙がなかなか来ない。第2子が生まれるはずであり、名前まで考えているのに、生まれたか生まれないかの便りもない。漱石は鏡子宛ての手紙にこう書いている。
「国を出てから半年許りになる 少々厭気になつて帰り度なつた 御前の手紙は二本来た許りだ 其後の消息は分らない 多分無事だらうと思つて居る 御前でも子供でも死んだら電報位は来るだらうと思つて居る」(明治34年2月20日付けの手紙より)
漱石がロンドンで神経衰弱に陥った原因は、異国の夫に面倒がって手紙すら出さない鏡子の思いやりのなさにあるというのが定説にもなっている。
とにかく鏡子夫人に関しては、芸術家を支える内助の功とか、良妻賢母という言葉からは程遠い評価がつきまとっている。一言でいえば気の利かない“きつい女”で、何事にも堂々と自分を主張する性格で、女ゆえに遠慮しなければという古風な考えを持ち合わせていない。経済的にも淡泊で、外聞も気にせず質屋通いをする一方で、金があるときには乱費してしまう。夫の作品を理解しない世俗的な女で、夫の苦悩や芸術における葛藤などには無関心である、等々。
「漱石文学」は悪妻から生まれた?
漱石の自伝的小説といわれる「道草」には、こんな一説がある。
「夫と独立した自己の存在を主張しようとする細君を見ると健三はすぐ不快を感じた。動(やや)ともすると、『女の癖に』という気になった。それが一段劇しくなると忽(たちま)ち『何を生意気な』という言葉に変化した。細君の腹には『いくら女だって』という挨拶が何時(いつ)でも貯えてあった」
寄り添って暮らしながらも、相容れず不平不満を募らせるばかりの夫婦。この文豪の悲惨な夫婦生活に関して、ある近代文学研究者は次のように記している。
「漱石が、いわゆるその理想の夫人をめとったならば、漱石はあるいはこれほどの暗たんとした人生観に追いこまれなかったにちがいない。しかし、われわれは漱石が理想の夫人をめとらなかったがゆえに、近代人の苦もんをあのようにみごとに文章に彫刻したすぐれた漱石文学を持ち得たのだともいうことができる」(早稲田大学教授・川副国基「マドモアゼル」1961年1月号より)
「夫は世界一の男」
このような悪評がある一方で、漱石の創作を陰で支えていたのは、他ならぬ鏡子夫人だったという説もある。漱石研究の著作が多い作家の長尾剛氏は、夏目夫婦はむしろ非常に仲が良かった、と主張する。
「漱石の教養に鏡子がついていけなかったという面はありましたが、人格の高潔さという点では2人はすごく似ていたのです」
漱石にしてみれば、鏡子の遠慮なくずけずけ言う性格を、むしろ“正直という美徳”として評価していた。そもそも漱石が結婚を決意したのも、見合いの席で鏡子が、歯並びが悪くてきたないのに、それを強いて隠そうとしないところが気に入ったからだという。漱石が惹かれたのは、鏡子の正直な人柄だった。家事が上手いとかの現実的な要素でなく、もっと根源的な人間的な清らかさが漱石には大事だったというのである。
漱石門下は「木曜会」と称して、毎週木曜日に夏目邸に集まり、漱石を囲んで話しをするのが習慣だった。鏡子は不器用ながら面倒見のいい性質で、漱石を慕って集まる弟子たちを我が子のように可愛がっていたという。その献身ぶりも、漱石にとっては有り難かったはずだった。
鏡子だからこそ可能だった漱石との対峙
さらに漱石自身の抱えていた病、神経衰弱の問題がある。とくに英国留学から帰国した数年がひどく、漱石は誰かに監視されているという妄想を抱き、たびたび激しいかんしゃくの発作を起すため、周囲のものたちが漱石を恐れて近づかない時期があった。
この時期、妊娠して悪阻のひどかった鏡子は、一時実家に身を寄せている。周囲の人たちからは漱石との離婚を暗に勧められたが、鏡子は断固としてこれを受け入れなかった。
「私が不貞をしたとか何とかいうのではなく、いわば私に落度はないのです。なるほど私一人が実家へ帰ったら、私一人はそれで安全かもしれません。しかし子供や主人はどうなるのです。病気ときまれば、そばにおって及ばずながら看護するのが妻の役目ではありませんか」(「漱石の思い出」夏目鏡子述より)
ある意味で、常人を超えた複雑で深遠な精神を持った漱石との対峙は、ものごとにあまり動じない、男勝りの性格だったという鏡子だからこそ可能だったのかもしれない。
弟子たちが流布させた悪妻説
長尾氏は、鏡子悪妻説は漱石晩年期の弟子たちが流布させたものだという。彼らがあまりにも師匠である漱石を神聖視したために、師匠に見合うだけの教養や深さがなかった鏡子を悪妻と決めつけ、そのイメージを世間に広めてしまったというのである。
「一般的には、自伝的小説の『道草』が引き合いに出されますが、私は『吾輩は猫である』に登場する苦沙弥夫婦こそ、夏目夫婦そのものだと断言します。ほのぼのとしてトンチンカンなやり取りは、2人の生活をそのまま写したものであり、実生活で漱石は鏡子のことをかなり可愛いと思っていたはずです。『猫』には、先生が自分の奥さんをイロっぽい女だと評する場面がありますが、明治時代に夫が妻のことをそこまで言うのは珍しい。
また鏡子も、『私の夫は世界一の男である』と、子どもたちが呆れるくらいに褒め讃えている。晩年の講演旅行の際も、具合が悪かった漱石は看護婦ではなく常に妻を帯同していた。漱石と鏡子は、最後まで惚れあっていた夫婦だったと思います」(長尾氏)
本人たちにしかわからない真贋
漱石の代表作である「坊っちゃん」には「清」という老女中が登場する。坊ちゃんが唯一愛情を覚える「キヨ」はまた、鏡子夫人の戸籍名でもある。かつて英国から鏡子に宛てた漱石の手紙には、こうも記されている。
「段々日が立つと国の事を色々思ふ おれの様な不人情なものでも頻りに御前が恋しい 是丈は奇特と云って褒めて貰はなければならぬ」
悪妻か否かは後世の人々の評価であり、その真贋は本人たちにしかわからない。いずれにせよ最後まで別れず添い遂げたのだから、漱石にとって鏡子が得難い相手であったのは間違いない。
上條昌史(かみじょうまさし)
ノンフィクション・ライター。1961年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部中退。編集プロダクションを経てフリーに。事件、政治、ビジネスなど幅広い分野で執筆活動を行う。共著に『殺人者はそこにいる』など。
デイリー新潮編集部










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN