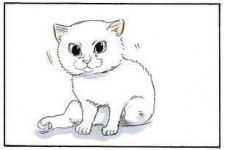猫を5匹飼っていた独居の祖母
2017年、『跡を消す』でデビューした、看護師兼作家の前川ほまれさん。特殊清掃や精神医療などを題材にした作品が次々と話題となり、最新刊『藍色時刻の君たちは』で第14回山田風太郎賞を受賞。そんな新進気鋭の著者が幼き日に東京で顔を合わせていた、道端で手相を占う祖母との少し変わった思い出とは。
***
私は幼少期から宮城県の港町で生活をしていたが、父方の祖母は東京で暮らしていた。私が小学生の頃までは毎年夏休みになると、祖母の家に遊びに行くのが恒例だった。
東京に住む祖母は常に、首輪をしていない猫を5匹以上は飼っていた。なので祖母が着ている服には、いつも猫の被毛が付着していたのを覚えている。当時の私は猫アレルギーがあり、東京の家に着くとティッシュが手放せなかった。鼻は詰まり、喉は痛み、悲しくもないのに涙目になってしまう。私は痒くて仕方のない両目を擦りながら「なんで、何匹も猫を飼うの?」と、聞いたことがある。祖母は「勝手に居着いちゃうのよ」と、眉根を寄せた。祖母はずっと、東京で独居だった。今考えると寂しさを紛らわすように、猫の温もりを求めていたのかもしれない。祖母の家の室外機の上には、煮干しの入った小皿が常に置かれていた。まるで、野良猫を歓迎するかのように。
「おばあちゃんに会いたい」と言うと不機嫌になる父
祖母は、易者として生計を立てていた。会うと必ず、手相を見せてほしいと頼まれた。祖母が手相を見る時に使用する拡大鏡には、持ち手に金色の龍が刻印されていた。毎回じっくりと私の手相を鑑定してくれる割に、漏らす感想はいつも同じだった。
「あんたは、大器晩成だね」
小学生の頃の私は、その四文字熟語を知らなかった。早速意味を問うと「将来が楽しみだ」としか、返事はなかった。しかし祖母は、私の将来どころか中学生になった姿すら見たことがないと思う。いつからか息子(私の父)との関係が悪化し、家族で東京に行く機会が消滅したからだ。何度か父に「東京のばあちゃんに会いたい」と、頼んだことがある。父は「ダメだ。やめとけ」と、不機嫌になるのが常だった。
祖母と何年間も疎遠のまま、私はファッション関係の仕事に就くために18歳で上京した。一度だけ両親には秘密で、祖母の家を訪ねてみたことがある。そこはもう空き家になっていて、猫たちの姿も消えていた。それから月日はたち、私が30歳の時に祖母が既に亡くなっていることを知った。父は現在も、祖母と不和が生じた原因を教えてはくれない。
脳裏で繰り返す「あの四文字」
東京に住むようになってから、街中で易者の姿を見かけることが多くなった。新宿の高架下、池袋の繁華街、上野アメ横商店街の片隅。彼らは「運命」や「姓名」や「手相」の文字が書かれた灯籠を灯し、客が訪れるのを静かに待っている。路上の易者が目に映る度に、私の歩調は緩んでしまう。見知らぬ易者に祖母の面影を重ねながらも、今まで客として占ってもらったことはない。幼い頃に飽きるほど、手相を鑑定してもらったせいだろうか。
易者を素通りして、私は東京の人混みに紛れていく。痒くもない目を擦って、脳裏であの四文字熟語を繰り返しながら。
前川ほまれ(まえかわ・ほまれ)
1986年生まれ。宮城県出身。看護師兼作家。2017年、『跡を消す』でデビュー。最新刊『藍色時刻の君たちは』で第14回山田風太郎賞を受賞。
デイリー新潮編集部










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN