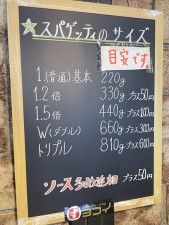【正解のリハビリ、最善の介護】#29
脳梗塞で失語症が残った50代の男性医師、Cさんのお話の続きです。治療後のCさんは、言語療法や理学療法などのリハビリと自主訓練を続け、発症から13日目にリハビリ病院へ転院しました。しかし、転院先の病院で新型コロナ感染症を発症してしまい、脳梗塞の発症から16日目に感染症専門病院に転院することになりました。
Cさんは、リハビリ病院内でコロナ感染したことは残念に思いましたが、一生懸命支えてくれる医療従事者のことを考えると怒る気にはなれませんでした。どこででも、誰にでも起こる感染だからです。幸い、新型コロナ感染症は重症にならなかったので、個室で自主リハビリ訓練を行いました。
理学療法は座ったままこぐフィットネスバイクを30分。室内歩行は1万7000〜2万5000歩を歩きながら徹底的に「考える」ことに挑みました。復職した時の診察場面を想定して、個々の担当患者が受診したらどういう方針で治療するのか、リハビリセンターに戻ったら作業療法をどう取り組み、改善結果を良くするためにどうしたらいいかなどを考え続けたのです。言語療法はプリント問題を解いたり、100マス計算を行いました。そして、10日間の隔離を経て、リハビリ病院に戻りました。
リハビリ病院での訓練は、Cさんのペースと希望に沿って実施されました。理学療法はバイクトレーニングが中心で、心拍数140で30分間の訓練を行いました。言語療法は、言語聴覚士との会話のやりとりが中心でした。作業療法では車の運転のシミュレーションに取り組みました。歩行訓練は3万〜3万5000歩を毎日行い、音楽を聴きながら、今後のことと今の回復を考えて、脳を活動させながら歩く訓練を続けました。
リハビリ病院の入院期間は8日間だけで、自宅退院となりました。もちろん、自宅でもリハビリに積極的に取り組みました。歩行訓練は、毎日1万4000〜2万歩、音楽を聴きながらとにかく考えて歩くことを続けました。趣味の自転車トレーニングは約25〜60キロを1〜3時間で行うと、気持ち良く感じました。水泳も取り入れて2500〜4000メートルを1〜2時間で泳ぎ、読書や将棋なども行い、妻と会話することを日課としました。
■リハビリを自発的に行う“患者の心がけ”
自宅退院から23日目の月初め、Cさんは復職しました。発症から2カ月弱での復職です。Cさんの脳梗塞は重症ではありませんでしたが、Cさん自身が考え実行した“攻めのリハビリ”がなければ、復職には4カ月以上を要したかもしれません。さらに、Cさんは「仕事がリハビリ」と考え、できるだけ患者と会話することを心がけました。職員とも会話をして、気持ちを穏やかにすることを心がけ、積極的にコミュニケーションをとりました。
高次脳機能障害後の復職で大切なことは、日々の気持ちを穏やかにコントロールできることです。毎日、患者の聴診を行って、必ず所見と治療方針を丁寧に説明しました。
一方で、脳血流量を増やすため、有酸素運動に取り組み続けました。晴れている日は毎日、自転車通勤です。走行距離は月平均850キロになりました。水泳は週1〜2回で1時間泳ぎ、泳いだ距離は月平均6000メートルでした。
さらに、常に「学習」することを心がけました。かかりつけ医としての学習や産業医としての学習に励み、歯周病対策や嚥下機能評価のために歯科医との連携にも取り組んだのです。脳梗塞の発症から数年たちましたが、Cさんは元気に医師の仕事を生き生きと継続しています。こんな一生懸命なかかりつけ医に診てもらえる患者は幸せです。
Cさんから学ぶべき点は、「自分が回復するためには、自分の回復に必要なことを自発的に積極的に行う」という“「患者の心がけ」(酒向正春著、光文社新書)”です。攻めのリハビリを自分で計画して、自分で行えたことは、Cさんが医師であるから、という要因が大きいといえるでしょう。しかし、早く回復したい患者にとって、Cさんの患者の心がけには見習う点が多くあります。早く回復するためには、正解のリハビリをあきらめずに続けることが近道なのです。
一方、リハビリを担当する医師や療法士に必要なのは、患者に現在の機能評価と能力評価を正確に伝えて、今後の改善点や変化点を説明して激励することです。そして、困った時にはいつでも相談に乗り、寄り添うことなのです。
(酒向正春/ねりま健育会病院院長)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN