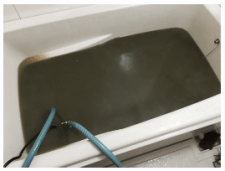皆さんはリモートワーク中、このような悩みに直面したことはありませんか?
・プロジェクトのアイデアが多すぎて、どこから始めればいいのか分からなくなった。
・メールやチャットツールでのコミュニケーションに疲れた。
・電話やビデオ通話がおっくうになった。
これらの感情は「メンタルブロック」につながっていると考えられます。メンタルブロックとは、業務中に行き詰まりを感じ、業務をスムーズに進められない状態のことを言います。
Miroが実施した調査によると、多くのビジネスパーソンが何かしらのメンタルブロックを経験しています。従業員のウェルビーイングに悪影響を与えるだけでなく、企業に数億円規模の時間損失をもたらしている場合もあるのです。
本記事では、働き方の変化によって深刻さを増しているメンタルブロックについて、調査結果を交えて紹介していきます。
●全労働者の約8割がメンタルブロックを経験
Miroでは、メンタルブロックが仕事にどのような影響を与えているかを理解するため、正社員として働く日本の知識労働者、1984人を対象に調査を実施しました。
その結果、調査対象の79%がメンタルブロックを少なくとも年に数回経験していることが分かりました。また「毎日または毎週メンタルブロックを経験している」と答えた人は29%と、約3分の1が高頻度でメンタルブロックを経験していることが明らかになりました。知識労働者にとって、メンタルブロックは当たり前のように起こっているのです。
調査対象者が「経験している」と回答したメンタルブロックのタイプは次の通りです。
・情報収集:必要な情報を適切なタイミングで見つけられない(23%)
・自己検閲:他の人に助けを求められないと感じている(21%)
・成果物への不安:業務が完了してもどのように結果を伝えるか不安になる、または完了したことを伝えられない(19%)
・意識散漫:多くの方向に意識が行きすぎて業務が進まない(18%)
・ツール過負荷:どのツールを使用すべきか分からない(15%)
これらのメンタルブロックが起こるタイミングは、「業務の開始時」(39%)と「業務の中間」(37%)が約7割を占めています。「業務の終盤」で感じる人は10%と少数ですが、注目すべきは、15%が「業務のどの時点でもメンタルブロックが起こり得る」と答えていたことです。
●メンタルブロックによる損失は数億円?
ビジネスパーソンは、メンタルブロックを克服するためにどれくらいの時間を費やしているのでしょうか。尋ねたところ、42%が「週に数時間」と回答し、26%は「1日に数時間」と答えました。驚くべきことに、7%は「1日のほとんどの時間」をメンタルブロックに費やしていたのです。メンタルブロックが従業員の生産性を低下させていることが明らかになりました。
この結果を従業員1000人を抱える企業に置き換えてみると、約半数の従業員が、週に数時間のメンタルブロックを経験していることになります。それぞれの生産性が週に3時間低下していると仮定すると、年間約8000万円の損失が出ています(2023年10月時点の最低賃金全国平均である1004円で算出)。もちろん知識労働者の時間給は最低賃金の数倍と想定されるため、実際の被害額は数億円に上ると推測されます。
●メンタルブロックは仕事、組織への不信感にもつながる
メンタルブロックは損失を生んでいるだけでなく、組織や自己に対する不信感、燃え尽き症候群の一因となり、組織の健全な業務遂行を妨げる可能性があります。
メンタルブロックに起因する感情として知識労働者は「不安」(49%)、「イライラ」(41%)、「心配」(39%)を感じることがよくあり、個人レベルでは次のような調査結果が見られました。
・メンタルブロックに対応するより良い方法があってほしいと願う(55%)
・今手元に持っているプロジェクト/タスクの価値を疑ってしまう(36%)
・適切な上司を持っているか疑ってしまう(35%)
・気疲れしてしまう(30%)
・自分自身を疑ってしまう(29%)
・インポスター症候群※1の一因になる(28%)
※1インポスター症候群:成功や成果に関わらず、自分がそれに値しないと感じる心理状態
上記の結果から見て取れるのは、メンタルブロックを対処する方法に苦悩している知識労働者が多いことです。特に注目すべきは、「プロジェクトやタスクの価値を疑ってしまう」「適切な上司がいるのか疑問に思う」といった、組織に対する不信感が上位にある点です。4番目以降の回答には、従業員の健康状態に悪影響を及ぼす可能性のある要素が含まれています。企業にとっても従業員にとっても望ましくない障害の発生を示しており、組織的に早期の対応を検討する必要があるでしょう。
また、調査対象者の88%が、メンタルブロックが仕事のパフォーマンスに与える影響を懸念しています。その中で、34%がメンタルブロックによって怠惰または仕事が遅いと感じられることを、27%が業務の遅延を、24%が自身の評価に影響することを心配しています。
●チーム構成とコミュニケーションが鍵
メンタルブロックの対処方法について聞いたところ、回答者の39%が「休息をとる」と回答し、28%が「同僚と話をする」と答えました。しかし先の項目で、55%が「メンタルブロックに対処するより良い方法があってほしい」と願っており、現在のアプローチでは不十分であることが分かります。では、知識労働者はどのようにしてメンタルブロックをより効果的に克服できるのでしょうか。
調査結果から考えるに、メンタルブロックへの対処法として、チーム構成を再検討することが有効であるようです。
メンタルブロックが発生する場面を尋ねたところ、「企業のリーダー格となる人との業務」(38%)、「単独プロジェクト」(38%)が特に多くなりました。一方、「自身のチームメンバーとの共同作業」においては27%でした。
明確なコミュニケーションとリソースへのアクセスは、業務の円滑化にもつながります。前述の通り、メンタルブロックは情報収集の段階で特に発生しやすく、「理解できないプロジェクトに取り組んでいるとき」(58%)、「自身の担当範囲外の業務にあたるとき」(49%)、「関心のない業務を行うとき」(47%)など、情報へのアクセスがない場合や業務への理解や関心度が薄い際に発生する傾向にあります。
企業の経営層や管理職は、従業員に対して明確な期待値やゴールを設定し、業務フローや業務関連ツール、情報のソースを簡素化するなど従業員がタスクをよりシームレスに進められる環境を構築すべきでしょう。
ここまで、メンタルブロックが企業に与える影響とその解決策を考えてきました。調査結果から見えた知識労働者のメンタルブロックを軽減する方法は次の通りです。
・適切なチーム構成/コラボレーションの設定
・明確なコミュニケーションによる業務への理解度と関心の向上
・革新的なコラボレーションツールによる生産的なワークフローの構築
上記により、知識労働者の業務に対する障壁が軽減され、創造性とウェルビーイングが向上し、組織のイノベーションが促進されるはずです。ぜひ、自社の業務やチームの現状について改めて見直し、メンタルブロックによる損失を軽減していただければ幸いです。
著者:関屋 剛(ミロ・ジャパン合同会社 Head of Japan Sales)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN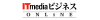






![ライフハッカー[日本版]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/lifehacker/s_lifehacker_2405-3-red-flags-youre-failing-as-a-leader.png)