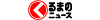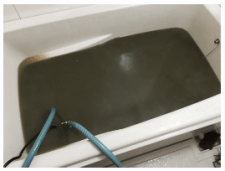時々クルマに貼られている「みどり地に黄色いちょうちょ」のマークについて、SNSなどではさまざまなコメントが投稿されています。
「みどり地に黄色いちょうちょ」 認知は低く…
クルマには、いわゆる初心者マークや身体障害者マークなどの「標識」を貼る場合がありますが、「みどり地に黄色いちょうちょ」というマークもあります。
これについて、SNSなどでは「知らなかった」などの声が多く寄せられています。
初心者マーク(正式には初心運転者標識)や「青地に四葉」の身体障害者マーク(身体障害者標識)は、それぞれ普通免許を受けてから1年経過していない人、肢体不自由を理由に免許に条件が付されている人がクルマを運転する際に表示します。
これらは名称の通り標識の一種であり、周囲の交通に対して運転者の特性を知らせる重要なものであり、義務として標示しなければならないものと、努力義務として表示するように努めなければならないものの2種類があります。
そして「みどり地に黄色いちょうちょ」のマークは、正式には「聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)」といい、聴覚障害者であることを理由に免許に条件が付されている人がクルマを運転する時には、このマークを表示することが義務になっています。
実は聴覚障害を持つ人は、2008年(平成20年)6月1日の道路交通法改正によって、一定の条件の下でクルマの運転をすることができるようになりました。
具体的には、補聴器を用いても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない人が対象で、ルームミラーを通常より視野の広いワイドミラーに変更するとともに、車両の前後に聴覚障害者マークを貼付することで運転が可能になります。
また、2012年(平成24年)4月1日の道交法改正では、貨物車や原付、二輪車の運転も可能になりました。
こうしたことから、聴覚障害者の移動の手段が増え、さまざまなクルマに乗ることができるようになったのです。
一方、聴覚障害者マークを表示したクルマが近くにいる時は、周囲のドライバーは配慮して運転しなければなりません。
踏切や緊急車両のサイレンに加え、警音器(クラクション)などの情報が伝わりにくいため、聴覚障害者マークを表示したクルマが合流や車線変更をしようとしているときは、譲ったり車間を開けるなど、思いやりの気持ちを持つことが大切です。
なお、聴覚障害者マークをつけたクルマに対して幅寄せや割り込みをした場合は、5万円以下の罰金、違反点数1点と普通車では6000円の反則金が科されることとなります。
※ ※ ※
この聴覚障害者マークについて、SNSなどでは「知らなかった」「単なるステッカーなのかと思っていた」といったコメントのほか、聴覚障害を持つとするユーザーからも「初めて知りました」と、標識の存在について知らない人がかなり多いようです。
また、「聴覚=蝶?」「なんで蝶なんだろうか」「これはわからない…」「意味わかりにくいですね」と、聴覚障害者が運転しているクルマであることが伝わりにくいとする意見も多く寄せられています。
2008年の改正から14年が経過したとはいえ、依然としてドライバーへの周知が不足していることに加えて、標識を見ただけでは意味が推測できないという課題も浮き彫りとなり、よりわかりやすい表示への改善が求められています。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN