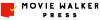『レオン』から30年!最新作『DOGMAN ドッグマン』に見るリュック・ベッソンの進化
■『レオン』から変わらない社会的少数者に対する眼差し
ある夜、血だらけで女装の男、ダグラス(ケイレブ・ランドリー・ジョーンズ)がトラックの荷台に数十匹もの犬を乗せた状態で身柄を確保される。取り調べの過程でダグラスが子どものころ、父親の虐待を受けて犬小屋に閉じ込められて暮らしたこと、女装は別の自分になれる唯一の手段だったこと、体に負った傷は理不尽な暴力と格闘した結果であることがわかってくる。取り調べを担当するのは、離婚した暴力夫の影にいまも怯える精神科医のエヴリン(ジョージョー・T・ギッブス)。ダグラスが自分の過去を包み隠さずエヴリンに話す気になったのは、彼女も同じ傷を持つ身だと直感したからだ。
これは、父親から虐待され、さらにその父親が原因で悪と戦うことになる『レオン』のヒロイン、マチルダ(ナタリー・ポートマン)と、偶然からマチルダを助け、彼女のリベンジに協力することになる孤独な殺し屋、レオン(ジャン・レノ)の関係性に似ている。ダグラスに、女装してキャバレーの舞台に上がるチャンスを与えてくれる、同じ店で働くシェールやマドンナを装う心優しいドラァグクイーンたちを加えると、よりいっそう、ベッソンの社会的少数者に対する眼差しが際立つ。そこに30年という月日の流れを感じないではいられない。
■スピーディで無駄がなく、かつユーモアも忘れないアクション
アクションシーンの処理は相変わらず手早い。特に、ダグラスが罪もない街の住人たちを苦しめるギャング一味と対決する際、自分は父親から浴びた銃弾による影響から車椅子に座ったまま、犬たちに実働を指示するシーケンスは無駄がなくスピーディだ。影では犬の調教を受け持つ15人ものドッグトレーナーのバックアップがあったらしいが、緊迫したシーンでもユーモアを忘れない監督としてのスタンスはベッソンならでは。また、ダグラスが初めてキャバレーのステージに立ち、舞台袖で見守る仕事仲間やほろ酔いの観客たちを熱狂させるのは、フランスの国宝、エディット・ピアフそっくりのパフォーマンス。その瞬間、荒れ果てた街にフランスの香りが漂う。それもまた、ベッソンが本作に仕込んだスパイスと言えるのではないだろうか。
■『DOGMAN ドッグマン』はフランス映画とアメリカ映画に精通した“らしい”作品
物語の舞台はアメリカ、ニュージャージー州のニューワーク。ニュージャージーはエリア・カザン監督、マーロン・ブランド主演のマスターピース『波止場』(54)からジム・ジャームッシュの『パターソン』(16)まで新旧の名作が撮影された場所だ。劇中には、一瞬だが木造住宅が建ち並ぶ街から臨むハドソン川越えの摩天楼が印象的に挿入される。ベッソンがこの地域にカメラを据えるのは、『マラヴィータ』(13)以来、約10年ぶり。『レオン』以来、30年ぶりになる。
映画界にデビューしてからおよそ40年、その間、脚本と製作を担当した作品を含めると90本近い作品を発表し続けてきたベッソンだが、その作風はいつも“ハリウッド的”と評されてきたものだ。キャリア初期の監督作『サブウェイ』(85)や『グラン・ブルー』(88)で見せた実験的な映像から、“ヌーベルバーグ”と比較して“ニューウェイブ”と評されることに反発し、かといって、ハリウッドに軸足を置くこともなかったベッソン。最新作はフランス映画とアメリカ映画の両方に精通した、彼らしい作品とも言えるのではないだろうか。
■次回作『Dracula - A Love Tale』にもケイレブ・ランドリー・ジョーンズを起用
ダグラスを演じるのは『ニトラム/NITRAM』(21)で実際に起きた銃乱射による大量殺人事件の犯人を演じたケイレブ・ランドリー・ジョーンズ。そこはかとなく漂う退廃感とジェンダーレスなムードはまさに適役で、ベッソンは次回作としてすでに発表されている『Dracula - A Love Tale(原題)』のタイトルロールをジョーンズに打診し、作品は製作準備段階にある。新たな鉱脈(主演スター)を掘り当て、リュック・ベッソンの米仏的な映画作りは新たな段階へと入っていくのだろうか。
文/清藤秀人










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN