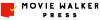藤井道人監督がミューズ・清原果耶に託した”理想のヒロイン”「アミには僕自身の憧れを投影している」
■「アミとジミーのそれぞれの旅の持つ意義などは映画オリジナル」(藤井)
――グァンハンさんと台湾プレミアに参加されていましたが、現地の反応はいかがでした?
清原「黄色い歓声がすごかったです。『観たよ』『大好き!』とストレートな言葉を投げかけてくださるので、『頑張った甲斐があったな』とうれしさが胸に込みあげました」
――滞在中、台湾メディアの取材も受けられたそうですが、どのような雰囲気でしたか?
清原「記者の皆さんのパワフルさに圧倒されました(笑)。合同取材の席でも、『あの場面ってどうなの?』『え〜そうなんだ!』『これも聞きたいから聞いていい?』といったように、ある媒体の記者さんの質問を皮切りに、ほかの記者の方々も次々と話に乗っかってきて、仲の良い友人同士で話しているかのようなフランクなノリで取材されるんです。どんなに際どい質問が飛んでこようが普通に返されているグァンハンさんの横で、『その質問に答えちゃっても本当に大丈夫!?』と、ドギマギしながら取材を受けていました(笑)」
――どんな質問だったのか気になります(笑)。本作は、台湾で話題を呼んだ紀行エッセイ「青春18×2 日本慢車流浪記」にインスパイアされ、人気俳優でもあるチャン・チェンさんが映画化を企画、藤井監督が脚本も担当されたそうですね。それぞれの役柄の細かい設定については、藤井監督ご自身が映画ならではの脚色をされた部分も多いのでしょうか?
藤井「『36歳になったジミーが、18歳の時に出会った初恋の人に会いに行く』という骨子はお借りしつつも、映画化するにあたって独自のアレンジをかなり加えています。バックパッカーのアミがカラオケ店に迷い込んできて、そこでバイトを始めて店が大人気になるところや、18年後にジミーが日本を旅するというエピソードは原作どおりですが、アミのパーソナリティや、大人になったジミーがゲーム会社を起業するくだり。さらにはアミとジミーのそれぞれの旅の持つ意義や、ジミーが道中で出会う人たちとのやりとりなどは、映画オリジナルです」
――ジミーとアミが趣のあるレトロな映画館に、岩井俊二監督の『Love Letter』(95)を観に行くというのも監督のアイデアですか?
藤井「いや、あれは原作どおりですね。僕自身は『リリイ・シュシュのすべて』世代なのですが、原作に岩井さんの映画が出てきたことがうれしかったので、そこはそのまま使いたいなと思って、『Love Letter』にしたんです」
■「ジミーは僕でもあり、アミはかつての理想を投影したところもある」(藤井)
――台湾で映画を撮ることは、台湾にご自身のルーツを持ち、20代のころに留学もされていた藤井監督の夢の一つでもあったそうですが、実際に取り組まれてみていかがでしたか?
藤井「台湾の方たちは本当に優しくて、『やりたいことを言ってもらえれば、実現できるように全力でサポートします』というスタンスでいてくれたことが、僕としてはとてもやりやすくてありがたかったです。ただ、台湾のNo.1とNo.2の日本語通訳さんを僕らが独占してしまったので、ほかのチームからクレームが殺到していたらしいんですけどね(笑)」
――国際プロジェクトにおいては、通訳さんとの相性も非常に重要になってきますよね。本作が“青春映画”であることも、監督にとって大きな意味を持っているのでしょうか?
藤井「自分が36歳の時に、36歳の男性を主人公にした『青春18×2』を撮ることができたということが、個人的にはすごく感慨深くて。言ってみれば、ジミーは僕でもあり、アミは『18歳の僕ならきっとこういう人を好きになるだろうな』との発想から、ちょっとお姉さんだけどキュートな女性という、かつての理想を投影したところもあるんです」
――なるほど。憧れの女性像を監督のミューズでもある清原さんに託されたわけですね。
藤井「そうなんです(笑)。映画のなかの果耶ちゃん、すごくかわいかった!」
清原「…ん?映画のなかの?それは聞き捨てならないな〜(笑)」
藤井「いや、違う違う!そういう意味じゃなくて。アミが。いや、アミを演じている果耶ちゃんが!…って、なんだかどんどん墓穴を掘っているような気もするけど(汗)。なんて言ったらいいんだろう?普段の果耶ちゃんは、アミよりもっとおしとやかというか…」
清原「はい(笑)。藤井さんが言わんとしてることはわかります」
藤井「そうそう。アミは等身大の女性ではあるんだけど、果耶ちゃん本人とは確実に違うので。俳優部ってやっぱりすごいんだなって、改めて実感しましたよね」
清原「確かに、アミはこれまでの2作でご一緒させていただいた役のイメージとは違いましたし、藤井さんの理想が詰まっているのであろう女性を演じることへのプレッシャーもありました」
藤井「いやいや、もちろんこちらだって、『今回お願いしたいのは、相手の男子高生より4つ年上のアミという役なんです』『実は、アミには僕自身の憧れを投影しています』みたいなことを伝えるにあたっては、正直照れくさい部分もありました。でもそれを恥ずかしげもなく言えたのは、気の置けない間柄である果耶ちゃんだからこそ。そこはすごくありがたかったですよね」
――清原さんは、そんなアミ役にどのように取り組まれたのでしょうか?
清原「私自身は喜怒哀楽の表現が激しいほうではないですが、共感することはできたので、アミとして感情を出せるラインがどのあたりまでなのかを見定めながら、ただただ彼女に寄り添うことだけを考えて向き合いました。その場に身を置いて感じることやキャストの皆さんから受け取るものをちゃんと消化したうえで表現すれば、きっと大丈夫だろうなと」
藤井「でも、結果的に今回の現場では、監督として俳優陣に非常に難しい要求をしてしまったんです。というのも、諸般の事情により時系列に即した台湾ではなく、日本からクランクインすることになったので、果耶ちゃんにとってはかなりの地獄だったと思います」
清原「ホントですよ(笑)。普段だったら『なんでそんなシーンから撮るんですか〜!』って、絶対に怒ってます(笑)。現場でも『ここはこういうシーンなので、恐らくこういう感じになる思います』『スミマセン』『よろしくお願いします!』とだけ言って、藤井さんはサーッと遠くに去っていってしまったので(笑)。あえて説明しすぎないで私に任せてくれるのも、藤井さんの優しさなんだろうなと思って。『よし、こうなったら腹を括るしかない!』との想いで初日の撮影に臨みましたね」
――実年齢33歳のグァンハンさんが、18歳と36歳のジミーをとてもナチュラルに演じていたことにも驚きました。
藤井「台湾のスタッフに意見を求めたら、『ジミー役ができるのはグァンハンしかいない!』と激推しされて。いざ会ってみたら本当に若く見えるうえに、すごくナイスガイで」
――清原さんとしても、グァンハンさんが演じる18歳のジミーの4つ上の女性を演じること対する不安はなかったですか?
清原「そこについては特に不安はなかったです。実年齢がどうこうというよりは、精神面の問題だと思っていたので。あまり思い詰めすぎたりすることなく、いま私の目の前にいるジミーとちゃんと向き合えていれば、成立するはずだと思いながら演じた気がします」
■「演じる役柄について考えることこそ役者の仕事における一番のやりがい」(清原)
――資料によれば、監督と清原さんの意見が2か所ほど食い違ったところがあったそうですが。
清原「そうそう!私も『どこのことを言ってるんだろう?』と気になっていたんです」
――監督は、具体的にどんなシーンだったのか覚えていらっしゃいますか?
藤井「えっ!?食い違ったところはなかった気がするけど。ああ、しいて言うなら確か、カラオケのメンバーたちが一緒に食事したあとに、アミがジミーにバイクに乗せてもらうシーンの前の段取りで、『アミは酔いつぶれて寝ているカラオケの店長たちをそのまま置いてまでデートに行ってしまう子なのか?』みたいな話になった気がする…」
清原「ああ、はい。確かに、そういうやりとりはありました。『お金の支払いもあるし、店長をこのままほったらかしにして私たちだけ先にお店を出ちゃっていいの?』って」
藤井「そういうことを果耶ちゃんが言ってくれて、『あ、確かに!』となって、結局ジミーが店員さんに『スミマセン』みたいな感じで、軽く言ってくれたんじゃなかったかな。正直、僕としてはそこについてはまったく考えてなかったんだけど、もしあの時あそこで果耶ちゃんがそういう指摘をしてくれなかったら、アミはもっと気遣いができない子に見えていたかもしれない。僕のデリカシーのなさに起因するやりとりだったように思いますね」
――演じている清原さんは、脚本を書かれた監督以上にアミのことを知っている、と。
藤井「そうです。そこは必然的にそうなりますよね。僕としては『きっとそうであるはず』という感情の流れや身体の動きを設計図として提案することはできるけど、現場で感情を宿すのは生身で演じている俳優さんなので。そこに対する信頼感が僕のなかにありますね」
清原「演じる役柄について考えることこそ役者の仕事における一番のやりがいというか。一番楽しい時間でもあるんです。しかも藤井組では、みんなでその役柄の一生を思い描きながら撮影できるので、監督やスタッフさんたちの意見に耳を傾けながら、私なりにその子のことをとことんまで考え抜いて、身体の中にしっかりと主軸を立てておく。そこが私の頑張りどころだな、と思います」
■「台湾で目にしたモノやコト、出会った人たちに対して抱いたリスペクトの気持ちを忘れずに」(清原)
――非常に興味深いお話ですね。では、改めて「藤井組」初の国際プロジェクトであり、3度目のタッグとなった本作を振り返ってみて、お2人はそれぞれどう感じていますか?
藤井「僕のなかでは、個人的な想いと、社会的な位置づけに対する想いとの二層に分かれているんです。まずは、『僕自身のルーツである台湾で映画を撮る』という、20代のころからの自分自身の目標が達成できたことに対する安堵感。そしてもう一つは、いまこの時代に、旅をテーマにした映画を撮るうえでの社会的意義のようなもの。というのも先日改めてこの映画の企画書を読み直してみたところ、『会いたくても会えない人がたくさんいるこのいまだからこそ』という言葉が目に留まったんです。コロナ禍になり、『会いたい人に会いに行けない』『行きたい場所にも行けない』というもどかしい想いを、世界中の多くの人々が同時に経験したからこそ、『人が旅をする』ということがこれまで以上に大きな意味を持つようになった。そんないまだからこそ、僕らはロードムービーを世界中の人たちに届けたい。そういった想いを、“青春にサヨナラを告げる”36歳の主人公ジミーとアミの物語に重ねながら映画を作れていたんだとしたら、それはとても幸いなことだと思いましたね」
――なるほど。清原さんはいかがですか?
清原「私にとっては、藤井監督とこうしてまた一緒に作品を作れたこと自体がうれしくて、非常に喜ばしいことなんですが、今回はそこにさらに“国際プロジェクト”という新たな挑戦が加わったことで、台湾の方々とも現場を共にできたうえに、そこでの思い出をちゃんと映画という形に残せたことも、本当にありがたいことだなと感じています。私の人生においても多くの学びがある作品でしたし、撮影中に台湾で目にしたいろいろなモノやコト、出会った人たちに対して抱いたリスペクトの気持ちを忘れずに、これからも役者として精一杯頑張っていきたいと思いました」
藤井「(しみじみと)いや…果耶ちゃん。立派な大人になったなあ。15歳のころから知ってるし、役への取り組み方や、俳優としての変遷みたいなものは見てきたつもりだったけど…」
清原「『大人になった』って言われちゃった(笑)。私、いまアミと同い年ですから!」
藤井「そうか…。アミと同い年か。じゃあ、僕の“4つ上のお姉さん”ってことですね(笑)」
取材・文/渡邊玲子










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN