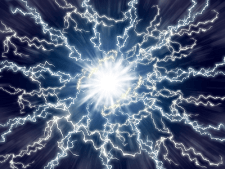医師の制止を振り切って退院「次は勝てる」
1971年にジュニアミドル級(現スーパーウェルター級)世界王者となった輪島功一さんは74年6月4日、7度目の防衛戦でアメリカのオスカー“ショットガン”アルバラードに最終15回KO負けを喫して王座から陥落する。
このファイトのダメージは深刻で、輪島さんは試合が終わると病院に直行、入院を余儀なくされた。輪島さんが50年前の試合を振り返った。
「あの試合、『オレは死なないから絶対にタオルは入れるな』ってセコンドに言ってあったの。それで、殴られて、殴られて、15回KO負け。病院で『1カ月半から2カ月入院です』と言われけど、入院しているわけにはいかないんだよ。病院にいたら内臓が弱る。それで『起きられないから救急車を出してくれ』って言ったら、出せないと。だからタクシーの後部座席を取り外して、寝台車みたいにして家に帰ったんだよ。当時住んでいた高島平の団地にね。そうしたら担架がエレベーターに入らない。どうしたかって? 11階まで担いで運んでもらったよ」
自宅でしばらくは寝たきりの生活。復帰など当然見えてこない。それにしてもなぜ、輪島さんは医師の制止を振り切ってまで退院したのだろうか。
「もう1回あいつとやったら勝てると思ったんだ。もちろん一度倒された相手だ。みんな100%勝てないと言う。でも、どこかに抜け穴がある。オレのいいところを生かせれば勝てる。これとこれを油断したから負けた。だからこことここをこうすれば勝てる、という信念があったんだよ」
寝たきりの状態から地道なリハビリへ。このような状態に陥っても闘志は衰えなかったというから驚きだ。そして王座陥落から7カ月半後の75年1月21日、アルバラードへの雪辱のチャンスを手にする。
“奇跡のカムバック”も、再びベルトを失い…
迎えたアルバラードとのリターンマッチ。輪島さんは前回の試合はオーバーワークが当日のコンディションに影響を与えたと反省し、練習の量を調整することを忘れなかった。
試合開始のゴングが鳴ると、輪島さんは躍動した。しゃがんだり、のけぞったり、いきなりパンチを打ったり、得意の変則ボクシングを遺憾なく発揮する。輪島さんは「3ラウンドまでに体力の7割を使う」という哲学を持っていた。序盤に流れを引き寄せるためにはスタミナを出し惜しみしない。これも輪島さんならではの「勇気」と言えるだろう。
アルバラードも持ち味のショットガンを炸裂させて試合は白熱。それでも輪島さんは第1戦とは見違えるような出来で、結果は文句なしの判定勝ち。リベンジ成功で王座に返り咲いた。この勝利は“奇跡のカムバック”と称賛された。一度負けた相手から世界タイトルを取り戻す。日本ボクシング史上初の快挙だった。
初防衛戦の相手は“日本人キラー”の柳済斗。1975年6月7日、ボクシングの世界タイトルマッチでは初めての日韓対決のゴングが鳴った。決して友好的とは言えなかった日韓の国民感情もあり、試合は異様な空気に包まれる。結果は輪島さんの7回TKO負け。5回終了のゴングが鳴った直後、輪島さんが両手を広げてニカッと笑ったところに柳の右ストレートが炸裂。輪島さんがダウンしたシーンが問題になった。
ゴング後であれば反則で柳に減点が科せられ、ゴング前であれば輪島さんのダウンとなり、それがジャッジに反映されるはずだが、そのどちらもないという不可解な結果となった。こうした経緯もあり、輪島さんは再び雪辱の舞台に立つことを誓ったのである。
マスクをつけて咳き込み…記者会見での“揺さぶり”
再戦は8カ月後、日大講堂で組まれた。ここで輪島さんは一計を案じる。試合前の記者会見にマスクをして登場、「ゴホッ、ゴホッ」と体調不良を演じたのだ。
「柳は強かったからね。これは何かやらなきゃと思ったんだ。それでマスクをつけた。普通はたとえ本当に風邪を引いていても、試合前にマスクなんて絶対につけない。相手に弱みを見せることになるからさ。その逆を突いたわけだ。そう、ごまかし合いだよ。みんなの仕事だってそうだろ。たかがボクシング、されどボクシングだ。煮詰めていくとそういうことになるんだよ」
柳陣営がすっかりだまされた訳でもないだろう。それでも輪島さんの“先制攻撃”にはなにがしかの意味があった。試合は輪島さんが最終15回に右カウンターを決めてダウンを奪い、劇的なKO勝ち。またしても一度負けた相手にリベンジし、“炎の男”輪島伝説は永遠に語り継がれることになったのである。
ニヤリと笑って「いいこと聞くじゃねえか」
輪島さんはこのあと、伏兵のホセ・デュランに敗れてベルトを失い、1977年6月7日、新たに王者となったエディ・ガソに挑戦、いいところなく敗れて引退した。不屈の闘志もついに燃え尽きたのか。いや、そうではなかったという。
「オレは医学も勉強するの。あのときは日常生活でもしっかり歩けなかった。試合になると一発も撃たれてないのにヒザがガクガクする。これはおかしい。己を知るんだよ。己を知って、もう続けることはできないと思ったんだ」
輪島さんは昭和の日本国民を熱狂させ、その名を歴史に刻んだ。20代半ばでボクシングを始め、考え得るあらゆる工夫を施し、ときに邪道と眉をひそめられながらも、勝利に執着した姿にはすごみがあった。そんな輪島さんに「ボクシングの魅力」を問うと、ニヤリと笑って「いいこと聞くじゃねえか」と次のように答えてくれた。
「殴れるって喜びだよ。お前だって殴りたい人、いっぱいいるだろ。でも殴ったら大変なことになるから殴らない。やったら分かるんだよ。やっぱり(殴りっこは)ダメだと辞めるヤツもいる。そこは性格だけどね」
若いころから腕っ節の強かった輪島さんだが、ケンカをしたことがなかったという。「ケンカしたら殺してやろうと思うから」という理由だそうだが、だからこそ内に秘めたパワーをリングで爆発させる喜びがあったのかもしれない。
「やっぱり世界チャンピオンになれたというのはうれしかったね。成功の喜びだな。勝てたことで、これだ、これしかないんだと思えるわけでしょ。オレなんか学歴もないからね。勝てば、よーっし、もっと稼いでやろう、とも思えるしね。いい意味で欲も出てくるんだよ」
輪島さんのラストファイトから44年後の2021年、孫の磯谷大心がプロのリングに上がった。輪島さんの長女の長男である磯谷はデビュー3年目を迎えた現在も悪戦苦闘しながら、プロ選手としてキャリアを重ねている。輪島さんがリングに注ぐ視線はいまなお熱い。
<前編から続く>
文=渋谷淳
photograph by KYODO










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN