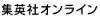ギタリスト、シンガーとして世界で戦うMIYAVIが、4月3日に最新アルバム『Lost In Love』をリリース。ニューアルバムでの挑戦や音楽の力について聞いた前編に続き、後編では、難民支援活動や世界の今について抱く思いを語ってもらった。(前後編の後編)
自分の首を絞める世界のパラドックスに対する嘆き
――アルバム収録の「Real Monster」や「Mirror Mirror」では、自分の中のもうひとりの自分が暴れているし、「Broken Fantasy」を配信リリースした際のビジュアルも血まみれで、自分の首を絞めていますよね。
血まみれのビジュアルで、「Broken Fantasy」や「Tragedy Of Us」を表現したのは、今、僕たちが地球規模でどれだけ自分たちで自分たち自身の首を絞めているかということを提示したかったから。イスラエルとパレスチナの問題も、核の問題もそう。そのパラドックスや無意味さに対する嘆きを込めています。
「Tragedy Of Us」のストーリーは『ロミオとジュリエット』。あの作品は、先祖の代から引き継いだ因果を現代に生き愛し合う二人が清算しなければいけなかった、というお話ですよね。難民問題も当事国だけの問題に見えがちですけど、元々分断が起きてそれぞれ民族が元いた場所にいられなくなった背景には、日本やアメリカ、イギリスも含めた世界中の先進国がどこかで関わっている。
本来、愛し合って認め合い、助け合わないといけないのに、傷つけ合い、首を絞め合っている。結果的に、またそれが自分たちに跳ね返ってくる。その中で自分たちが自分の世代でどう生きるか、どう未来を変えるために存在できるかが大きいと思って、そういったメッセージも込めて「Tragedy Of Us」を書きました。
難民支援につながるアンジェリーナ・ジョリーとの出会い
――MIYAVIさんが、世界での活動に目を向けたきっかけは何だったのでしょうか。
17歳で東京に来て、18〜19歳でアジアの国でパフォーマンスを始めて、自分のアイデンティティに向き合いはじめました。なんで俺はギタリストとして西洋の楽器を弾いているんだろう、日本人、アジア人としての自分の存在意義はどこにあるんだろうって。大きな世界の中にいる自分を意識し始めました。徐々に、オリコンではなくてビルボードの中で自分はどう存在できるのかを見たくなった。そこからですね。
――25歳で単身、ロサンゼルスに行かれたことも大きかったですか?
海外に行くようになって、自分の知らなさ、小ささに気づきました。英語もしゃべれなかったから。25のときに身ひとつで行って、発電機を買って、サンタモニカとかヴェニスのストリートでパフォーマンスしたり。やっぱりデカかったですね、海外は。そこからまたワールドツアーもたくさん行って、映画にも出演して(アンジェリーナ・ジョリー監督『不屈の男 アンブロークン』に出演)。ずっとギター持ってガンガンロックしてたのが、いきなり手ぶらでレッドカーペットに放り投げられましたから。「何しゃべればいいの?」っていう感じですよね。
――MIYAVIさんは、難民支援や社会問題への発言をされていますけど、日本でそういう振る舞いをするアーティストは少ないですよね。
あまりメリットないというか、むしろ後ろ指を刺されることの方が多かったりしますから。日本では、エンターテインメントはエンターテインメントとして割り切る文化があります。僕はそのあり方は否定しないし、むしろそういうスタイルでしか成し得ないこともあると思う。とはいえ、子育てや政治もそうだけど、日頃、自分たちアーティストもいろいろなものから影響を受けるし、そういった日々の暮らしや世界の情勢から、切り離せない部分はあると思うんですよね。
まして影響力を持ってくると、発言する意味が大きくなってきて。僕はそれをアンジェリーナ・ジョリーさんの出会いで気づかされました。6人の子どもを育てながら第一線で活動して、かつ難民支援もやって国連でスピーチして、単純にかっこいいなと思ったし、そうなりたい、なれる努力をしようと思いました。
初めての難民キャンプの帰り道、ずっと泣いていた
――そういう活動をやらなければいけないと思った理由はなんだったんでしょうか?
今はソーシャルメディアが発達して、地球の裏側で起きた出来事が瞬時にわかります。だけど、リアルに今、世界のどこかで紛争が起きて誰かが犠牲になっている中で、僕たちは音楽をやって、楽しんだりしてる。これも事実であって。じゃあその中で、「どうやって向き合っていくの?」っていうことだと思うんですよ。
誰だって、パーティしているときに難民や紛争の話なんて聞きたくないわけじゃないですか。それは間違ってないと思うんですよね。だって人間だから。つらいことがあっても飯、食えよって。それぞれのバランスとそれぞれのやり方でやっていけばいい。これは僕にとって大きなテーマでもありますね。
難民支援に関しては……やっぱり一度見てしまったら、目を背けられないですよね。初めておそるおそるレバノンの難民キャンプに行ったとき、防弾の窓ガラスの車に乗って、テロがあったショッピングモールに行って、ホテルに入るのもセキュリティを通らないといけないような状況。空港にも2か所、セキュリティがあって、兵隊が銃持って歩いてる。なんだこれは?って。
難民キャンプに着いて、自分が持ってるギターを見て「Wow!」って言う子どもたちと、泥まみれでわーって遊んで。山の向こう側のシリアは紛争している最中で、畑で一緒にサッカーやって……帰り道、ずっと俺、泣いてました。ロスに帰ってから、現地の職員から「子どもたちがロックスターになりたいって言ってる」って聞いて、また(涙が)ダーって。そんな簡単なことじゃないよ、ギターさえないんだから……だけど、少しでも新しい世界を見せてあげられた。そのことにはすごく可能性を感じて、自分にも何かできるのかも、って思ったんですよね。
ギターがあるからどこへでも行ける
――MIYAVIさんが難民キャンプで子どもたちと一緒に歌ったり、サッカーをしていることと、音楽活動の根本は同じなんですね。
そんな偉そうなことは言えないですけど、観る人、聴く人たちにとって新しい世界、体験でありたいですよね。難民キャンプで子どもたちが感じた「Wow!」と同じ「Wow!」を僕は世界中どこででも提供してるつもりだし、その人が驚いた時や感動した時の混ざり気のない感覚には希望しかないから。それをステージのパフォーマンスや楽曲を通じて伝えていきたいです。
――MIYAVIさん、いろいろな方向で幅広く活動をされていますけど、その原動力は何なんでしょうか?
……まあ、大阪人やからじゃないですか(笑)。
――(笑)。
それが僕の属性で、得意だからやっているだけであって。もちろん、得意じゃないことを得意にもしてきました。歌だって得意じゃなかったから。デビューした頃、デタラメな英語で歌ってた僕が、今はグラミー獲った人たちと一緒に楽曲作って、「いいボーカルだった」って言ってもらうこともある。これは僕自身の自信にもなってるし、応援してくる人たちにとっても自分を通じて人間の可能性を提示してる部分もあると思う。ちょっと大袈裟かもしれないけど。得手不得手がある中で、それぞれのテリトリーで自分なりにやっていく。それに尽きると思います。
――最新作では普遍的なテーマに向き合って、今後、MIYAVIさんは何を伝えていくのか気になります。
それは考えてないですね(笑)。でも、ギターと歌だけで作るとか、それこそオーケストラとか、違う形態での作品作りもやってみたいです。今回、いろんな人とコライトしてますけど、これって実はすごい危険なんですよ。結果的にしっちゃかめっちゃかになりかねないから。でも、それで自分が浮き彫りになるし、誰とやっても自分自身でいられる自信があるからやれる。やっぱりギターの存在は大きいですね。ギターがあるからどこへでも行けるし、歌も歌える。自分でギターを弾かない曲なんて、今までなかったですから。やっぱり自分が信じられるものがあるのは強いですよね。
取材・文/川辺美希 撮影/村井香
ジャケット/ヴェルサーチェ ジャパン
〈問い合わせ先〉www.versace.jp
スタイリング/櫻井賢之[casico]










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN