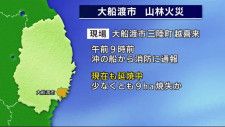南陽・林野火災、暖冬少雪で延焼拡大か 専門家指摘、雪解け早く山の地表が乾燥
東京理科大創域理工学研究科の桑名一徳教授(51)=国際火災科学専攻=は、この時期に全国で相次ぐ大規模山林火災について「延焼拡大には気象条件が大きく影響している」と話す。暖冬少雪で雪解けが早まって山の地表の水分が少なくなって乾燥し、結果的に延焼が進みやすい環境だったと指摘する。
もっと広い視野で見れば世界的に地球温暖化で気温が上昇していることも「地表の水分が蒸発し乾燥するなど燃えやすい環境となる」と懸念を示す。海外でも大規模な山火事は頻発しており「森林火災で大量の二酸化炭素が放出され、それが温暖化を加速させる」と危機的な状況を提示した。
山形大農山村リジェネレーション共創研究センターの林田光祐プロジェクト教員・教授(65)=森林保全管理学=は暖冬少雪に加え、手入れが行き届かなくなっている山林が増加している観点から検証し「昔は燃料に使うため低木を刈り取ったが、最近は放置されている。その落ち葉が堆積し燃え広がりやすい状況にあるのでは」と指摘した。一定の幅で樹木を伐採し、下刈りして延焼拡大を防ぐ防火帯の意識も薄れつつあるとして「行政や地域を含め雑木林をどう適正に管理していくかが問われる」と話した。
置賜広域行政事務組合消防本部の杉原利彦消防次長兼南陽消防署長は「乾燥と強風が相まって、想像以上に速いスピードで燃え広がった」と振り返る。幹まで燃える樹木もあり、炭化して風にあおられて再燃したといい、「木の根が火種となり、地表の枯れ葉に燃え移り、葉っぱの層でくすぶる状態だった。上空からの放水では根や葉の層に水が届かなかった」と語った。
山形地方気象台によると、現場に近い米沢地点は4月中下旬の降水量が「かなり少ない」状況だった。平年比で中旬17%、下旬4%。5月初旬も高温乾燥の状態が長期間続いていた。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN