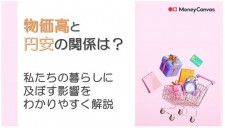もうけた経済界から「お腹いっぱい」の声
日本は国を挙げて、国民に多大な犠牲を強いながら壮大なお笑い劇を演じている。これがお笑いでなければいったいなんなのか、私には皆目見当がつかない。
5月10日、鈴木俊一財務相は閣議後の記者会見で、行きすぎた円安ドル高の水準に対して、経済界から懸念の声が上がっていることを受け、「(政府として)市場の動向にもとづいて適切に対処する」と述べた。同じ日に岸田文雄総理も、経済財政諮問会議で「最近の円安の動きを十分注視しており、政府・日銀は引き続き密接に連携していく」と発言した。
1ドル150円台で推移している過度の円安のせいで、現在、なにが起きているか。海外展開をしている企業を中心に、過去に例がないほど収益がふくらんでいる一方、消費者は激しい物価高にあえいでいる。要するに、企業をもうけさせるために国民が苦しめられているのだから、弱者の味方であるはずの野党やメディアから、真っ先に是正を求める声が上がらないとおかしい。
ところが、野党は沈黙したままで、メディアも円安や物価高の話題を断片的に取り上げるにすぎない。そんななか、「いくらなんでも(1ドル)150円を超えるのは安すぎる」と発言したのは、経団連の十倉雅和会長だった。円安の是正を求める声は、もうけている当事者であるはずの経済界から相次いでいるのである。
最初に注目されたのは、ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長の発言だっただろうか。4月11日の決算会見で円安について、「当社に対してだけでなく、日本にとっていいわけがない」と語った。
その後は、同様の指摘が重ねられている。経済同友会の代表幹事を務めるサントリーホールディングスの新浪剛史社長は「是正が必要なレベルになってきている」といい、日本・東京商工会議所の小林健会頭はさらに踏み込んで、「他国との協調介入も検討してほしい。中小企業にとって原材料高騰で苦しい」と発言。さらには、円安のおかげで過去2番目の利益を上げている三菱商事の中西勝也社長までが、「円というのは国力を表すので、円安が進むということは国力が弱くなるというような側面もあります」と指摘している。
賃金上昇は物価高に追いつかない
岸田総理は、先に引用した内容を述べた同じ場で、「賃金や所得の拡大(中略)への対応に全力をあげて取り組み、経済の好循環を実現する」と述べた。しかし、現況をみるかぎり、その実現はきわめて困難だといわざるをえない。
厚生労働省が5月9日に発表した、3月の毎月勤労統計調査(速報値)によると、物価変動を考慮した1人当たりの実質賃金は前年同月比2.5%減で、24カ月続けてマイナスになった。給与の総額は伸びているものの、物価高にまったく追いつかない。
厚労省は、4月分からは、春闘の影響が反映されはじめるとの見方を示している。たしかに今春の春闘では、連合の集計によると、ベースアップと定期昇給を合わせた賃上げ率は平均5.17%で、1991年以来の高水準となった。しかし、3月の消費者物価指数は、変動が大きい生鮮食品を除く総合指数が前年同月比で2.6%上昇し、31カ月連続でプラスを記録した。4月以降の急激な円高の影響は、これから数字に表れるから、賃上げ分など簡単に吸収してしまうだろう。
仮に、実質賃金が多少プラスになったとしても、こうも物価高が続くかぎり、消費マインドが上向くとは考えられない。経済同友会の新浪代表幹事は、「仮に1ドルが160円を超えてくるようなことになれば、実質賃金がプラスに転換しても消費にプラスにはならない」と述べている。
円安の恩恵を受けている企業は多い。SMBC日興証券の集計では、3月期の上場企業の純利益総額は、3年続けて過去最高になる見込みだという。また、日本政府観光局(JNTO)によると、4月の訪日外国人旅行者数は円安の追い風を受けて、3月に引き続き300万人を超え、304万2900人(推計値)となった。このため、コロナ禍で苦境を強いられてきた運輸業界やホテルなどの業績も急回復している。
しかし、そこだけを見て安心し、円安がもたらす負の効果から目をそらしていると、日本の沈没は避けられない。それが見えるからこそ、円安でもうけている当事者である経済界から、円安の是正を求める声が上がるのである。
企業の利益は消費者から搾り取られている
これまでも再三述べてきたが、現在の異常な物価上昇の原因は、そのほとんどが円安に求められる。日本が世界でもまれなほどの輸入大国だからである。
農林水産省が公表している2020年のデータによれば、日本の食料自給率は38%(カロリーベース)にすぎない。主要国をみると、カナダ266%、オーストラリア200%、アメリカ132%、フランス125%、ドイツ86%、イギリス65%、イタリア60%、スイス51%。G7の平均も102%で、日本が群を抜いて低いことがわかる。
ほかにも、衣類の輸入依存率は97%で、その素材となる綿花や羊毛は100%を輸入に頼っている。木のぬくもりが日本の伝統のように語られるが、木材の輸入依存率は70%に達する。鉄鉱石は100%である。さらには、原油やLNG、LPGなどのエネルギーの輸入依存率は88%を超える。
こうしたデータから、日本は自国の通貨価値の下落が、他国以上に消費者の生活を直撃する国であることがわかる。たとえば、国産の野菜の価格高騰は天候不順などが原因で、円安とは関係ないと思うかもしれないが、そうではない。輸入肥料をあたえ、ハウスなどで燃料を消費して栽培し、産地から消費地に運ぶのにも燃料が費やされるのだから、円安の影響が小さいとは到底いえない。
私たちの生活がこれほど全方位にわたって輸入に依存している以上、円安が続くかぎり物価の上昇は避けられないし、止まったとしても高止まりするほかない。
物価高については、考えておかなければならない重要な問題がもう一つある。円安が企業に好業績をもたらしているのは事実だが、それは消費者の利益に反している、という問題である。物価が下がり続けるデフレの状況には終止符が打たれたが、それを受けて企業は、円安によって原材料などのコストが増加した分を、価格に転嫁するようになった。だから利益は上がっている。いわば、企業は消費者に物価高騰を強いて利益を得ており、こんな状況が続けば、さすがに消費者は疲弊し、消費マインドが後退して景気がしぼむ。そうなると自分たちも利益を上げられなくなるから、行きすぎた円安を懸念する声が、経済界から上がるようになったのである。
上場企業が空前の利益を上げているのだから、賃上げに反映されるはずだ、と考えるのは甘い。原材料の高騰分を価格に転嫁できない中小零細企業にとって、賃上げどころでないのはいうまでもない。だが、じつは、大企業も事情はあまり変わらない。日本ではいったん賃金を上げると、経済情勢が変わっても引き下げるのは難しい。このため、永続的に利益を上げられると確信できないかぎり、企業が賃金を大きく上げることはない。円安への懸念が経済界から示されているのは、昨今の利益の水準は一時的なものだと、ほかならぬ企業自身が認識していることの証だろう。
それでも野党もメディアも声を上げない
それでは、なぜ、これほどの円安がもたらされているのか。それはひとえに日銀が金利を上げないからである。この円安につながった「異次元緩和」と呼ばれる大規模な金融緩和は、2013年4月、アベノミクスの「第1の矢」を担った日銀が導入した。
それが、これほどの円安につながるようになったのは、コロナ禍の収束後である。欧米諸国ではポスト・コロナのインフレを受けて、2021年から中央銀行が金利を引き上げた。しかし、日銀だけは例外で、金利を抑えたままにした。このため、日米および日欧の金利格差が急拡大し、大幅な円安につながったのである。では、なぜ日銀だけは、金利を上げないという判断をしたのだろうか。
異次元緩和によってもたらされた歴史的な低金利によって、日本政府は躊躇なく国債を発行し、財政出動できるようになった。極論すれば、効果があるかどうかなど考えずに、各方面に予算をばら撒けることになった。その結果、すでに2012年末には705兆円と、毎年の予算の数倍におよんでいた国債残高は、2023年末には1070兆円前後にまでふくらんでしまった。いま金利を上げれば、国債償還額が跳ね上がってしまう。そもそも国債は日銀が大量に買い上げており、金利を上げれば日銀のバランスシートが悪化する。だから低金利を解消せず、ひいては円安を放置している。
しかし、物価高の大本である円安、それをもたらす低金利を放置しているから、物価高を補正するために国債を発行して予算を組む、などという本末転倒もまかり通る。こんなことを続けていたら、ますます円安になり、さらなる物価高を招くだけだ。しかし、国債の山の前に自縄自縛状態になって、なんら手を打てないことになる。
日本の財政がこれほど放漫化したのは、異次元緩和のせいであり、それをむやみに続けてきた日銀の責任である。効果が疑わしい政策のために予算をばら撒くような愚策を、これ以上重ねないためにも、日銀はいまの緩和政策をあらためるべきである。それがすなわち、円のレートを適正に導き、物価高を抑制し、私たちの実質賃金の上昇につながる。
しかし、こうした声が、これまで緩和政策と円安の恩恵にたっぷり浴してきた経済界から真っ先に上がるというのは、やはりお笑い劇としかいいようがない。これほど国民が苦しめられているのに、なぜ野党もメディアも声を上げないのか。日本はもう経済では勝負できないから、「お笑い」で勝負しようとでもいうのだろうか。
香原斗志(かはら・とし)
音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』(ともに平凡社新書)。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え!』(アルテスパブリッシング)など。
デイリー新潮編集部










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN