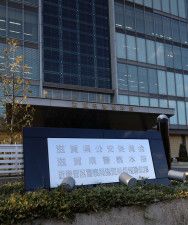あのまちでしか出会えない、あの逸品。そこには、知られざる物語があるはず! 「歴史・文化の宝庫」である関西で、日本の歴史と文化を体感できるルート「歴史街道」をめぐり、その魅力を探求するシリーズ「歴史街道まちめぐり わがまち逸品」。
今回は、滋賀県近江八幡市の「江州ヨシ」。琵琶湖最大の内湖である西の湖の周辺には水郷地帯が残り、船での遊覧が観光の目玉となっている。そして、この水郷に育まれたヨシは、多様な分野で活用される特産品であった。人とヨシとの関わりから古来の生活文化のあり方を探る。
【兼田由紀夫(フリー編集者・ライター)】
昭和31年(1956)、兵庫県尼崎市生まれ。大阪市在住。歴史街道推進協議会の一般会員組織「歴史街道倶楽部」の季刊会報誌『歴史の旅人』に、編集者・ライターとして平成9年(1997)より携わる。著書に『歴史街道ウォーキング1』『同2』(ともにウェッジ刊)。
【(編者)歴史街道推進協議会】
「歴史を楽しむルート」として、日本の文化と歴史を体験し実感する旅筋「歴史街道」をつくり、内外に発信していくための団体として1991年に発足。
太古からの日本の原風景だったヨシ原
池や川の水辺に高々と茂る植物、ヨシ。現在はヨシが標準和名とされるが、古くはアシと呼ばれ、平安時代以降に「悪(あ)し」に通じる名を忌み、「良し」へと言い換えるようになったという。
漢字では葭、蘆(芦)、葦の文字が使われる。「豊葦原瑞穂国(とよあしはらのみずほのくに)」「葦原中国(あしはらのなかつくに)」とは、上古のこの国の美称である。
湿地を稲作の場とした弥生時代の人々にとって、ヨシは生活圏のどこにでも生い茂っていたことだろう。そして、そのころからヨシは、人の暮らしのなかでさまざまに利用されてきたのであった。
引き継がれる神事で、ヨシの火が春の夜を焦がす
近江八幡の春は、火祭りの季節である。3月中頃の土曜と日曜日(今年は3月16日・17日)に開催される「左義長まつり」では、旧城下町の各町から松明に「ダシ」と呼ばれる干支(えと)の作り物を取りつけた左義長が担ぎ出され、二日目の夜、日牟禮八幡宮にて順番に火が放たれ、惜しみなく燃やされる。
そして、4月14日・15日に開催される日牟禮八幡宮の例祭「八幡まつり」では、近江八幡周辺地域を合わせた十二郷が大太鼓を繰り出すが、太鼓を打ち鳴らしながら宮入りする本宮「太鼓まつり」に先駆けて、一日目の宵宮(よいみや)では「松明まつり」が執り行われる。
この松明まつりでは、高さが10メートルにもおよぶものがある「笠松明」、担ぐなどして燃やしながら持ち込まれる「引きずり松明」、抱え持って演舞を行う「振り松明」など、大小およそ200本の松明が奉火され、春の宵闇に神社楼門を浮かび上がらせる。
なかでも大房町の大松明は傾けた状態で先端に点火され、そのまま大勢が竹竿を構えて突き起こすという勇壮なものである。また、八幡まつりにあわせて、近江八幡周辺50余の神社でも、4月中を中心に3月から5月に松明を奉火する祭礼が行われる。
これら松明まつりの起源は古く、伝承によると、この地に行幸した応神天皇を、地元の民がヨシの松明を灯して案内したことに由来するという。そして、現在の祭りの松明にも主な素材としてヨシが使われているのである。
ヨシは原始より身近にある優れた素材であった。弥生時代の竪穴住居の屋根を葺(ふ)くのに使われた第一の素材と考えられ、のちの瓦屋根の普及に至るまで、耐久力が高い最良の屋根素材として扱われてきた。
特にヨシを豊富に産した湖東地域に残る茅葺(かやぶ)きの家屋には、ヨシが使われているものが多く、安土にある沙沙貴(ささき)神社の楼門は壮麗な姿のヨシ葺き屋根を今に伝えている。
また、琵琶湖岸の弥生時代の遺跡からは、ヨシ簀(ず)を用いた川で魚を捕る仕掛け、簗(やな)が見つかっている。
琵琶湖の漁具の代表である魞(えり)は、近世以降に仕掛けが巨大化して竹簀が素材とされ、現在はさらに網を用いるようになったが、これもかつては内湖にヨシ簀を使って設置した小型のものだった。魚の入りがよかったといい、明治時代までヨシを素材に使った魞があったという。
ヨシ簀は、風通しのよい日除け、簾(すだれ)として重宝されてきたものでもある。家屋の外からの人目を避けながら、内側からは外を見通せるのも利点であった。
京町家の夏の設えとして襖(ふすま)と交換するヨシ戸やヨシの衝立(ついたて)などは、日本家屋の美の一つといえよう。商店の軒先に立てかけられた立て簀も、夏日の懐かしい風景である。そのほかにも、ヨシ簀は茶農家が使う覆いとして大量の需要があった。
サステナブルな素材としての可能性を模索
ほかにもヨシを使った製品としては、毛筆の軸や筆先の鞘(さや)、よしぶえ、雅楽で使われる管楽器「篳篥(ひちりき)」のリード部分にあたる「舌(ぜつ)」などが知られる。
さらに、ヨシの根などを乾燥させたものは生薬とされ、ヨシの新芽は食用にすることもできた。屋根を葺き替えて取り除いた古いヨシは最上の肥料になったといい、ヨシは土に返るまで利用できる素材であった。
しかし、戦後、国内でのヨシの需要は激減する。大口の納品先であった茅葺き屋根の家屋は希少となり、ヨシ簀などもプラスチック素材ほかの別製品に置き換わり、さらに中国からの安い製品が台頭した。高級な家具や建具の素材として注目されても、そのニーズは失われた量に比べてあまりに小さい。
江州ヨシの産地として知られた湖東の内湖のヨシ地は、近世から個人の所有地、いわばヨシ畑として管理されてきた。現在の西の湖でもそれは引き継がれている。それだけにヨシの需要の減少は、ヨシ地の運用そのものに影響を与えている。ヨシ刈りの人件費が確保できず、人員を集められないこともその一つである。
ヨシ地は毎年3月中に、刈り取った地に火を放つヨシ焼きを行う。それによって4月から新芽が出て、青々としたヨシ地へと成長する。
その一年のサイクルを維持するためには、ヨシ焼きまでの刈り取りを欠くことはできない。近年、西の湖のヨシ地では、イベントを企画するなどしてボランティアを集めてヨシ刈りに対応するようになっている。
そのヨシ刈りに以前より参加してきたのが、近江八幡で江州ヨシの製品を扱うショップ「アトリエ伸」を営業する千賀伸一さんである。
「私は京都出身ですが、近江八幡に移って地域おこしのイベントに関わってきました。この店もそんな活動の延長です」という千賀さんだが、店を設けるまでになったことには、ヨシの研究者だった西川嘉廣氏との出会いの影響が大きかったという。
西川氏は、近江八幡の水郷地域に江戸時代から屋敷を置くヨシの卸商「西川嘉右衛門商店」に生まれるが、東京大学医学部、同大学院を経て、薬学博士として国内外の大学で基礎医学と薬学分野での研究、教育にあたった。
定年を迎えた平成12年(2000)、実家に戻って家業を継ぎ、17代当主となり、翌年には実家内に「ヨシ博物館」を開設。著書『ヨシの文化史─水辺から見た近江の暮らし─』もまとめられた。しかし、平成24年(2012)に亡くなられ、ヨシ博物館の資料は滋賀県立琵琶湖博物館に寄贈されている。
千賀さんは、一本のヨシの先を繊維状にした「よし筆」を独自に開発して、お店でも販売している。この筆は西川氏と懇意にするなかで生まれたという。
「ヨシは油分が強く、繊維状にするだけでは、墨汁も絵具もはじいてしまいます。西川先生に相談すると、ヨシを燃やしたのちの灰は『油落とし灰』として、かつて販売されていたことを教えてくれたのです」。
実際にヨシの灰を入れた沸騰水に筆先を入れることで、脱脂されて筆として使えるようになったという。「使用する灰は筆作りで出た端材を燃やしたもの。ヨシは本当に捨てる部分がないのですよ」。
思いがけないかすれがでるのが、むしろ魅力という「よし筆」だが、製品として購入するより、自身で作ってほしいと千賀さんは語る。
ヨシについて知り、琵琶湖の環境について考えてもらうきっかけとして一番いいのは、ヨシ刈りなどに参加してヨシに触れ、それで何かを作ってもらうことだと続ける。確かにヨシには、はるかな人の営みを思わせる手触りがあった。それは、ただ消費するだけではない、創造という暮らしのあり方を思い起こさせる。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN